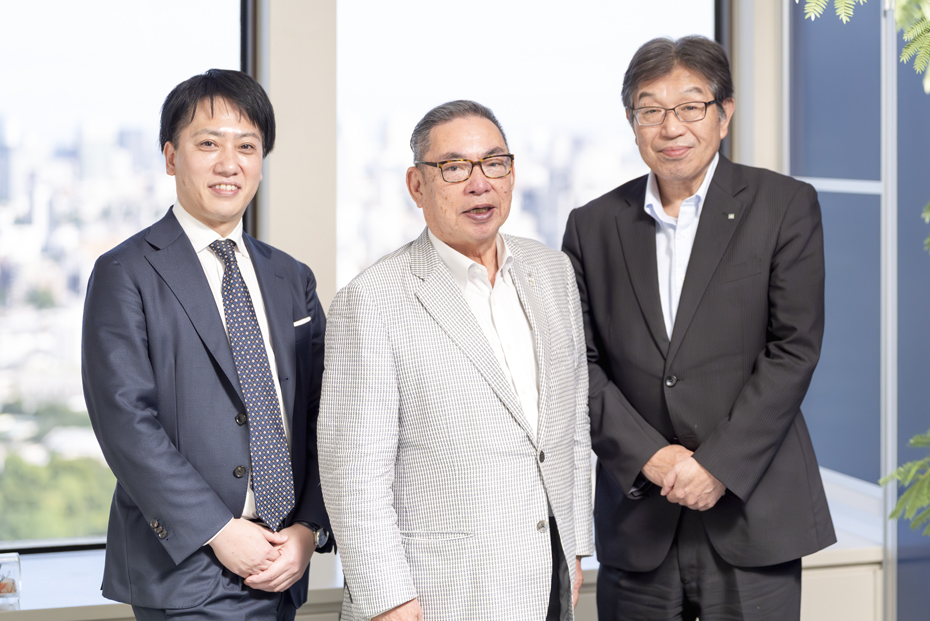独自の人事サービスを創り上げた企業文化を受け継いでほしい。
成長への道を歩む“Win-Win”のバトンタッチ
人事・採用支援サービスを提供する株式会社トライアンフは、自社の人材を育て上げるとともに顧客と深い信頼関係を構築し、着実な成長を遂げてきた。2024年、AI技術を活用したサービス開発に強みを持つ株式会社PKSHA Technologyへ、株式譲渡によるM&Aを実施したのはなぜか。創業者であり前社長の樋口 弘和 様に、M&A決断までの経緯と、譲受企業に求めた条件などを語っていただいた。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社トライアンフ
- 所在地
- 東京都渋谷区
- 事業内容
- 人事コンサルティング、人事アウトソーシング、採用コンサルティングなど
- 資本金
- 225,109,548円
- 従業員数
- 202名
- M&Aの検討理由
- 後継者不在、さらなる成長発展のため
-
譲受企業
- 会社名
- 株式会社 PKSHA Technology
- 所在地
- 東京都文京区
- 事業内容
- アルゴリズムライセンス事業
- 資本金
- -
- 従業員数
- -
- M&Aの検討理由
- 新分野への進出のため
最先端の人事制度を学ぶとともに自ら事務作業に手を動かして、
広範囲な仕事を経験した
創業までの樋口様のキャリアを振り返っていただけますか。

私のキャリアのスタートは、新卒で入社した横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現:日本ヒューレット・パッカード合同会社、以下HPと表記)でした。アメリカに対する憧れがあり、工場見学で目にした自由闊達なオフィスの雰囲気や、大学生採用の1期生としてアメリカで仕事をする機会が約束されていたことも決め手でした。
入社後の7~8年間は、工場で生産管理の仕事をしていました。私はラグビー選手として入社しましたので、夕方5時になるとラグビーの練習が始まる生活でした。30歳まで現在のトップリーグのレベルで、この小さな身体でそれなりにがんばっていたのです。現役を退いてからは、「工場以外の勤務も経験したい」と異動を願い出たところ、たまたま人事部門に配属されました。これが後年、株式会社トライアンフの創業につながっていくわけです。
憧れていたアメリカでの勤務も経験されたそうですが、そこで何を得られましたか。
HPは世界トップレベルの先進的な会社でした。80年代の時点で既にアメリカでは、ダイバーシティ(多様性)やビジネスパートナーとしての人事の役割など、日本では聞いたこともないような概念がさかんに議論されていました。私は現地社員の話を聞き、最先端の人事施策を学んで日本に持ち帰るために、たびたび出張していたのです。
見聞きすることすべてが新鮮で、日本の20年、30年先を先取りするのはエキサイティングな経験であると同時に、「早く追い付かなくてはいけない」と危機感を持ちました。アメリカのHPで得た学びを活かして、日本法人で社内公募制度の導入を提案し、実行に移していきました。
ただ、人事の仕事は華やかなものばかりではなく、むしろ給与計算や採用手続きといった地道な業務が大半です。私自身は、こうした事務的な仕事が不得意で、数年間苦戦したこともありました。しかし、後年に創業した会社の4分の1ぐらいは、苦手だった事務作業によるものだったので、何が幸いするかわからない不思議な思いがします。社長である私自身、事務作業の苦労が骨身に染みていたので、社員もついてきてくれたのではないかと思います。
多くの同業他社が採用強化サポートに絞るなか、給与計算も社内の制度設計として支援できたのは、泥臭い仕事を経験したおかげです。
経営の教科書には無い独自の方法で事業拡大を実現した
独立して、株式会社トライアンフを起業してからは、どのように事業を拡大されたのでしょうか。

1998年、40歳のときに株式会社トライアンフを設立しました。最初は法人社宅の管理など、総務系のアウトソーシング業務からスタートし、古巣であるHPからも仕事を受注しています。徐々に人事関連の業務全般へと広がっていくのですが、創業時にこれといった具体的なビジョンは無く、「お客様のニーズに応えながら、自分の好きな人たちと一緒に仕事をしていきたい」という思いでいました。
最も重視したのは人材です。能力や経験があるのはもちろん、私たちのカルチャーに馴染む人材だけを厳選しました。都合の悪いことを隠さない誠実な人や、高い正確性が求められる地道な事務作業もいとわない人を優先的に採用しました。気づけば、女性社員が8割を占めるユニークな組織になりました。
クライアントの選定にも、こだわりを持ち続けています。アウトソーシングの世界では、お客様からのあたりが強く、ときにはハラスメントに発展する場面もあります。そのようなときは、責任者に直接お会いして、改善を求めました。そのまま契約解除になったこともありますが、優しく丁寧な対応をしてくださるお客様には、徹底的に尽くしてきた自負もあります。長いお客様では、創業時から30年以上のお付き合いが続いており、今も契約を結んでいただいていることには喜びを感じています。
社員を大切にしてこられたことが伝わってきます。
創業時からずっと1on1の面談を続けて、社員たちの声に耳を傾けてきました。突然の離職防止や、キャリアチェンジの支援にもつながったと思いますが、他方ではカルチャーを大切にしすぎて、事業の拡大スピードが遅くなったのではないかという見解もあります。
一定の年齢で経営のバトンを渡したい
規模、売り上げ共にここまで育て上げた会社のM&Aを検討したのは、なぜでしょうか。

知り合いの経営者仲間の動向を注視していたことが大きいです。上場やMBO(経営陣による買収)を行った方々の話を伺う機会もありました。それまでM&Aを実施したケースは身近になかったのですが、「自分が元気なうちに会社を引き継ぎたい」との想いは強くなっていました。
トライアンフは結果的に、独特な企業文化を持つ会社として発展を続け、社員はもちろん、クライアント企業とも深い信頼関係を築いてきたつもりです。それなりの利益を出していて、魅力的な取引先があるからこそ、これまでも「買いたい」という話は、多少なりともありました。
しかし、経済的合理性だけで相手先企業を選び、カルチャーが合わなかったら、もとからいた社員は続々と辞めてしまうでしょう。人材で成り立っている会社だからこそ、相手探しは細い糸をたぐるような感覚を持っていました。「相当な時間がかかるだろう」と、覚悟せざるを得なかったのです。
ここからは、担当アドバイザーの大竹さんにも加わっていただきます。どのように支援をしていかれたのでしょうか。

もともと、私から樋口様にお送りした手紙がきっかけで、お会いさせていただくようになりました。先ほどもおっしゃっていたように「企業文化を大切にしたい」ということは、最初から伺っていました。強い信念をお持ちなので、将来的なM&Aの実現に向けて「3年程度は必要だろう」と、覚悟されていたことも印象に残っています。
トライアンフも、譲受側の企業も、双方に相乗効果が生まれるような提案をする必要があると直感しました。
私が相手に求めた条件は3つでした。1つ目は、再三お話ししているカルチャーのマッチングです。これがずれていると、会社がボロボロになってしまいます。2つ目は、事業のマッチングです。人的パワーを集約してきたビジネスをさらに拡げるには、何か革新的な技術を持っている会社である必要性を感じていました。
そして3つ目は、リーダーです。業績を伸ばすために、私よりも圧倒的に優秀なリーダーに率いてほしかったのです。

のちに譲受企業となる、株式会社PKSHA Technologyが「トライアンフに関心を持っている」と社内で情報を耳にしたのは、M&Aの準備が始まって1年ほど経過したタイミングだったかと思います。
PKSHA Technologyの創業者である上野山 勝也様は、若くして東京大学発のベンチャーを成功させた方で、樋口様も興味を示されたため面談の場を設けました。
他の企業ならば面談しようとは思いませんでしたが、上野山さんのお名前は存じ上げていたので、一度会ってみたいと思いました。話してみると彼もまた、シリコンバレーで創業のアイデアが生まれ、自由闊達な競争社会で育てられたそうです。振り返れば、HP時代の私も同じ土壌で鍛えられた共通点があり、これはおもしろい人物だと、直感が働きました。
初回の面談で、カルチャーや事業の面でもある程度の親和性を感じ取った私は、その週末には無理をいって、再度時間をとってもらいました。これまで事業パートナーとして、ずっと会社を支えてくれた妻も参加しました。会話を通じて、妻もまた、上野山さんの人間性に惹かれたようでした。
ビジネス上の判断の前に、人柄や価値観での適合性を確認する重要な機会となったわけです。M&Aは私にとって、単なる事業の売買ではありませんでした。「カルチャーと価値観を引き継いで、発展をもたらしてくれる相手を見つけたい」と考えていた私にとって、この面談は、欠かすことのできないプロセスだったと思います。
PKSHA Technologyは先進的なAI技術をお持ちです。相乗効果については、どのようにお考えでしたか。
トライアンフの主要なメンバーも「一緒にやりたい」「おもしろそうだ」といった、前向きな反応でした。そこで、ビジネス面のシナジーを探るため、実務レベルでのミーティングを両者合同で開始したのです。通常のM&Aプロセスで考えれば、早すぎたかもしれませんが、私はリスクを承知で進めることにしました。この過程で、それまで人力に頼っていたサービスも、AI活用によって、高精度かつ高速化できる可能性を確認できました。
さらに幸運だったのは、PKSHA Technologyの社外取締役の一人が、旧来から心を許している友人だったことです。彼が間を取り持つようにして、隠し事なく対話を重ねた結果、すでに私の心は決まっていました。通常であれば、複数の企業からオファーを受けて選択肢の中から決めるのかもしれませんが、私とトライアンフにとってはラッキーなめぐり合わせだったと思います。
「リーダーシップを取ってほしい」本気のサポートを期待した
基本合意以降、成約に向けたM&Aキャピタルパートナーズの支援については、いかがでしたか。

M&Aキャピタルパートナーズのサポートがなければ、これほどスムーズに、M&Aの取引が完結することは難しかったでしょう。特にデューデリジェンスのプロセスは、多くの経営者にとって初めて経験することで、緊張感と不安を伴うものです。このプロセスでは「私たちの不安を理解し、リーダーシップを発揮してほしい」と、苦言を呈したこともあります。
期待の裏返しとはいえ、顧客からプレッシャーをかけられ続けた大竹さんの負担は察するに余りありますが、常に迅速な対応を行ってくれました。法人名義の資産を処理する際に伴う煩雑な手続きも、社内に抱える公認会計士などの専門家を交えて、最適な解決策を見出したのは、さすがというほかありません。今後、友人・知人からM&Aの相談を受けることがあれば、躊躇なく大竹さんを推薦するつもりです。
時には厳しく、貴重なご指導をいただきました。これまでM&Aのアドバイザーとして、中立的に両者の間を取り持つことを優先していた私にとって、「プロセス全体をリードして積極的に道筋を示してほしい」という樋口様からのご指摘は、大きな気付きとなりました。
結果的に、今回の取引を通じて、私自身が成長できたと感じています。近い将来、お知り合いの経営者の方々を安心して紹介いただけるように、この経験を今後の支援に活かしていきたいと思います。
最後に、これからM&Aを検討される経営者の皆さまに向けたメッセージをお願いします。

M&Aは、経営者が長年かけて築き上げてきた「事業と文化の承継」だということを、再認識しました。私は譲渡対価よりも、トライアンフの企業文化を理解し、さらに発展させてくれる相手を見つけることに注力しました。準備から1年ほどで、最適と思えるパートナーとめぐり合えたことは、極めて幸運です。
その後のM&Aのプロセスでは、「信頼できるアドバイザー」の存在も非常に重要だと感じました。どのような良縁に恵まれたとしても、取引を完結させるには、経験豊富なアドバイザーによる顧客目線の支援がなくては成り立たないでしょう。
M&Aを決断するのは経営者ですが、従業員や取引先、パートナー企業など、多くの方々の人生に影響が及びます。一度きりの決断に向けては、相性をとことん見極めるしかありません。
最後にこうしてお客様に喜んでいただけたことが、私たちにとっても何よりの喜びです。運命的と言っていただけるような出会いを生み出し、M&Aをご支援させていただいたことはとてもありがたく、貴重な機会だったと感謝しております。

(左から)弊社大竹、樋口様
文:蒲原 雄介 写真:佐久間 ナオヒト 取材日:2024/7/2
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。