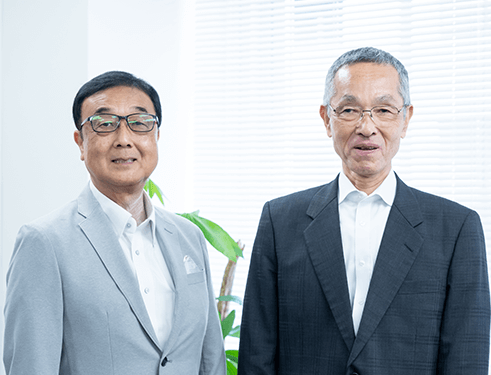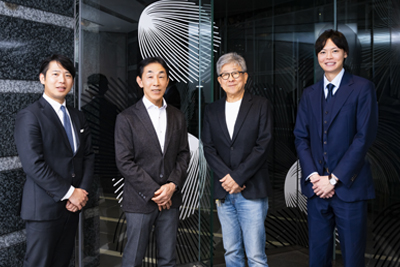信頼できるパートナーを最適なタイミングで選べた
公共広告のパイオニアが選んだ次なる一手
株式会社郵宣協会は、1992年の創業以来、郵便局や自治体の公共スペースを活用した広告事業を展開してきた。全国20,000以上の郵便局と約500の自治体に実績を持つ業界のパイオニアだが、2024年12月に株式会社フジテックスとの資本業務提携を発表。創業から30年以上にわたって、組織の成長をリードしてきた村上左一郎社長に、資本業務提携に至るまでの経緯、今後の展望をお聞きした。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社郵宣協会
- 所在地
- 福岡県北九州市
- 設立
- 1993年
- 事業内容
- 郵便局広告取扱[郵便局広告 指定代理店]、自治体広告取扱、印刷・デザイン制作関連事業、WEB制作関連事業
- 資本金
- 1,000万円
- M&Aの検討理由
- 後継者不在のため
-
譲受企業
- 会社名
- 株式会社フジテックス
(ジャフコ グループ株式会社投資先) - 所在地
- 東京都中野区
- 設立
- 1978年
- 事業内容
- 総合商社
- 資本金
- 3億円
- M&Aの検討理由
- 広告事業への参入のため
タブーとされていた郵便局や自治体への広告の道を切り拓く
創業の経緯および現在の事業概要を教えていただけますか。

郵宣協会は、郵便局や自治体の施設に設置する広告を得意とし、企画・制作を行っています。広告主のニーズにあわせて、郵便局が使用している現金封筒への広告やデジタルサイネージを活用した広告、自治体で使用している窓口用封筒、婚姻届、出生届への広告など様々な商品を扱ってきました。公共性の高い場からの広告発信は企業と消費者を強く結びつけると同時に、広告モデルによって公共施設の設備充実にも貢献できるのが特徴だと言えます。
どのような経緯で会社を創業したのでしょうか。
大学卒業後はアパレルメーカーなどで主に営業を担当していました。当時から、いつか自分の会社を持ちたいと思っていたのですが、親戚が運営する協同組合の手伝いを求められたことが大きな転機となりました。やがては経営により近い立場で仕事ができると誘われたことで、将来独立する近道になるかもしれないと思い、飛び込む決心をしたのです。
それまで高額だった市外通話を格安で提供する事業者を組合員に対して紹介することが主な業務内容でした。毎日のように中小企業の経営者と接する機会があっただけでなく、同僚にも私と同じようにいずれは独立を目指す志を持った仲間が集まる刺激的な環境でした。
そこで偶然、出会ったのが郵便局の広告事業を手がける会社です。その社長が、我々の組合員に対して広告の提案をしたいという話を進めていたのですが、不動産投資に失敗して社長とは音信不通になってしまいました。
一度は協同組合が主体となって事業を引き継ぐことでまとまりましたが、この機会をビジネスチャンスとして捉えた私は、独立創業を申し出たのです。すでに1000を超える既存顧客もあったので、ゼロから始めるよりはよほど有利だという目論見もありました。ところが実際に会社を立ち上げると、その引き継ぐ会社の債権問題から既存顧客には手をつけられないことが判明しました。一気呵成に営業活動しようと、スタッフを5人も雇用した後だったので、さすがに焦りました。
厳しいスタートから逆転して、どのように事業を伸ばしたのですか。

ようやく軌道に乗ったと思えるまでには、10年ほどかかったでしょうか。キャッシュフローが安定せず、胃の痛む日々を送っていたものです。
転機を迎えたのは、創業から3〜4年が経ち自治体広告という新しい分野に挑戦した頃のことです。今でこそ、市役所などの封筒に広告が印刷されていることは当たり前になりましたが、当時は自治体の施設や印刷物での民間企業の広告はタブーとされていました。
必死の思いで私の生まれ故郷である大分県日田市を口説いて、初めての導入が決まりました。最初は難しい反面、公的な機関は前例があると、右に倣えで真似をする傾向にあります。広告収入によって厳しい財政が少しでも潤うと聞けば、多くの自治体には魅力的な提案だったのです。そしてこうした公的なスペースに広告を出すことは、企業側にとってもブランド力の向上につながります。郵便局広告と自治体広告という事業の柱ができたことで、売上が徐々に安定してきました。
順調に事業は伸びるも将来的にはM&Aが最適だと知る
その後、会社は順調に成長したとお聞きしています。何が要因だったとお考えですか。
気が付けば顧客数は6,000社に伸び、全国の郵便局や数百もの自治体へ広告を案内できる組織となりました。その理由を一つに絞って答えるのは難しいですが、私自身の経営姿勢が変化したことも大きかったように思います。安定軌道に乗るまでは社員にも厳しく接していたため、結果として人材が定着することもありませんでした。しかし、誠実に自分の仕事と向き合い、顧客のために全力を尽くし続ける彼らの姿を見て、自然と心からの尊敬や感謝の思いが芽生えるようになったのです。
社内の雰囲気がいいというのは、M&Aキャピタルパートナーズの宮島さんにもたびたび言っていただいています。

初めてオフィスにお伺いしたときから、いつも明るい雰囲気で迎えていただいて良い印象しかありませんでした。社長のほかに従業員の方々ともお話しをしましたが、皆さん一様に村上様のことを慕っていて、尊敬している様子が伝わってきました。これまで拝見してきた企業の中でも、雰囲気の良さはトップクラスだと思います。
あるとき、村上様にどうすればこうした風通しのよい空気が醸成できるのかお尋ねしたことがあります。そこで「社員を信じて、任せてきたからだと思う」とおっしゃいました。とても印象に残る一言でした。
経営が順調だったのに、なぜM&Aに関心を持たれたのでしょう。
10年ほど前、私も40代半ばに差し掛かると、経営者仲間からも将来どうするつもりなのかと尋ねられる機会が増えてきました。私には3人の娘がいますが、子どもたちには自分の人生を歩んでほしいと思っており、無理に継がせる意志は一切ありませんでしたので、自然と従業員の中から後継者を選ぶのだろうと漠然と考えていました。
しかし、行政が主催したM&Aに関するセミナーに参加して、従業員の承継も簡単ではないことを学んだのです。株式の譲渡や税金に関する問題もありますし、会社に債務があればその借金も継いでもらうことになります。そこでようやく初めてM&Aという選択肢が私にとってはベストなのではないかと考えるようになりました。ただ、すぐに具体的な検討に入ったわけではありません。M&A仲介会社と複数お会いして、企業価値の評価は聞きましたが、まだ私の中に話を進めたいという思いが芽生えていなかったからです。
やや時期を置いてから、M&Aキャピタルパートナーズは初めて面談の機会をいただきました。
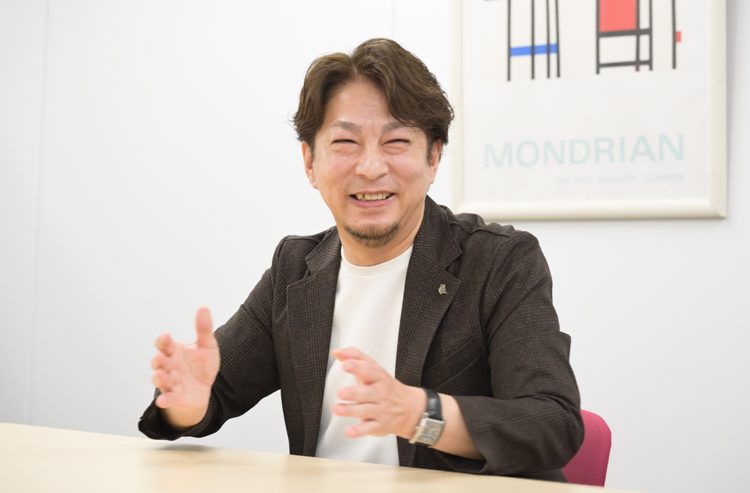
ちょうどM&Aキャピタルパートナーズからお手紙が届き、直後に電話をいただいたのが、宮島さんとお会いするきっかけとなりました。最初の仲介会社との面会からは2年ほど経過し、私も50歳を過ぎてそろそろ将来について考えないといけないと思い始めていた時期だったので絶妙なタイミングでした。
宮島さんは初めてお会いしたときから、どのような質問をしても的確に回答してくれ、知識も豊富なうえに説明も非常に分かりやすくて、安心感がありました。企業価値の算定から始まり、M&Aの仕組みのことなど、様々な情報を提供してくれたことからもクレバーな方だという好印象を持っていました。さらに2~3か月に一度は定期的に訪問してくれたり、連絡をしてくれたりという熱心さもあわせ持っているのが魅力ですね。徐々に信頼関係が深まり、家族の話や個人的な話も共有するようになりました。娘がやっているカフェに一緒に行くなど、本当に何でも話せる関係になりました。
最初にお会いした時から、私は村上様の人柄に惹きつけられました。初対面の時点では従業員の方々の社長評をお聞きする前でしたが、フランクで丁寧に対応してくださるその姿勢に感銘したことをよく覚えております。
M&A仲介の営業職の中には、うわべだけの調子のいい言葉を並べる人もいます。しかし、口先だけと感じた瞬間にあらゆる言葉が心の底からは信じられなくなってしまいます。私は取引先でも社員でも、いいものはいい、ダメなものはダメとはっきり言ってくれる人を信頼しますが、宮島さんはまさにこのタイプでしたね。
信頼できるパートナーが導いたシナジーを予感させる出会い
今回の成約に至るまで村上様のお気持ちはどのように変わったのでしょうか。

企業価値の算定をしてもらったあと、相手先について何社か候補の紹介を受けました。ただ当時は、まだまだ会社が成長を続けていて自分たちだけの力でどこまで伸ばせるか試したい気持ちがあったのも事実で、決めかねていた時期が数年間続いていたというのが正直なところです。
村上様は将来的にはM&Aがベストな選択肢だと思っていらっしゃったので、まずは候補先となる企業へこちらの社名を伏せた状態、いわゆるノンネームで打診をしました。興味を示した企業もありましたが、社名を開示する段階に進むことには村上様が躊躇されているように感じていました。ご自身も時期尚早だと感じていらっしゃったようでしたし、ご勇退を目的とした場合、50代前半という年齢は一般的にまだ早いと言われるかと思います。
実際に私がお会いしているその数年間にも、売上は継続的に伸びていましたし、私どもから無理にM&Aをおすすめすることはありません。事業承継という観点だけではなく、成長戦略のひとつになり得るか、広告業界のM&A動向など様々な情報をご提供していました。
宮島さんの決して急かさずに、変わらないスタンスで接してくれたことには感謝しています。ただし「自力で成長を続けているからM&Aは必要ない」という考え方も絶対ではないと気づくようになったのです。もし、会社が落ち目になった後では条件も悪くなり、選択肢も狭まるでしょう。M&Aは、困ったときの最後の手段ではなく、成長をさらに加速させるための戦略的選択だと理解できました。だからこそ、ベストな決断のタイミングは、会社が成長過程にあるときだと知ることができたのは結果的に大きかったと思います。
複数の選択肢からどのように絞り込まれたのでしょうか。
M&Aの相手先候補として事業会社や投資ファンドなど複数社を比較検討しました。その中で最終的にフジテックスを選んだ背景には不思議なご縁がありました。
最初の面談で、取締役の角田さん(株式会社フジテックス 取締役 角田 斉 様)から「事業構想大学院大学で何を構想しましたか」と質問されて、私は大いに驚きました。数年前、私は同学の福岡校に通っていた時期がありました。事業アイデアの根本から発想し、郵宣協会をさらに飛躍させるためのヒントを得たいと考えたからです。実は、事業構想大学を設立したのはフジテックスの創業者である東理事長で、角田さんも社長の一森さんも通われていたことがあるという共通点を初めて知りました。しかも角田さんは、北九州にある大学の出身でもあり、強い親近感を覚えました。
事業のシナジーという点でも大きな可能性を感じました。商社であるフジテックスは、大学やドラッグストアといった、私たちが持っていない新たな広告媒体になり得るパイプを多く持っていました。また、販促物の商品も多く取り扱っているので、私たちの既存のお客様に対して広告以外の新たなPR手段を提案するうえでもすぐプラスになると感じました。
事業内容の相性として、商社と私たちのような広告業とはバッティングしないので、M&A後も互いの独自性を保ちやすいのも魅力です。これが同業種だと、方法論を押しつけられてしまい、社内の風土が変わってしまったという話も聞いたことがあります。それでは、M&Aのシナジーは発揮されず、むしろ逆効果になってしまいます。

村上様とフジテックスの方々の間には、初めて会ったとは思えないような和やかな雰囲気がありました。直感的な話にはなりますが、両者の顔合わせでこのように話が弾むケースは、その後もうまくいく確率が高いように感じていました。特にフジテックス側が、事前に村上様や郵宣協会に対して一際強い関心をお持ちだったことが、大学のエピソードからも明らかでしたね。
当社の独立性を保つという点で、投資ファンドからのご提案も魅力的に感じていましたが、投資ファンドの特性上、数年後に再び同じようなプロセスを繰り返さなくてはなりません。しかしフジテックスという事業会社なら、一度の決断で長期的な安定が見込めると考えたのも決め手になりました。
払拭された不安。新たな全国展開という目標に向かって
成約まで不安や心配はありませんでしたか。
デューデリジェンス(企業監査)など一連の手続きは、そこまで大変ではなかったんです。宮島さんが先回りしてくれて、公認会計士とも必要な連携を取ってくれたので、安心感はありました。サポートがなければ、正直、この複雑なプロセスを乗り切ることはできなかったと思います。M&Aというと、経営者側に多大な労力がかかるイメージがあるかもしれませんが、私の場合はプロフェッショナルの支援のおかげで、本業に集中しながら進めることができました。
一方、従業員が不安に思うのではないかという点は、大きな懸念事項でした。ここでも宮島さんのアドバイスをもとに、従業員への丁寧な説明を行いました。今までと体制に変更はないこと、資本が加わることでより安心できる状態で働けることを伝え、フジテックスの幹部にも来てもらい説明会を実施したのです。
結果として、従業員の理解が深まり、むしろ意識が高まる効果もあったように感じています。
無事に成約を迎えての感想をお聞かせください。
肩の荷が下りたというより、むしろ責任が増したと感じています。フジテックスの一員として、足を引っ張るわけにはいきません。郵宣協会の、今後の展望としては、全国展開を視野に入れています。これまでは資本や人的なリソースの課題から、西日本や中四国、東北・北海道に限定して展開していましたが、今後は関東、関西、中部といった都市部での営業を強化します。フジテックスというバックボーンを活かせば、十分に可能だと思っています。
村上様はもちろん両社の成長発展や従業員の方々にとって大切なお話しにかかわる緊張感と喜びがありましたが、それ以上に人柄が素晴らしく心から尊敬している村上様と一緒に仕事ができて「楽しかった」という思いがあります。村上様がお話しされたように、これからの両社の成長発展が非常に楽しみです。
今後M&Aを検討する経営者に向けたメッセージをお願いします。
まだまだM&Aは乗っ取り行為だという先入観が染みついている経営者もいるかもしれません。今でも親族内承継がセオリーのように思われがちですが、それが経営者、後継者の双方にとって本当に幸せなのか考えてほしいと思います。子どもたちに意思があれば良いですが、そうでない場合も多いでしょう。M&Aという選択肢について正しく理解することが大切です。
すでに知り合いから、自分たちもM&Aを選択すればよかったと言われたこともあります。いきなり選択肢から外すのではなく、会社の継続的な発展と従業員の幸せを考えたM&Aは十分に価値のある選択肢と言えるように思います。

文:蒲原 雄介 取材日:2025/3/25
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。