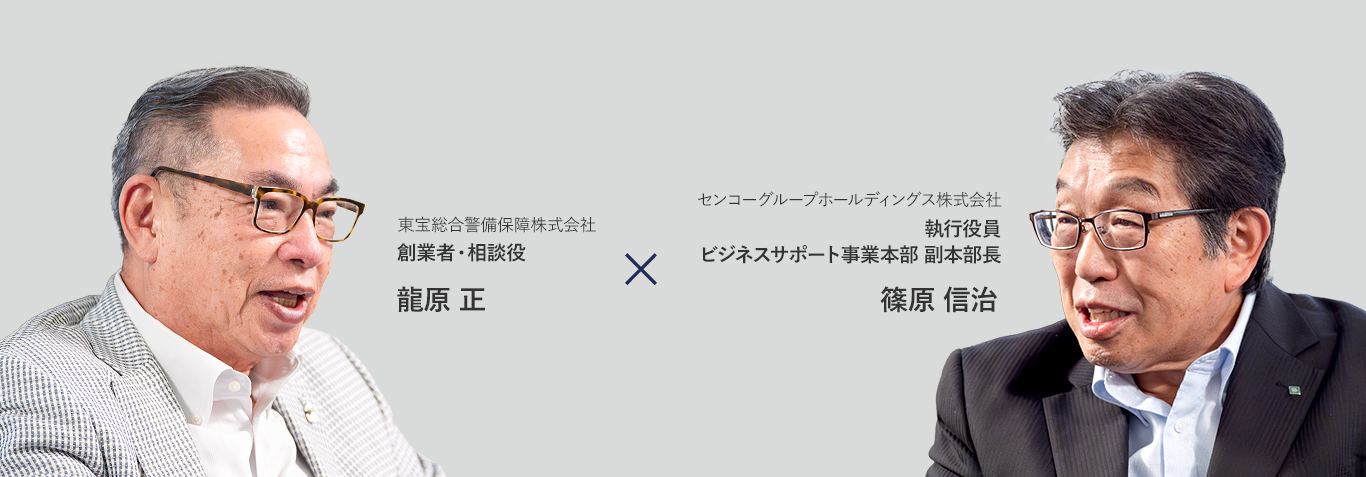
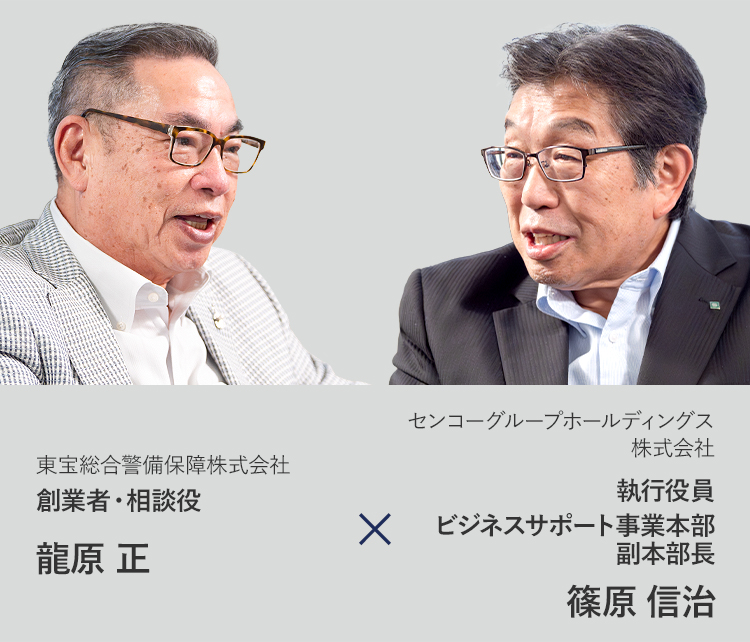
街の安全を守り続けて48年。
積み重ねた信頼を次世代へつなぐ創業者の決断
1978年の創業以来、渋谷を拠点に警備業を営んできた東宝総合警備保障株式会社。創業者の龍原正氏が後継者問題に直面する中、物流大手のセンコーグループホールディングス株式会社への株式譲渡を決断した。異業種のセンコーグループへの株式譲渡の背景には、龍原氏とM&Aキャピタルパートナーズ竹内謙太氏との7年にわたる信頼関係があった。譲渡側の東宝総合警備保障株式会社の創業者である龍原正様、譲受側のセンコーグループホールディングス株式会社の篠原信治様に、今回の経緯と将来展望を伺った。
-
譲渡企業
- 会社名
- 東宝総合警備保障株式会社
- 所在地
- 東京都渋谷区
- 設立
- 1978年
- 資本金
- 4,500万円
- 事業内容
- 各種施設、工事現場等の保安・防災・交通誘導業務、イベントの安全管理業務などの総合警備業
- M&Aの検討理由
- 後継者不在のため
-
譲受企業
- 会社名
- センコーグループホールディングス
株式会社 - 所在地
- 東京都江東区
- 設立
- 1946年
- 資本金
- 394億8,300万円
- 事業内容
- 物流事業を中核に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート等を展開
- M&Aの検討理由
- 事業領域の拡大のため
友人の言葉で踏み出した警備会社の第一歩。渋谷の街とともに発展を遂げた
警備業を創業された経緯についてお聞かせください。

私は九州の出身で、21歳の時に東京に出てきました。最初は広告会社に就職しましたが、人間関係、特に上下関係というものが苦手でした。数年ほどは試行錯誤しましたが、自ら退職を選んだときには、自分で起業するしか道は残されていません。そこで1975年、渋谷で広告代理店のような仕事を始めましたが、その後すぐに警備業へと転身することになりました。そのきっかけをくれたのは、学生時代に警備のアルバイトをしていた友人の話でした。彼が「警備業は将来絶対に伸びる。安心安全を売る商売だから、今の日本ではまだ普及していないが、今後必要になるのは間違いない」と言うのです。その言葉が非常に印象的だったので、信じてやってみることにしました。私自身には警備の経験が全くありませんでしたが、これが東宝総合警備保障の始まりです。
一口に警備といっても施設警備、交通誘導や雑踏の警備、貴重品運搬、身辺警備などと細分化されます。創業時に選んだのは業界では2号警備と言われる、建設現場での交通誘導警備でした。この分野が、最も参入障壁が低いと判断したためです。主流とされた施設警備は、大手警備会社が強く、資本力がない状態での新規参入は困難でした。交通誘導警備は建設現場の工事が始まる時点で新規に警備会社を選定されるため、新築ビルの工事の情報をつかめばすぐ営業活動ができます。渋谷の街は、まさに開発ラッシュを迎えており、建設現場がたくさんありました。こうした現場を取り仕切るゼネコンから、警備の仕事をもらおうと考えたのです。実際に当社の第一号案件は、渋谷駅前にあり、今も街の顔として残る大型商業ビルの建設現場でした。当時、3名から5名程度の警備員でスタートし、私自身もヘルメットをかぶって現場に立っていました。仕事をこなすのに必死でしたが、建設現場にはまだまだ警備の手が足りません。これは事業拡大のチャンスが目の前に転がっていると感じました。
警備員の人材集めはどのように行ったのでしょう。

求人はアルバイトニュースという紙媒体に掲載し、学生を中心に比較的容易に人を集められました。しかし、問題は教育です。法令で定められた教育は3日間ほど必要でしたが、本当の意味で、安心や安全を守るには全く不十分だと感じていました。実は私自身、教育されるのは大嫌いなタイプですが、だからこそ教育によって警備員たちのレベルを引き上げることの重要性はわかっていたつもりです。
顧客企業の信頼を得るためには、徹底した教育しかないと考え、独自のカリキュラムを作りました。法令教育はもちろん、建設現場特有の知識も教えますし、駅舎特有の注意点、ビルならではの気を付けるべきポイントなどを教えるのです。それぞれの現場に応じた教育を実施しました。最も重視したのは、歩行者への対応です。笑顔での挨拶、声かけの仕方など言葉選びで、相手が気持ちよく止まってくれるかどうかが変わります。大きな声で、はっきりと、そして笑顔で対応することを徹底的に叩き込みました。本来、私たちに車や通行人を止める権限はありません。だからこそ、笑顔と感謝を欠かしません。これが警備の原点だと考えています。
顧客は建設会社ですが、その先にいる一般の通行客のことを考えたのですね。
そうした姿勢を認めていただき、大手ゼネコンの新幹線駅舎建設や地下鉄工事など、大型案件を任されるようになりました。そして、繰り返し我々を指名してもらえるようにもなりました。こうした実績が呼び水となり、さまざまな大型インフラ工事の警備も受注し、現在では、渋谷の開発案件の約8割は東宝総合警備保障が手がけています。渋谷の街を見渡せば、ほとんどのビルの建設に私たちが関わってきたと言っても過言ではありません。しかし、私が最も誇りに思っているのは、地域住民の方々から多数のお礼状をいただくようになったことです。ある現場で、多数の車両が通る道路が通学路になっていました。のちに保護者から「安心して子どもを通わせられるのは警備員さんのおかげ」という感謝の手紙をいただきました。建設現場の警備員に対し、こうした言葉をいただけるのは、稀なことだと自負しています。私たちの本当のお客様は歩行者であり、地域住民の方々だと徹底してきました。
独自のサービス開発にも取り組まれてこられましたが、女性警備員の活用はその好例ではないでしょうか。
ある時、客室乗務員を退職した方が数名、私たちとともに働いてくれることになったという偶然から生まれたサービスでした。話を聞くと、子育てのために退職せざるを得なかったり、数年間限定で働きたいといったり、それぞれの事情がありました。そんな話をしているうち、航空機と地上の安全を融合させたら面白いのではないかとひらめいたのです。客室乗務員といえば接遇のプロであると同時に、空の安全を守る教育を受けてきた人材です。
そこで生まれたのが、女性警備員のチームで、これが非常に評判となりました。女性ならではの、細やかな対応が求められる現場で活躍してもらう方針を採用したためです。受付業務と巡回を組み合わせたり、データセンターを警備したりするなど、体力や腕力が重視されない場所というのがあります。さらに派遣業の許可も取得し、警備だけでなく派遣という形でも女性の活躍の場を広げていきました。
さらに私たちは、盗聴や盗撮に悩む方たちをサポートするサービスも手がけています。若い女性がストーカー被害に遭い、部屋に盗聴器が仕掛けられているのではないかという不安を抱えるケースが増えています。それを専用の機械を使って調査するのですが、ここでも男性だけでなく、必ず女性の調査員を向かわせるようにして、依頼者の不安を和らげるようにつとめてきました。実際には、ほぼ盗聴器などは見つかりません。ただ、仕掛けられていないという事実を確認できただけで、お客様に安心を届けることができます。
コロナ禍で気づかされた経営者としての責任
ここまで育て上げてこられた会社についてM&Aを選択したのはなぜだったのでしょうか。
一番の理由は、後継者が不在だったことです。60代の後半に入った頃から、漠然と承継について考え始めました。社内の人に継がせるのか、外部から招聘するのか、いろいろな選択肢を検討しました。しかし、改めて警備業の経営というのは本当に大変な仕事です。24時間365日気が抜けず、たとえ深夜でも何かあれば電話が鳴ります。
創業から48年間、私はずっと社長として、創業者としてすべての責任を負う覚悟で、張り詰めながら生活を続けてきました。このような重責を誰かに任せ、引き継ぐことができるかを考えると、大抵の人は躊躇し、逃げ出すと思います。だから、後継者問題になかなか答えは出ませんでした。そこに追い打ちをかけるように、コロナ禍がありました。同年代の元気だった友人が急に亡くなることも、年齢とともに少しずつ増えてしまいます。こうした現実を目の当たりにすると、自分自身にも明日何が起こってもおかしくないのだと感じずにはいられませんでした。
もし私が後継者を決めずに何かあったら、従業員はどうなるのか。会社はどうなるのか。これは、経営者として無責任なのではないかと思うようになりました。
龍原様とM&Aキャピタルパートナーズとの出会いについて教えてください。
M&A仲介会社からの手紙は大げさでなく山となるほどで、うんざりするくらいのアプローチがありました。一度だけでも会ってほしい、話だけでも聞いてほしいというメールや電話も毎日のように来ていました。しかし、会ったとしても自社の実績をアピールするばかりであまり面白くありません。その中でM&Aキャピタルパートナーズの竹内さんの姿勢だけが違っていました。
押し付けがましさがなく、こちらを焦らせるようなことも言いません。定期的に業界内のM&Aに関する情報だけを提供してくれるのです。その姿勢が新鮮で、この人は信頼できるなと感じていました。

龍原様と初めてお目にかかったのは、もう7年前のことです。東京五輪を見据えた建設ラッシュが続き、会社の業績も非常に好調なご様子だったため、龍原様に譲渡の意思がないのは、承知していました。ただ、よい会社であるがゆえ、株式の譲渡なども含めた承継課題があるとはお聞きしていたので、お時間をいただくたびに情報提供は続けさせていただきました。龍原様が本格的にM&Aを検討され始めたのは、2年前です。コロナ禍を経て、承継の緊急性を強く意識されるようになったと仰っていました。
実は心の中では「M&Aを選ぶ時期が来たら、パートナーは竹内さんしかいない」と決めていたのです。7年間も付き合ってくれていたと聞き、そんなに時間が経過したのかと驚きましたが、その間に彼の熱心さと誠実さをよく理解していました。竹内さんは、リスクについても包み隠さず話してくれ、良いことばかりではなく、M&Aの留意点もきちんと説明してくれます。そうした姿勢を信頼していました。
身に余るお言葉をありがとうございます。具体的な検討フェーズに入る際に、龍原様はいくつかの条件を明確におっしゃっていて、その一つが同業者は避けたいというものでした。将来的な従業員の待遇面で、不安があることを気にされていました。

私が最も重視していたのは、従業員の将来です。同業他社、誰もが知るような大手警備会社からもアプローチを受けたことがありましたし、たしかに大手なら待遇は良いかもしれません。しかしさらに先を見据えると、機械警備が中心の大手企業と、人的警備を中心とする我々では、方向性が違います。大切な人材が幸せになれるとは限らないと判断したのです。
そこで異業種でも警備業にシナジーを見出せる企業で、渋谷の地で築き上げたお客様との関係性や若者が集まる渋谷での人材採用を継続することも条件に入れました。社名や役員、従業員の待遇を維持することとして、給与や役職、働く環境も変えないでほしいということも伝えました。
龍原様のご意向を踏まえて、同業他社は少し絞りつつも、異業種の企業中心に幅広くご紹介することとしました。何社からも手はあがりましたが、その中でセンコーグループが非常に積極的だったのは印象に残っています。以前から、首都圏の警備業を強化したいという強いご意向もいただいていた経緯があったので、一層強い熱意となって現れたのだと感じました。
物流業と警備業、共通点と強みの補完関係が成長戦略を生み出す
センコーグループの事業概要、そして警備業に関心を持った理由を教えていただけますか。

センコーグループは物流を中核事業とする企業グループで、物流のほかにも貿易事業、ライフサポート事業、そしてビジネスサポート事業と4つの事業領域を行っています。私自身は、物流の現場から始まり、人事、建築業などと広範な事業に携わってきました。7年ほど前からは人材派遣事業を担当し、その中で警備業にも参入することとなった次第です。
警備業を選んだ理由は、物流と警備にはいくつかの共通点があると感じたためです。どちらも労働集約産業であり、中小企業が多く、後継者問題を抱えています。そして人手不足にも悩んでいるため、逆に捉えれば人さえ集めれば事業を拡大しやすいという特徴もあります。
これまで3社の警備会社をM&Aによってグループへ迎え入れてきました。自分たち自身で運営する中で、この業界の可能性を確信しました。そして東宝総合警備保障は、都内でも有数の実績と、組織体制を持っている企業です。特に顧客リストを拝見すると、そうそうたる大手企業名が並んでおり、簡単には築けない資産がありました。だからこそ、私たちの警備事業の中核になる存在として、ぜひ迎え入れたいと考えたのです。
初めて両者がお会いした時の印象はいかがでしたか。

失礼ながらお会いする前は、警備業と物流業は畑違いなので、あまり期待していませんでした。会社名は高速道路でトラックをよく見かけるので知っていた程度です。ところが、篠原さんとお会いして、その考えが完全に変わりました。30分間、一人でプレゼンテーションをされましたが、私たちの会社と警備業界のことを本当によく調べて作りこまれた提案資料を使って、今後の警備事業の発展プランを具体的に熱く語ってくださいました。そして「東宝を核にしたい」という言葉に、本気度を感じたのです。すでに警備会社を3社迎え入れているのに、私たちが築いてきた顧客基盤と組織力を高く評価してくださいました。そして、私が出した従業員の待遇などの条件もすべてその場で受け入れを即答されたことには驚きました。
言うまでもなく、それだけ思い入れが強かったからです。私たちが抱えている課題と、東宝総合警備保障の持っている強みが、見事に補完関係にあると感じました。私たちには人材を集めるだけの力がありますし、物流で培った外国人技能実習生を育成するノウハウもあります。そして、東宝総合警備保障には顧客基盤に加えて、龍原さんが48年間培ってきた信頼があります。直接お会いした際にも、こうしたすばらしいリーダーが率いてきたからこれだけの組織ができたことはすぐに確信しました。
成長性はあるが採算性はまだ高くないながらも、社会的な意義を感じ続けてきた盗聴・盗撮発見サービスの話もしました。普通なら不採算事業には反対されてもおかしくありません。しかし、篠原さんたちは「社会貢献として素晴らしい」と共感してくださいました。その時に、信頼できる方たちだと思いました。
それでもさすがに即決できたわけではありません。48年間育ててきた会社ですから、簡単に最終結論は出せませんでした。他の会社とお会いして、条件面も含め比較検討したのも事実です。ただ初回面談の時点で、私の中で直感は働いていました。最終的には、本当に従業員のためになるか、会社の将来にとって最善の選択と言えるか。やはり従業員を大切にし、会社を伸ばすと言う篠原さんの言葉は単なる口約束ではなく、具体的な計画とともに示されたものだったと信用したいという気持ちが強くなっていきました。
龍原様は、他の企業からも好条件が提示され慎重に検討を重ねていたと思います。ですが、センコーグループとの打ち合わせを重ねるごとに、表情が明るくなっていらっしゃるのもわかりました。ようやく安心して任せられる相手が見つかったという安堵感があったのではないでしょうか。
交渉を進める中で苦労された点はありますか。

やはり48年分の書類整理は大変でした。デューデリジェンス(企業監査)で上場企業の基準に合わせるため、必要書類の多さを示されて、愕然としたのは事実です。昔の書類を引っ張り出して、一つずつ確認するといっても、記憶力も衰えてきていますから、途方もない作業でした。でも、竹内さんが全面的にサポートしてくれて、丁寧に1つずつ解決に導いてくれました。
デューデリジェンスで創業期の書類などを発掘するのは大変だった部分はあります。しかし、双方が常に前向きに、また真摯に対応してくださったのが大きかったと思います。要求水準は決して低くありませんでしたが、上場企業としては当然の務めという点もありました。私ができることはすべてサポートしたいと思っていました。
さまざまなご苦労、ご負担をかけてしまったかと思います。ただ、デューデリジェンスを進めてみると、感心させられることも多くありました。独自の教育メソッドもその一つです。こうしたバックボーンなら間違いなく、私たちグループの中核企業として成長できると感じました。
また竹内さんは両者の間に立って、バランスの取れた対応をしてくれました。売り手・買い手双方の立場を理解して、丁寧に調整してくれたこと、私たちが強い関心を持っていることを龍原さんにしっかり伝え、さらに龍原さんの要望も私たちに的確に伝えてくれました。このコミュニケーションの質の高さは、スムーズな成約につながったと思っています。
売上100億円への挑戦——規模の力で変える警備業界の未来
今後の展望についてお聞かせください。

東宝総合警備保障を含めたことで、センコーグループの警備事業の売上は約50億円になりました。これを5年以内に、100億円まで高めることを目指します。100億円を超えると、業界内でのランキングでも20位以内に入り、存在感が大きく変わります。価格決定力も持てるようになるはずです。そして将来的には200億円を達成し、トップ10入りも視野に入れています。その頃には、機械警備にも参入できるかもしれません。グループが持つ物流施設やマンションなども、機械警備の対象になりえます。
最大のカギは人材確保ですが、外国人技能実習生の活用も検討しています。私たちは、物流業界での技能実習生制度の導入に携わってきました。警備業界でも近い将来、認められる可能性があると考えています。
ネパールやインドネシアといった国々の若者たちは、年収水準が日本の10分の1程度です。そのため、月に20万円稼げれば、本国の家族に十分な仕送りができます。すぐに実現できるわけではありませんが、警備業界団体との調整をはじめ、様々なハードルを乗り越えていきたいと考えています。人手不足が深刻化する中で、新しい選択肢を模索すること自体が重要です。
警備の需要は今後も減ることは想定しづらく、むしろ増えていくと思います。安全安心に対する社会の要求は、年々高まっています。たとえば、大規模な花火大会や新幹線を思い浮かべてください。これらの警備員の数は何倍にも増えました。何か事件や事故があると、警備を強化してほしいという声が上がるのは、必然的な流れです。
一方で、働き手は減っています。生産年齢人口は、15年後には今の4分の3になると言われています。この矛盾をどう解決するかが、警備業界全体の課題です。

だからこそ、規模の拡大が重要だと考えています。人さえ集まれば、仕事はついてくる。これが警備業界の特徴です。何もしなければ、少ない人材を奪い合うだけになってしまい、小さな存在は大きな存在の前に淘汰されるでしょう。グループには、人材採用のノウハウや人材確保の手法が豊富にあります。このノウハウを警備業に応用すること、そしてグループ内で人材の融通を利かせるなど、フル活用することで人材不足の解決につなげていく狙いです。
業務の効率化も進めなくてはなりません。今なお業界の多くで、電話での勤務調整のやり取りをしています。その労力は、スマートフォンのアプリで代替が可能です。勤怠管理も請求書作成も、まだまだデジタル化する余地が残されています。こうした効率化によって、限られた人材でも、より多くの現場をカバーできるようになるのは間違いありません。
従業員の方々の反応はいかがでしたか。
M&Aの成約前は伝える人を限定しなくてはならず、発表前に詳しい説明を行う時間が限られていました。しかし、発表されたあとの従業員の表情を観察していると、不安よりも期待の方が大きいように感じられます。より大きな組織の一員となることで、安定性が増し、福利厚生も充実し、将来への不安が減る可能性についても説明しました。センコーグループの一員になる意味を、皆が理解してくれている手応えは感じています。
そしてこれからも渋谷を中心に東宝総合警備保障として頑張ってほしいと伝えました。会社の名前も場所も変わりません。ただ、背後には大きな組織がついてくれているという事実が一番重要なことであり、私は彼らにとって最良の選択をできたと今では思っています。
私たちは従業員の皆さんに、雇用と待遇を守るだけでなく、より良い環境を提供すると約束しました。上場企業の一員となり、社会保険も100%加入で、退職金制度も整っています。警備業界では、必ずしも当たり前ではなかったことが、これから当たり前になるかもしれません。さらに仲間となる警備会社を迎え入れ、強固な基盤づくりに注力していきます。
M&Aを検討している経営者へメッセージをお願いします。
早めに相談することが大切なのではないでしょうか。私はまだその気がなかった時点から竹内さんと情報交換をしていたからこそ、いざ決心した時にスムーズな選択ができました。多くの経営者がまだ大丈夫、もう少し自力で頑張れると思っているのではないでしょうか。しかし気づかないうちに、タイミングを逸してしまうのです。私もコロナ禍を経験したことで、それまでいかにのんびりしていたかを痛感しました。残りの時間は誰にも分からないのです。
M&Aは売却ではなく、バトンタッチだと思います。自分が築いてきたものを、より大きく発展させてくれる人に託すつもりで、従業員や取引先のことを念頭に置いて前向きな心で向き合えば、良い結果は得やすいと思います。
この業界に限らず、人手不足や後継者不足に悩む経営者の方々は、悩む前にぜひ相談していただきたいです。私たちのように出身が異業種でも、シナジーを生み出せるかもしれません。人手が集められればビジネスは伸ばせるという業界なら、私たちの採用力や経営管理ノウハウは活かせます。規模を拡大することで、価格決定力も持てるようになり、従業員の待遇も改善できます。
初めて龍原様にお会いしてから7年間という長い年月を経ただけに、個人としても感慨深いものがあります。そして、センコーグループという物流大手企業が描く警備業界での新たな挑戦を支援できたのも、M&Aアドバイザーとして本当に光栄なことです。両社の価値観が見事に合致し、初回の面談から具体的なシナジーの話ができたことも印象に残っています。M&Aは企業文化や理念の融合が重要だと改めて実感しました。良い会社であるがゆえの悩みを抱えている経営者の方は多いと思います。私たちM&Aキャピタルパートナーズは、そうした経営者の方々に寄り添い、最適な選択を見つけるお手伝いをさせていただきます。
竹内さんの言葉どおり、センコーグループの一員となった東宝総合警備保障が、業界のモデルケースとなることを願っています。渋谷の街の歴史とともに歩み、新たなステージで更なる発展を遂げ、従業員たちが誇りを持って働ける会社であり続けること。それが私の願いです。

文:蒲原 雄介 写真:松本 岳治 取材日:2025/7/24
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。











