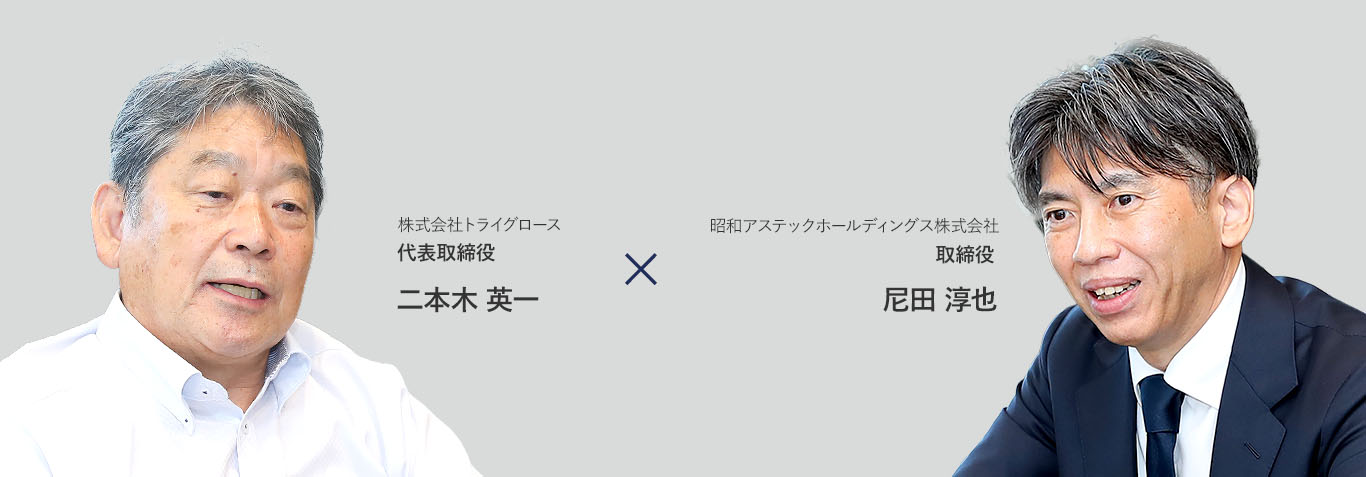
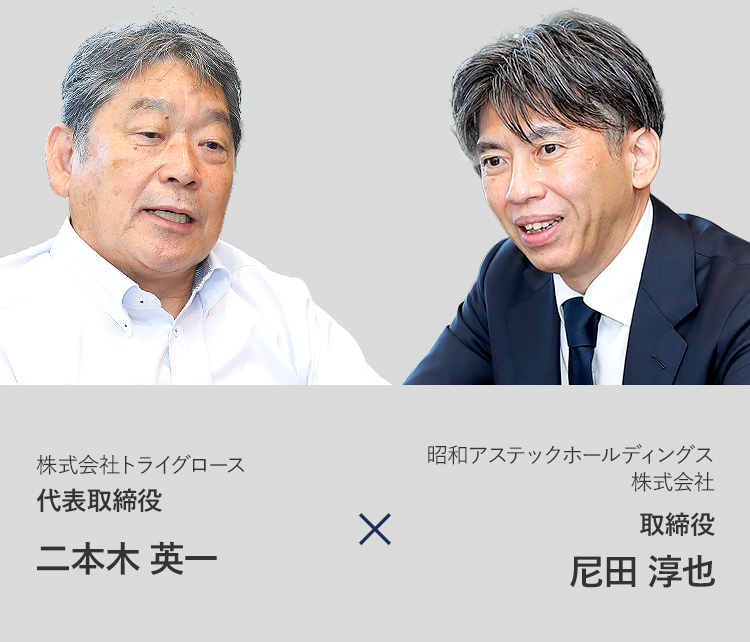
“背水の陣”から“大きな安心感”へ。
70歳社長の従業員と会社の未来を見据えた決断
電気計装事業を通じて発電設備や化学プラントなど社会インフラの安定稼働を支えている株式会社トライグロース。20年以上にわたる豊富な知見と経験を持つ技術者たちが、顧客からの信頼を得て実績を積み重ねてきた。2025年、同社は昭和アステック株式会社とのM&Aを決断した。その経緯と今後の展望について、株式会社トライグロース 二本木 英一 様、昭和アステックホールディングス株式会社 尼田 淳也 様に伺った。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社トライグロース
- 所在地
- 愛知県半田市
- 設立
- 2020年
- 従業員数
- 35名
- 事業内容
- 発電所および石油プラント等の電気計装工事
- M&Aの検討理由
- 後継者不在のため
-
譲受企業
- 会社名
- 昭和アステックホールディングス株式会社
- 所在地
- 東京都港区
- 設立
- 1951年
- 従業員数
- -
- 事業内容
- 石油精製・石油化学プラントの防爆電気設備・防爆計装エンジニアリングを主力に業務展開
- M&Aの検討理由
- 技術者の獲得のため
専門技術と信頼を武器に地位を確立してきた電気計装事業
創業の経緯と事業内容を教えていただけますか。

事業の柱は火力・原子力発電所でのメンテナンス業務です。それに加え、老朽化した設備のリプレイスといった電気計装工事も請け負っています。 私自身のキャリアは、1981年にトライグロースの前身となる会社へ入社後、長年にわたり電気計装の分野に携わってきました。ところが、バブル崩壊の影響で業績が悪化し、さまざまな対策を打っても好転せず、とうとう2004年に会社をたたむことが決まってしまったのです。途方に暮れ、親しくしていた同業他社の社長に相談すると、「会社を始めるならバックアップしますよ」と温かいお言葉をいただきました。そのおかげもあり、資金提供を受けて事業を引き継ぐ形で独立することを決意しました。それが、50歳手前のことです。
大きな決断ではありましたが、「社長になったぞ」という特別な高揚感や気負いは正直ありませんでした。というのも、取締役本部長時代から現場のことはすべて任されており、お客様とのやり取りから業務の差配まで、実質的な経営は自分で行っていたからです。
変わったことといえば、会社の資金繰りのために自身が連帯保証人になったことくらいです。会社そのものは社名を変えただけで、事業も人材もそのまま引き継ぎましたので、スムーズに再スタートを切ることができました。
その後、事業は順調に推移したのでしょうか。
最初の2年間こそ数百万円ほどの赤字でしたが、それ以降は今日に至るまで一度も黒字を逃したことはありません。私たちの事業は、ほとんどがお客様や関係者の方からのご紹介で成り立っています。この業界は広いようで狭く、信頼がすべて。「あの業者はいい加減だ」という評判が立てば、たちまち仕事は来なくなります。だからこそ、一つひとつの仕事に真摯に向き合い、信頼を積み重ねてきました。
そうして事業が軌道に乗った後、最初の大きな転機が訪れたのが、東日本大震災後の電力自由化でした。電力会社の経営方針が大きく変わり、発電所の定期点検インターバルが大幅に延長されたのです。定期点検は私たちの主な収益源でしたから、これは死活問題。売上の8割を占めていた大手電力会社の仕事が、一時は3割を切るところまで落ち込みました。しかし、バイオマス発電所の新設や化学プラントなど、電力以外の分野からお声がけいただく機会が増え、おかげさまで時代の波に乗り、事業の柱をうまく移行させることができました。
順調に事業を続けていましたが、2020年に再び大きな転機が訪れます。当時、出資していただいた方と、経営方針の違いもあり、独立することになりました。
お客様からも、「二本木さんが続けるなら応援します」と温かい言葉をいただきました。ありがたいと思う気持ちと周囲に後押しされる形で、「もう一度、頑張るか」と65歳で覚悟を決め、新生トライグロースとして会社を立ち上げました。
専門性の高い事業ですが、御社の強みはどこにあるとお考えですか。

私たちが手がける計装という分野は、プラントにおける制御などを担うニッチな領域です。大がかりな機械設備に比べると工事の受注額は小さいですが、プラントを正確に動かすためには不可欠です。そのため大手企業は参入しづらく、専門業者も多くはありません。人が育ちにくい分野でもあるからこそ、専門家として頼りにしていただく機会が多いのです。ライバルが少ない、これが最大の強みかもしれません。現在では、人手が足りずにお断りせざるを得ない案件もあるほど、多くのお引き合いをいただいています。
事業承継へのタイムリミットが迫っていることへの焦り
事業が好調な中、どのようなきっかけでM&Aを意識され始めたのでしょうか。
最大の理由は後継者問題です。おかげさまで業績は非常に好調で、今期も最高益を見込んでいます。しかし、私自身が70歳になり、事業承継のタイムリミットが迫っていると感じていました。社内には息子もいますが、会社を任せるには、引継ぎや育成など承継には最低でも5年はかかると考えていました。時間的な猶予がないという焦りから、「M&Aも一つの方法ではないか」と考え始めたのです。
ただ、最初からM&Aに前向きだったわけではありません。当初はほとんど興味がなく、むしろ消極的でした。周囲でM&Aを経験した方からあまり良い話を聞いていませんでしたし、顧問税理士などからも慎重な意見をもらっていたので、ネガティブな先入観があったのです。
そのような状況で、M&Aを本格的に検討する決め手は何だったのでしょうか。

M&Aキャピタルパートナーズのアドバイザーとの出会いです。あるとき手紙をいただき、最初は興味本位で「どんな話か聞いてみよう」とお会いしました。しかし、実際に話してみると、お若いのに非常に理路整然とお話され、何よりその人柄に誠実さを感じ、「この人なら信頼できるかもしれない」と直感したのです。
彼との出会いがなければ、M&Aが本格的な選択肢となることはなかったでしょう。後日、「もし担当があなたから別の人に代わったら、この話は断る」と本人に伝えたほど、彼という人間を信頼していました。実際にその後、担当は代わってしまったのですが、前任者に劣らず素晴らしい方でした。だからこそ、最後まで安心してお任せすることができたのです。
「もうM&Aはやめよう」という考えを覆したアドバイザーの提案
ここからは担当アドバイザーの常峰さんにも加わっていただきます。二本木様のご支援は、前任の方から引き継がれたそうですね。

はい。前任の担当者から、私が担当を務めさせていただくことになりました。私が担当を引き継いだ時は、譲受候補企業3社と面談を進めていたものの、事業面でのシナジーが見出せず難航していた時期でした。
正直に言うと、その頃には8割がた「もうM&Aはやめよう」と気持ちが固まっていました。何社かとお会いするうちに、自分たちが本当に求める条件は明確になっていきましたが、それゆえに、ご紹介いただいた企業とはどうしても合わないと感じたのです。
良い条件をご提示いただいても、電力関連や計装という専門分野へのご理解が少し浅いように思えましたし、M&A後に「従業員や技術をどう活かすのか」というビジョンも明確ではありませんでした。また、大変失礼ながら会社の規模も我々と大きくは変わらず、グループ入りするメリットを感じられなかったのも事実です。
そして社内承継という選択肢もあったため、「無理に進める必要はない」と考えていました。会社は資金繰りや業績の面で特に問題を抱えておらず、経営的に切羽詰まった状況ではありませんでしたから。そのまま続けようと思えば、まだまだ続けられたわけです。
常峰さんはどのような提案をされたのですか。
まず、前任からの情報と、私自身が二本木社長から直接ヒアリングした内容を改めて整理しました。そして、これまでのご面談を通じて、二本木社長がお相手に求める「事業内容の親和性」「相乗効果」「会社の規模感」という条件は明確でしたので、その条件をもとに再度お相手企業探しを行いました。その結果、今回のお相手である昭和アステックホールディングス様は、M&A戦略とも合致する部分があり、双方にとって良いお話ができるのではないかと考え、提案に至りました。
その提案を受けたときの印象はいかがでしたか。

「こんなにピッタリの会社を、よくぞ見つけてくれた!」というのが率直な感想です。事業内容は非常に似ているのに、顧客層がまったく被っておらず、両社で手を組めば大きな相乗効果が生まれるとすぐに分かりました。さらに、互いの繁忙期・閑散期を補い合えますし、会社の規模から人材も豊富だろうという期待もありました。もし昭和アステック以外だったら、M&Aの検討は続けなかったと思います。
また、最初の面談から役員の方々が非常に丁寧で、上から目線な態度が一切なく、とても好印象でした。そして後日、堀江社長(昭和アステックホールディングス株式会社 代表取締役社長 堀江 健介 様)にお会いして、お人柄に触れたのが決定的でしたね。「この方は嘘を言う方ではない。この方となら安心して一緒にやっていける」と確信しました。
理想的なお相手に出会われたのですね。迷わず決断されたのでしょうか。
いいえ、実は非常に迷いました。素晴らしいお相手であることは間違いありませんでしたが、社内では息子への事業承継を期待する声もあり、最終的なお返事までに2〜3ヶ月の猶予をいただきました。ただ、心の中では「この話を断ったら、これほど合う会社は二度と現れないだろう」とも思っていました。
最後はもう「時間切れだ」という思いです。これ以上ひとりで考えても、1年後、2年後も同じように迷い続けるだろうと。明確に「これだ!」というよりも、「えいや!」とサイコロを振るような気持ちで決断しました。私としては、100%の確信というより、“会社と従業員の未来のために、前進するための決断”でした。
「大事なのは“人”だ」という想いが結んだ信頼とパートナーシップ
ここからは、譲受企業である昭和アステックホールディングス株式会社の尼田様にもご参加いただき、お話を伺います。まずは事業についてご紹介いただけますか。

昭和アステックは1951年の創業以来、主に石油化学プラントを対象に、防爆と呼ばれる特殊な電気計装工事を事業の柱としてきました。設計から施工、メンテナンスまでを一貫して手がけ、現在は全国約39箇所の工場に常駐し、お客様のプラントの安定稼働に欠かせない存在として事業を展開しています。
創業当初はプラントの建設工事が主体でしたが、建設ラッシュが一段落した際に、前オーナーが「今後はメンテナンスに軸足を移す」という経営判断をしました。その方針が現在の事業基盤となっており、今では常駐メンテナンス事業が売上の約8割を占める主力事業となっています。
多くの電気設備工事会社は、「そこまで突出して特殊な技術を持っているわけではない」と考えています。その中で我々の強みを挙げるとすれば、まず防爆という特殊な施工技術を持っていること。そして、一般設備ではなく高圧電力を扱うため、有資格者による安全な施工の重要性を熟知している点です。そして、究極的な話で言うと、技術そのものよりも「現場で働く人」こそが最大の強みだと考えています。個々の技術者が持つ高い技術力と、状況に応じて臨機応変に対応できる力。結局は“人”が我々の事業の核だと考えています。
M&Aに対するお考えを教えてください。
昭和アステックが本格的にM&Aに着手したのは2019年からです。その戦略には、大きく分けて2つの軸があります。
第1の軸は「人的補完」です。少子高齢化により業界全体で採用が難しくなり、既存事業を守り、成長させていくための人材・技術力の確保が急務となっています。第2の軸が「事業ポートフォリオの分散」です。主力である石油化学の領域だけでなく、電気通信やインフラ関連といった新たな事業領域を開拓し、将来的なリスクの分散を図っています。
実は、今回のトライグロースで3社目の資本提携となります。1社目は2019年に福井県の計装会社、2社目は2022年にシンガポールの電気通信工事会社をグループに迎え入れました。
トライグロースに興味を持たれた理由をお聞かせください。
昭和アステックは、「The Human Capital Company」というスローガンを掲げており、事業内容以上に従業員への想いを重視しています。二本木社長が、従業員を守るために一度は身を引く覚悟を決めながらも、皆に請われて再び会社を立ち上げたというご苦労の経緯を伺い、仕事への情熱はもちろん、従業員のことを第一に考える姿勢に強く感銘を受けました。そのため、「この方となら一緒にやっていける」と面談の早い段階で直感しました。
実は、最初のトップ面談の際に代表が体調を崩してしまったのですが、二本木社長が「また日を改めて」と快く日程の変更を受け入れてくださったのです。そのご厚意にも大変感謝し、こうした一つひとつの出来事にもご縁を感じました。
事業面でのシナジーについては、どのようにお考えでしたか。

二本木社長ご自身が、技術を深く理解されている方だったのも大きなポイントでした。例えば防爆といった専門的な話もすぐに理解してくださるので、我々としては非常に話が進めやすかったです。 また、施工管理を主体とする我々にとって、現場作業を担っていただく信頼できる協力会社の存在は不可欠です。トライグロースのような高い技術力を持つ会社を迎え入れることで、これまで外部に依頼していた仕事を“気心知れた仲間”と進められるようになります。これは、我々にとって計り知れないシナジーをもたらします。
さらに、この関係はトライグロースの従業員の皆さんの成長にもつながると考えています。より難易度が高く規模の大きな仕事に挑戦していただくことで、従業員の皆さんの視野も広がり、会社としてさらに成長していけるのではないでしょうか。もちろん、我々は何が何でも「昭和アステックの仕事だけをしてください」と押し付けるスタンスではありません。「こういう案件がありますが、ご対応いただけますか」とご提案し、状況に応じて取捨選択していただく。そうしてお互いが、ともに成長していける関係が理想だと考えています。
二本木様が、「この会社となら」と思われた決め手を教えてください。
昭和アステックは会社の規模が大きいので、「少し上から目線で来られるのでは」と警戒していましたが、役員の方々は非常に物腰が柔らかく、丁寧で、すぐに好感を持ちました。特に、後日お会いした堀江社長の「一番大事なのは人だ」という言葉には強く共感しました。私も人と人とのつながりを何より大切にしていますから、その価値観が完全に一致したのは大きかったです。さらに、「ああしろ、こうしろとは一切言わない」と私たちを尊重してくださる一言が、心に強く響きました。
「今後、この産業がどうなっていくのか」という将来に対する考えも、ある程度、共通認識が持てていると感じます。外部環境は私たちの都合の良いようには動いてくれず、「変化は一瞬で訪れる」という苦い経験もしてきました。だからこそ、「10年後、20年後も今と同じようにやっていけるのか」という危機感を共有し、多少の嵐が来ても揺るがない“屋台骨”をしっかりさせたいという考えを一致することができたのだと思います。
代表の堀江は、最終的には経営者の方と直接お話し、その初対面の直感を何より大事にします。トップ面談まで進んだ案件は、8割方成約に向けて進みますが、最終的な決め手となる残りの2割は、理屈ではない「フィーリング」です。二本木社長とお会いし、技術への深い知見と従業員を想うお人柄に触れ、すぐに「ぜひご一緒したい」という気持ちが固まりました。業界の未来をどう見るか。そのビジョンにおいても、二本木社長と我々の間には、大きな隔たりはありませんでした。
トライグロースは元々愛知県が中心だったと伺いましたが、今では関東をはじめ全国各地で事業を展開されています。昭和アステックの現場も全国にありますから、そうした拠点で連携し、トライグロースの事業展開を我々がサポート、バックアップできる部分も大きいだろうと考えています。
常峰さんは、アドバイザーとして面談をどのようにご覧になっていましたか。
初回の面談から相性の良さは感じていましたが、堀江社長がお会いになられてからは、結びつきが強くなっていくのが分かりました。ご両社の対話は非常に自然で、私が口を挟む必要がまったくないほどでした。
既存事業を大事にしながら、互いに補い合える関係を築いていく未来へ
成約後のお気持ちや、今後の展望についてどのようにお考えですか。

これまでは後ろ盾がなく、「ここで自分が転んだら終わりだ」という背水の陣を敷いてやってきましたが、今は「昭和アステックがいてくれる」という大きな安心感があります。もっとも、経営が切羽詰まっていたわけではないので、失敗だったとは決して思いませんが、正直に言えばこの決断が正解だったのかどうか、まだ確信はありません。だからこそ、「M&Aをしたから後は適当でいい」という気持ちは一切なく、これから事業をどう伸ばしていくかを常に考えています。「長く続けてほしい」と言っていただいていますが、私としては、次の経営者にしっかりとバトンを渡す目処がついた段階で、元気なうちに退任したいという想いもあります。
事業連携の面では、昭和アステックの仕事の一部を我々がカバーするなど、補い合える関係を築いていきたいです。まずは研修会への参加から始め、私たちの既存事業も大切にしながら融合を図っていくことが今から楽しみです。これが今回のM&Aがもたらす大きなメリットだと感じています。
トライグロースには、高い技術力を持つだけでなく、出張なども厭わないフットワークの軽い社員の方々がたくさんいらっしゃいます。そうした皆様には、昭和アステックのさまざまなリソースを最大限に活用していただきたいです。
例えば、財務や人的なバックボーン、各種研修や社内制度といったリソースを開放することで、グループ各社がともに成長できる場所を作っていくのが我々の役目だと考えています。グループ全体の成長をともに目指していきたいです。
また、昭和アステックはホールディングス体制なので、グループ会社間に上下関係はなく、あくまでも対等なパートナーです。二本木社長には、その素晴らしい求心力で、これからも会社を力強く牽引していただくことを大いに楽しみにしていますし、社長ご自身のことも我々がしっかりとバックアップしていきます。
今回の取り組みにおけるM&Aキャピタルパートナーズの支援を、どのようにご評価いただいていますか。

忖度抜きで、本当によくやっていただきました。M&Aキャピタルパートナーズにはこれまでにも多くの案件をご紹介いただきましたが、成約に至ったのは今回が初めてです。我々自身も探している相手の軸が定まっていなかったため、多くのご提案をお断りする中で次第にニーズを深くご理解いただけたのだと思います。その上で常峰さんが、「この案件は昭和アステックに合うのではないか」とアンテナを立て、ピンポイントでご紹介してくださったことが、このご縁が実った最大の要因です。我々の考え方やスタンスを熟知した上でのご提案は非常にありがたく、レスポンスも驚くほど早いため、常に安心してプロセスを進めることができました。心から感謝しています。
常峰さんは非常に誠実で、きちんとした方でした。そしてとにかく仕事が早い。今日話したことが、今日中にメールで共有されるくらいのスピード感があり、全幅の信頼を寄せていました。
実は以前、別のM&A仲介会社と関わった際に、不信感を抱いた経験があります。Web会議で不具合が生じたため電話をしたのですが、担当者とまったく連絡が取れなかったのです。大切な会社の将来を託すのですから、信頼できる相手でなければ任せられません。M&Aキャピタルパートナーズは、約束を守る、連絡が早いという基本が徹底されているので、不安は一切ありませんでした。
それに、決して急かすようなことはなく、「ゆっくり時間をかけて考えてください」というスタンスで寄り添ってくれました。ご紹介から最終的な手続きに至るまで、こちらが「ここまでやってもらえるのか」と思うほど何から何までサポートしていただき、私自身はほとんど何もしていないという感覚です。
ありがとうございます。最後に、これからM&Aを検討する経営者の方々にメッセージをお願いします。
私自身、トライグロースと同規模のグループ会社の経営にも携わっていますので、中小企業が直面する課題は身をもって理解しています。知名度の問題による採用の難しさや、昨今の賃上げ要求への対応など、単独で成長していくには限界があるのが実情です。
そうした背景から、規模の大きな会社との「強い接点」を持つことがいかに重要か、私自身が実感してきました。私が代表を務めるグループ会社も、6年前に昭和アステックと提携してから、計器メンテンナスなどの現場業務だけでなく施工管理・監督業といったよりレベルの高い仕事に挑戦する機会が増え、売上だけでなく、従業員の考え方や会社の雰囲気も大きく変わりました。
長年経営されてきた会社への想いや、大企業と一緒になることへの気後れから、二の足を踏まれるお気持ちはよく分かります。しかし、従業員の成長や待遇改善など、会社の未来を真に考えるのであれば、M&Aは企業の成長に不可欠な選択肢の一つです。それを検討することも、従業員を想う経営者の重要な務めだと考えています。

企業の置かれている状況は、後継者がいない、資金繰りが厳しいなど、本当にさまざまです。ですから、一概に「M&Aが良い」と申し上げるつもりはありません。ただ、経営者として「会社の将来がどうなるのか」を予測しようと努めることは、どのような状況であれ必要だと考えています。
もちろん、未来がすべて見通せるわけではありませんが、少なくとも「小さな船より、少し大きな船に乗り換えた方が、従業員は安心できるのではないか」と考える視点は重要です。経営者がどうしたいかという想い以上に、大切なのは「従業員がいかに安心して仕事や生活ができるか」。それを実現するための一つの選択肢として、M&Aは非常に有効な手段だと感じています。何十年も経営されてきた会社を手放すことに、オーナー社長が悩むのは当然ですが、その想い以上に優先すべきは、従業員と会社の未来です。
素晴らしいご両社をつなぐという、非常に良いご縁に携われたことを大変嬉しく思いますし、無事にここまでお手伝いできたことに安堵いたしました。
これからご譲渡を検討されるオーナー様へお伝えしたいのは、“M&Aはあくまで選択肢のひとつ”だということです。二本木社長もおっしゃっていましたが、親族や従業員への承継、あるいは上場や廃業といった道もあります。どれが正解かということはありません。だからこそ、まずはさまざまな可能性を検討するための情報収集から始めていただくのが良いかと存じます。
また、企業のお譲り受けをご検討の皆様には、M&Aをぜひ戦略的にご活用いただきたいと考えています。人口が減少していくこれからの日本において、企業の効率性はますます問われることになります。そうした時代にあってM&Aは、企業をより大きく成長させ、国内だけでなく海外でも活躍する力をつけ、ひいては日本全体を強くするための大きな可能性を秘めた戦略の一つです。我々は、そのような未来につながるM&Aのお手伝いができればと考えておりますので、ぜひご相談いただければ幸いです。
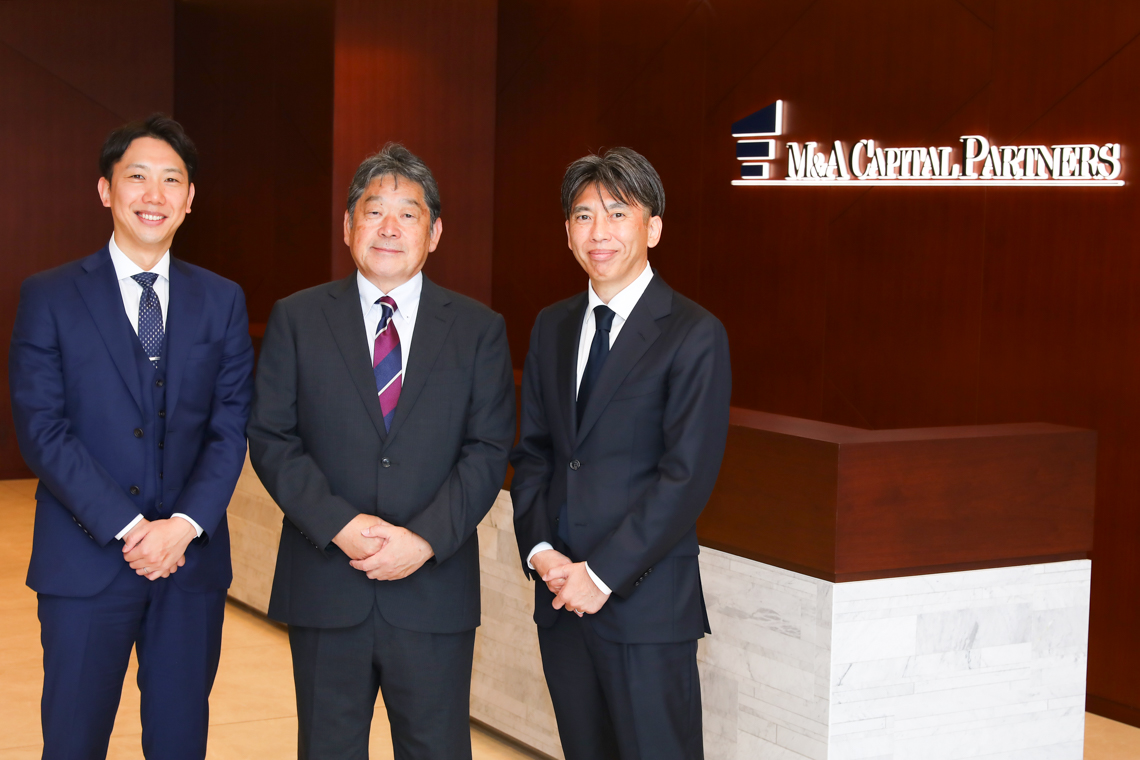
文:伊藤 秋廣 取材日:2025/8/25
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。











