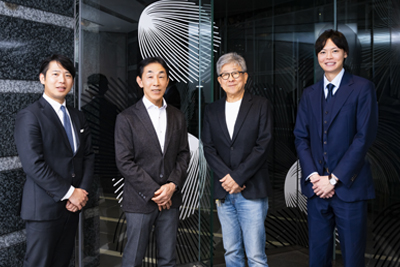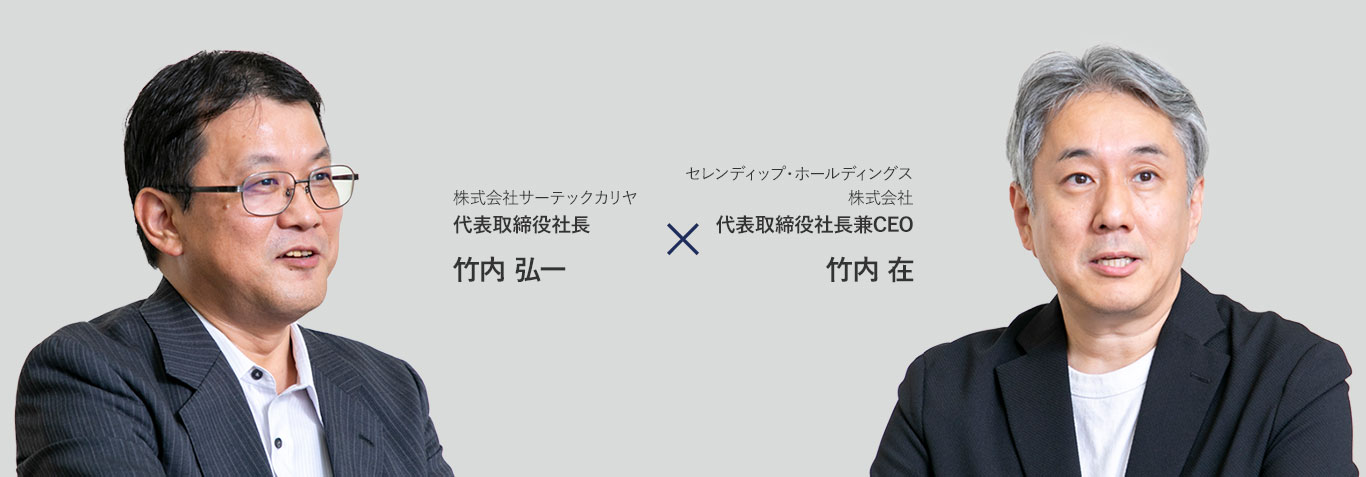
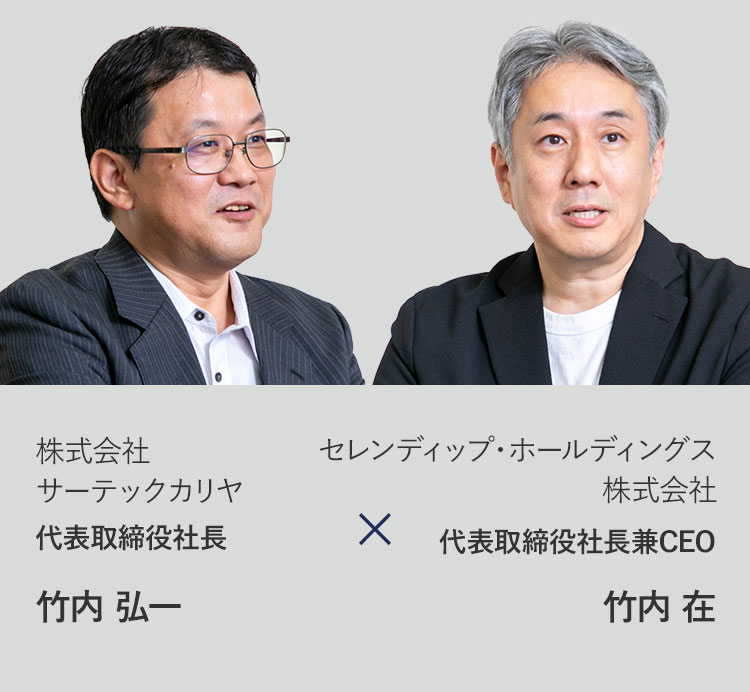
自動車産業を支えるトップカンパニーが選んだ成長戦略はM&A
相互出資という一蓮托生の覚悟がもたらすもの
創業75年、自動車部品の表面処理技術で国内トップクラスの地位を築いてきた株式会社サーテックカリヤは、グローバル展開で売上200億円超まで成長を遂げつつも、2025年7月にセレンディップ・ホールディングスグループへの参画を決断した。単なる株式譲渡ではない「相互出資型」という新しいM&Aの形が示唆する製造業の未来像について、株式会社サーテックカリヤ 代表取締役社長の竹内 弘一様、セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長兼CEO 竹内 在様、そして取締役CFO 北村 隆史様にお聞きした。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社サーテックカリヤ
- 所在地
- 愛知県刈谷市
- 設立
- 1954年(1950年創業)
- 従業員数
- 3,004名
- 事業内容
- 表面処理技術のパイオニアで、自動車のエンジン、ブレーキ、空調部品といった安全性・信頼性が求められる部品への採用実績を多数有する
- M&Aの検討理由
- 事業の拡大・成長、後継者問題の解消のため
-
譲受企業
- 会社名
- セレンディップ・ホールディングス株式会社
- 所在地
- 愛知県名古屋市
- 設立
- 2006年
- 従業員数
- 66名
- 事業内容
- 経営受託・経営支援などを主体に、財務会計なども含めた経営コンサルティング業務を行っている
- M&Aの検討理由
- 事業拡大のため
世界中の自動車産業を支える表面処理技術
サーテックカリヤの事業概要と強みについて教えてください。

1950年の創業以来、自動車部品の表面処理、特に金属上のめっきを専門として事業を展開してきました。これは、90年代はじめまでは、刈谷鍍金工業所という社名だったことにも表れています。金属部品に対して耐熱性や耐摩耗性、防錆といった機能を付与する技術が当社の最大の強みです。
自動車という愛知県の一大産業を、当社の技術力で下支えしてきたという自負もあります。メーカー側のニーズが多様化するとともに、研究を重ねることで、さまざまなめっきに対応できるように努めてきました。その結果の一例として、車載エアコンに使用するコンプレッサー部品を年間2,400万台分も生産しています。全世界での自動車生産台数が年間約1億台と言われますので、単純計算では新車の4分の1に、当社が表面処理した部品が搭載されていることになります。

刈谷で生まれ育った私は、子どもの頃から父に連れられて会社に足を運んでいたため、遊び場のように感じていました。なじみがあったので、大学卒業とともに入社することに。入社後は主要な取引先であるデンソーの仕入先枠で総合職の入社研修を受講し、生産管理、部品検査部で、2年間基礎を学びました。その後インドネシアでの法人立ち上げのため2年間出向しました。帰国後はデンソーTQM賞の事務局を担当し、会社にかかわるさまざまなデータを取り扱いながら経験を重ねた遍歴があります。その後、2013年に父から後継者社長に指名されるに至りました。
竹内(弘)様が入社してからの業績変化という点ではいかがだったでしょうか。
振り返ってみれば、当社は着実な成長を遂げてきました。私が入社した1993年の売上は20億円規模で、ほぼ国内のみのビジネスでしたが、30年を経て国内だけで120億円、グローバルのグループ全体では200億円を超えるまでになりました。この成長を支えたのは、お客様との信頼関係と技術力、そして積極的な投資だったと思います。
リーマンショックでは、主要取引先の生産が大幅に落ち込み、当社も影響を受けました。ただ、その時期を新たな技術開発の機会と捉え、次世代の自動車部品に対応する表面処理技術の研究に注力しました。さらに品質課題の解決にも取り組み、自動車業界で技術的な問題がクローズアップされた際には、当社の表面処理技術を活用した解決策を率先して提供しています。新型エンジンの耐久性向上にも当社の技術が貢献していますが、こうした技術開発力の支えになっているのは当社の設備があるからです。設備を自社で製造できる体制をとっていることが、お客様のニーズに対する迅速な対応につながっているのです。
一方、積極的な設備投資により、財務面のバランスが不安定な状況になるタイミングもありました。それもあり、社長就任後は、財務体質の改善にも注力し、現在ではより健全な経営基盤を構築できたと思っています。
地に足のついた堅実な経営を心がけていらっしゃったのですね。
それにもかかわらずM&Aを検討したのはなぜだったのでしょう。

ずっと、自動車産業という、巨大かつ特殊なビジネスに依存していることへの危機感はありました。当社に限らず、愛知県の企業の多くは、自動車関連の事業に依存しているケースが少なくありません。EV(電気自動車)へのシフトが進む中で、今後、エンジン部品の需要は確実に減少することが見込まれます。売上減少は避けられない中で、どのように適応するか、生き残っていくか不安がある中で、M&Aという選択肢を考えるようになりました。
自動車産業という特定業種への依存が続いたこともあり、当社には飛び込み営業的な売り込みは必要ありませんでした。30年以上にわたり、仕事はお客様からの依頼によって成り立つものであり、自ら営業して獲得するという発想が根付いていなかったのです。こうした状況を変えようと、自ら新規取引先の開拓に乗り出したタイミングもありましたが、既存の業務で手いっぱいなところ、新規開拓は決して効率が良いとは言えず、結局立ち消えになってしまいました。
M&Aによって外部の力を取り入れることが重要と考えたのですね。
M&Aによって、透明性のある会社にしたいという狙いもありました。いわゆるオーナー経営体質で、上意下達、トップダウン式で「次世代のリーダーが育っていない」という危機感もありました。大切な情報も、経営のトップ層にのみ集中してしまう仕組みが続いており、こうした状況を放置していれば、本質的な経営改善を行ううえでも障壁になるのは目に見えていました。
よりよい組織として進化するには、M&Aで外部の力を取り入れることが最適と考えた
M&Aキャピタルパートナーズとの出会いについて振り返っていただけますか。

私からお電話を差し上げたのがきっかけでした。以前からサーテックカリヤの社名はお聞きしており、高い技術力を持った、規模感のある会社だと認識していましたので、ぜひ一度お話をさせていただきたいとお願いした次第です。
他にも多数のM&A仲介会社から連絡はありましたが、松井さんが他社と決定的に違ったのは、企業価値の評価に対する姿勢です。多くの企業が表面的な財務数値だけで機械的に評価する中で、M&Aキャピタルパートナーズだけが丁寧なプロセスで、適正な評価を行ってくれました。当社の真の強みである技術力を正しく見てくれたから、評価金額も変わったのだと思っています。
竹内(弘)様がおっしゃった通り、他社と私たちとでは、根本的なアプローチが異なっていたように感じます。サーテックカリヤのような技術力を持つ製造業の真の価値は、表面的な数字だけでは測れません。取引先から「代替できない技術」と頼られている事実もその証拠の一つです。また、めっき技術の進化によって品質改善を提案してきた事実からも、ただ受託して加工を行うだけでなく、問題解決型のソリューション提案企業としてのポテンシャルを示していると思います。
当時、限定的にしか経理データを揃えられなかった私に対して、松井さんは本当に根気強く対応してくれました。これまでサポートしてきた他社の事例と比べても大変だったのではないかと感じています。
企業価値の評価に際しましては、M&Aキャピタルパートナーズの士業専門家集団であるコーポレートアドバイザリー部に協力を依頼し、担当となった公認会計士の小嶋(M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 コーポレートアドバイザリー部 ディレクター 小嶋 善雄)と共に提案させていただきました。竹内様のもとを訪ねる際にはその都度、小嶋公認会計士も同行し、財務面の専門的な分析はもちろん、製造業特有の会計処理や、海外子会社を含めた連結での評価など、専門性の高いサポートを心がけました。
小嶋さんをはじめとする専門家の方々がバックにいるというのは、心強かったです。サーテックカリヤの将来性についても、客観的かつポジティブに評価してくれました。EV化でエンジン部品は減少しても、そのEV車向けの新たな需要も生まれており、電動コンプレッサーやインバーターなど、EV関連部品の表面処理はむしろ高度化・高付加価値化しています。この技術転換への対応力も織り込んでくれました。
サーテックカリヤの海外展開の実績も重視すべきだと考えました。得意先の生産拠点に合わせて、すでにタイやインドネシア、ベトナム、フィリピン、マレーシア、さらにメキシコと多くの海外拠点にネットワークを構築されていましたが、これは後から簡単に真似できるものではありません。
また、めっき業界では既にマーケットリーダーであり、得意先からも絶大な信頼を得ているにもかかわらず、安泰だと思わずに、「トップ企業だからこそ先に変化が必要だ」と危機感をお持ちの姿はとても印象的でした。
以前から譲受企業であるセレンディップ・ホールディングスのことはご存知だったのでしょうか。
松井さんから初めて名前を聞いたのは、白金鍍金工業株式会社のM&Aを行った会社として、白金鍍金の笹野会長(当時社長)の褒章受章記念パーティーの時です。白金鍍金工業は県内の同じ協同組合に所属している間柄で、めっきを専門としていることからも旧知の仲です。ただ、白金鍍金工業は樹脂めっき、当社は表面処理で、専門分野が異なるため、全く競合しない関係でした。ただ、白金鍍金工業を譲り受けた「日本ものづくり事業承継投資株式会社」がセレンディップ・ホールディングスのグループ企業と聞き、どのような企業なのかは気になっていました。
松井さんから、「一般的な投資ファンドのように数年で再び譲渡して利益を得ることを目指すのではない」とお聞きした時は、少し意外に感じました。グループに参画した会社をじっくり育て、グループ全体の成長を目指す方針と知ったことが、その後の私の決断にも大きな影響を与えました。
白金鍍金工業の事例は、セレンディップ・ホールディングスを竹内(弘)様にご紹介させていただくうえで、良い事例だったと思います。資本投入を行うだけでなく、経営人材を送り込み、現場と経営の両面から支援するというスキームが親しみのある企業で起こったことで、イメージしやすくなったのではないでしょうか。
ものづくりへの愛着と深い理解。惹きつけられる両者の出会い
ここから竹内 在様と北村様にもお話をお聞きします。
まずセレンディップ・ホールディングスの概要をお話しいただけますか。

当社は2006年に創業した、ものづくり企業の経営支援に特化した事業投資会社です。事業承継M&Aによる経営受託・経営支援などを主体に、財務会計なども含めた経営コンサルティング業務を行っています。
私自身は外資系のIT企業で働いていましたが、日本企業の生産性の低さや非効率性にもどかしさを感じていました。しかし、外部からコンサルティングやITシステムを提供しても、結局根本的な変革は起きません。それなら自分たちがリスクを取って中に入り、一緒に汗をかきながら変えていこうと考えたのが創業のきっかけです。
当初は私自身が社長として企業に入り、現場でラインを改善しながら経営改革を進めていました。自分の手で変革を実証していくうちに、徐々に体系化されて、経営と現場の両輪で企業を支援する体制が整ってきたと自負しています。私たちは、まずルールやプロセスを明確化し、属人性を排除します。そして、これらの仕組みを実行できる組織体制を構築しつつ、若手から中間管理職まで、各層の人材を育成します。こうした仕組みづくり、組織づくり、人材育成の3つを同時並行で進めることが、持続的な成長のための重要な要素です。

私は監査法人でのコンサルティングを経て、2018年に当社へ参画しました。私自身も、コンサルタントの立場では、執行権限がなく実行まで責任を持てないジレンマを感じていました。そのため、現在のように直接経営改善に関与し、変革を実行できる仕事には魅力とやりがいを感じています。
松井さんが解説してくださったように、M&Aに対する私たちのスタンスは明確で、短期的な売却益を狙うのではなく、長期的な企業価値向上を目指します。そのため、投資先を選定する際にも「成長の奥行き」を重視します。国内だけでなく、世界で通用する技術や事業モデルを持っていて、5年後、10年後も成長できる余地があるかが最も重要な判断基準です。
別の言い方をすると、現在の売上規模や利益率は二の次です。むしろ変革の余地が大きい企業の方がより魅力的だと考えます。特に日本の基幹産業である自動車関連製造業は、長年変化を避けてきた傾向にあり、その分変革による成長ポテンシャルが大きいと考えています。
そういった意味で、サーテックカリヤはまさに我々が求めていた企業でした。自動車部品の表面処理という、私たちがまだ進出していなかった領域のリーディングカンパニーであり、75年の歴史と200億円超の売上、さらに海外8拠点という実績があります。そして何より、継続してEVをはじめとする新たな技術の領域にも積極的に挑戦されています。最初にお話を聞いた時から、一目惚れに近い感覚でした。
初めて両社がお会いした時の印象はいかがでしたか。
初めてお会いした際、髙村(セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役CIO 髙村 徳康 様)さんの迫力に圧倒されたことをよく覚えています。当社の強みを理路整然と分析し、「一緒に会社を強くしていこう」という意思が明確に伝わってきました。当社の事業に対する理解も深く、既存の取引先との関係性や品質問題への対応、海外展開の状況など、私が説明する必要がほとんどないほどでした。そのうえで、セレンディップ・ホールディングスのリソースと組み合わせることで実現できる将来像を、具体的に示してくださったのです。
私が最も惹きつけられたのは、グループインした企業における人材育成の実例でした。若手社員が成長を遂げて、他のグループ会社で社長を務めてもおかしくないほどの人材になっているとお聞きして、興奮を隠せませんでした。言うまでもなく、当社の従業員にとって大きなチャンスになると感じたためです。長年のトップダウン型経営が招いた結果として、若手が自分の意見を言える環境ではなかったのが、当社の反省点です。現場の社員一人ひとりが当事者意識を持ち、職場を自ら改革していける環境を目指していましたが、一度根付いた組織文化を独力で変えることは容易ではありません。だからこそ、この話に強く魅力を感じました。
竹内(弘)様には、セレンディップ・ホールディングスだけでなく、近しい領域に進出している事業会社や投資ファンドなど、様々なタイプの企業をご紹介させていただきました。M&Aは一生に一度の大きな決断であり、選択肢を幅広く検討していただくことが重要だと考えています。竹内様が最適な判断をできるよう、各企業の特徴や経営スタイル、もちろんM&Aのメリットも客観的に整理してお伝えいたしました。竹内(弘)様に最適な判断をしていただけるようなサポートを心掛けました。
以前の他の仲介会社からの提案では、同業他社からのスケールメリットを活かした事業拡大を前面に打ち出すお話が多くありました。しかし、規模の拡大だけが目的になってしまうと、従来型の既存ファンドの短期売却益をねらうアプローチと同じで、当社の従業員にとって必ずしも望ましいとはいえません。だからこそ、セレンディップ・ホールディングスの「一緒に成長しよう」という姿勢には、強く共感できました。
面談を重ねる中で、竹内様の中で判断基準が、より明確になっていったように感じていました。単なる金額や条件ではなく、従業員が成長できる環境であること、自社の歴史や文化を尊重してくれること、そして経営の視点が長期的であること。こうした観点から考えた結果、セレンディップ・ホールディングスが最も適していると判断されたのではないでしょうか。
最終的には、人としての相性や価値観、そしてリスペクトできるかどうかが本当に重要だと思います。竹内(在)さんと初めてお会いした時にも、その経営哲学に感銘を受けました。同じ姓という親近感もありましたが、日本の製造業を本気で変えようという情熱、そして私が感じていることと同様の現状への危機感が、言葉の端々から伝わってきました。
北村さんは、財務・会計の専門家としてデューデリジェンス(企業監査)の際に的確な質問をされていたのが印象に残っています。表面的に数字をなぞるだけでなく、その背景にある事業の本質を理解しようとする姿勢が際立っていました。

初対面で、竹内(弘)社長がもつ実直さと誠実さを色濃く感じました。75年の歴史ある会社を経営しているプレッシャーを感じさせない謙虚な姿勢。そして何よりも、会社や従業員のこと、自社の独自性ある製品について話す時の表情が本当に楽しそうで、心から事業を愛していることが伝わってきました。
さまざまな経営者とお会いすると、無意識のうちに自社の課題を隠そうとされる方も少なからずいらっしゃいます。しかし、竹内(弘)社長はその対極にあるような方です。新規の営業をできなかったこと、透明性のある組織にしたいという課題など、率直に話してくださいました。こうした経営者の正直さは、M&A後の成功に不可欠な要素だと考えています。
ポジティブな内容もネガティブな内容も竹内(弘)社長から包み隠さずお話をしていただいたので、かえって信頼が増したことをよく覚えています。従業員の方たちからも慕われていて、中には勤続65年の方がいるという話を聞き、それだけ人を大切にする企業文化があることを実感しました。
さらにデューデリジェンスを進める中で、10年で借入金を大幅に削減してきた、経営者としての不断の努力があったことも知りました。トップ企業でありながら、財務改善にも真摯に取り組む経営姿勢は、決して容易に真似できるものではありません。

このような評価をお聞きすると、ありがたく思うのと同時に、お二人のものづくりに対する理解の深さに改めて驚かされます。製造現場の課題、技術の重要性、そして人に対する考え方をお聞きすると、当社も一緒に成長していけると確信できます。
いくら財務数値が良くても、経営に対する考え方が合わなければうまくいきません。初めてお会いした時から、具体的なシナジーの話で盛り上がりました。私自身が特に魅力を感じたのは、グループ企業との連携による新規顧客開拓や、自動化や省人化による生産性向上です。そして何より、若手人材の育成と活躍の場の創出を早期に実現できると、私自身感じられたのは大変よかったと思います。
また、ぜひお話しておきたいのは、M&Aキャピタルパートナーズの対応が非常にプロフェッショナルだったことです。特に印象的だったのは、全体を通して中立的な立場を崩さずプロセスを遂行してくれた点です。これは両者への信頼と、仲介会社自身に豊富な知識と経験があってこそできることではないでしょうか。
M&Aキャピタルパートナーズの公認会計士チームのサポートによって、財務面はずいぶんと助けられました。特に海外子会社を含めた連結決算の評価、製造業特有の会計処理など、専門性の高い部分がスムーズに進められたことは、M&Aキャピタルパートナーズならではだと思います。約半年間の膨大なデューデリジェンスを経てからの最終契約書の交渉が、約1ヶ月という短期間で完了できたのも、驚異的なことです。
ありがとうございます。私たちは双方の企業にとって最適な結果を導くことを使命としています。今回は、ものづくりへの情熱と従業員を大切にする価値観が共通していました。こうした本質的な部分での合致があったからこそ、スムーズに進められたのだと思います。
相互出資という新しいM&Aの形が、グループのシナジーを加速させる
M&Aの内容を知った従業員の方々の反応はいかがでしたか。

発表された日の夕方、管理職と事務職の全員を集めて説明会を開いたところ、ベテラン社員の中には不安を感じる人もいたようです。しかし、若手から中堅社員の間からは変化を歓迎する声も多く聞かれました。会社の未来に対して希望をもってくれているのは、喜ばしいことだと感じています。
発表の翌月に開かれた創立75周年記念のパーティーの日、そして正式にグループインした日、私も従業員の皆様に直接お話しする機会を作ることができました。現場に出ている従業員にも配信を通じてできるだけ多くの人にメッセージを見てもらえるようにしました。
竹内(弘)社長とは、正社員だけでなく、派遣社員の雇用も守る約束を交わしました。そのうえで、会社の在り方や普段の業務が何も変わらないことも理解され、安心してもらえたのではないかと思います。
多くの人が変化を恐れる気持ちは理解できます。だからこそ、急激に変えるのではなく、時間をかけてじっくり進めることを心がけています。まずは1人でも多くの従業員に変革が「面白そう」と思ってもらうように働きかけて、仲間を増やしていくつもりです。

【成約日に撮影した記念写真と、従業員説明会の様子】
今回のM&Aを振り返っていただけますでしょうか。
実は今回、新たな試みを実現することができました。通常のM&Aは、一方的に株式を譲渡するだけですが、今回は竹内(弘)社長にセレンディップ・ホールディングスの株式を取得していただきました。つまり、サーテックカリヤがセレンディップグループに入ると同時に、竹内(弘)社長がセレンディップの株主になるという相互出資型のM&Aです。
最初にこの提案を聞いた時は驚きました。譲渡するだけでなくこちらも株式を取得するなど、今まで考えたこともない形でした。しかし、私もグループ全体の株主として、経営に関与し、意見を言える立場になることは理にかなっています。単なる子会社の社長ではなく、グループのオーナーの一人として経営に参画できることは、両者のシナジーを実現させる上でも優れた枠組みだと思います。
通常、M&Aを行った会社の経営者には引き続き経営をお願いしていますが、今回のようにグループの株主になっていただくことはありませんでした。しかし、竹内(弘)社長のような優れた経営者に、グループ全体の成長にもコミットしていただきたいと考えたのです。これは、お互いに緊張感のある関係でもあります。もし私たちの経営方針が約束と違うようなことがあれば、株主として反対票を投じることも可能です。一方でグループの経営が良ければ、保有する株式の価値も上がるので、まさに運命共同体と呼べます。
この新しい形のM&Aは、事業承継に悩む経営者にとって、一つの解決策になるのではないでしょうか。会社を手放すのではなく、より大きな成長の機会を得る。そんな前向きなM&Aの形を示せたのではないかと思います。
中小企業にとって、現状維持することさえ難しい時代になっています。このように新たな仲間を得ることは、新たな成長のためのチャレンジに向けたよいきっかけとなります。今後、同じような悩みを持つ経営者の方々のロールモデルになれれば幸いです。
M&Aは成長の機会だと捉えています。トップ企業である今だからこそ、先んじて変わっていこうという決断をしました。変化の大きい時代だからこそ、M&Aを検討する価値は非常に高いと思います。日本の伝統産業である自動車関連企業にとっても希望となる存在になれるように、ますます進化したいと思います。
M&Aは事業承継の一つの手段として認知されてきていますが、企業の成長戦略、従業員の幸せを実現する手段として、経営者の方々にはぜひ早い段階からご検討いただきたいと思っています。今回のような相互出資型のM&Aは、お互いの信頼関係があってこそ実現できるスキームです。今後も、正しい情報と適切なサポートを提供し、多くの企業にさらなる成長のきっかけを届けていきたいと思います。
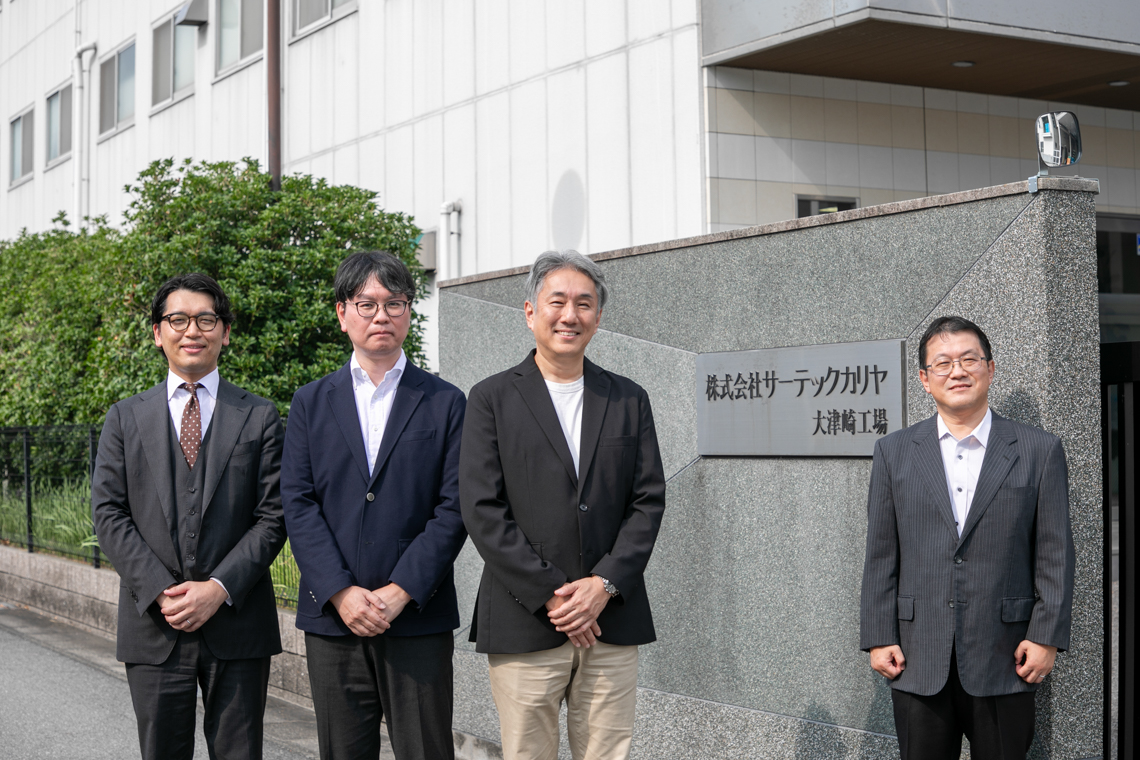
文:蒲原 雄介 写真:北川 友美 取材日:2025/8/25
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。