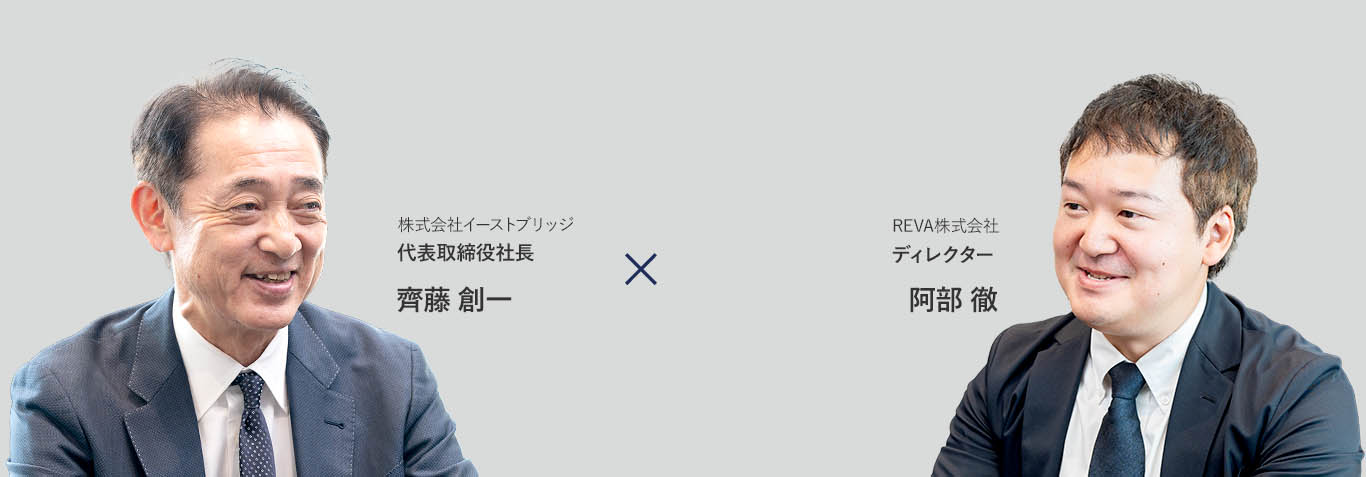
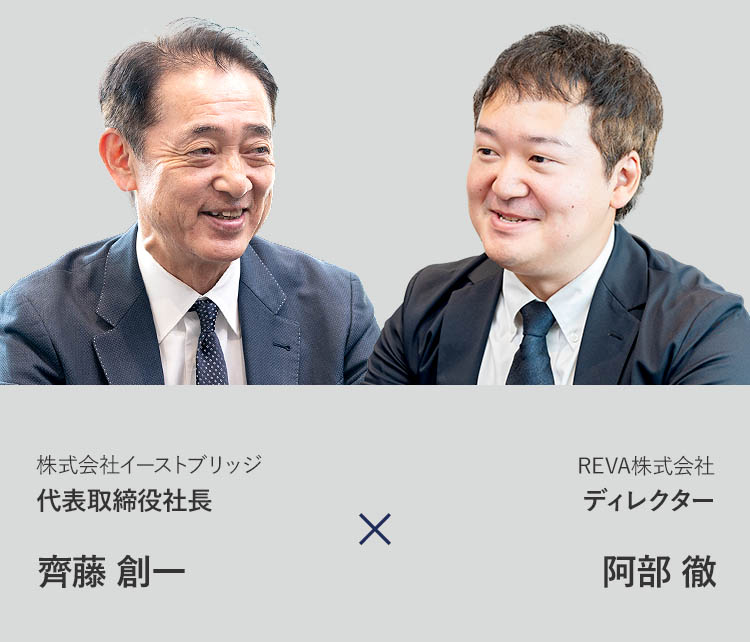
創業31年目のM&Aで異次元の事業拡大へ。
外国人向けモバイル事業から外国人総合支援事業へ展開
外国人留学生向けの携帯電話販売事業で業界トップの株式会社イーストブリッジ。創業から30年以上、代表取締役社長の齊藤創一氏は「日本とアジアの架け橋になる」という理念のもと、国内外に拠点を広げながら事業を成長させてきた。さらなる事業拡大と後継者育成のためにM&Aを決断。同氏と譲受企業REVA株式会社の阿部氏に、M&A成立の経緯や今後の展望を伺った。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社イーストブリッジ
- 所在地
- 東京都台東区
- 設立
- 1994年
- 事業内容
- 外国人留学生を主対象とした通信機器、
インターネット回線販売、不動産賃貸仲介、日本語学校への紹介事業 - 従業員数
- 247名(アルバイト含む)
- M&Aの検討理由
- 将来的な後継者育成のため
事業領域の拡大のため
-
譲受企業
- 会社名
- REVA株式会社
- 所在地
- 東京都千代田区
- 設立
- 2021年
- 事業内容
- 事業投資会社
- 従業員数
- -
- M&Aの検討理由
- -
顧客に徹底的に寄り添う30年で築いた信頼
まずはイーストブリッジ様の事業内容と創業の経緯について教えてください。

イーストブリッジは「日本とアジアの架け橋になりたい」という理念で立ち上げました。創業は今から31年前にさかのぼります。当時の日本はバブル崩壊の直後で、人材不足が少しずつ話題になり始めた時期で、特に技術系の人材は日本人だけでは採用が難しくなり、外国人採用が注目されるようになっていました。私は前職のリクルート時代から「いつかは起業する」と決めていまして、入社時に上司にもそう宣言していたのです。
学生時代からイベントの企画やマスコミの下請け業務などを経験し、自分で事業を作ることに魅力を感じていました。リクルートでは営業の基礎を徹底的に仕込まれ、顧客課題に正面から向き合う姿勢や「挑戦しながら考える」といった思考法を叩き込まれました。この経験が今の会社の文化にも息づいています。
独立のタイミングは、ちょうどアジア経済が成長し始めた時期と重なっています。欧米ではなく、日本と関係が深まっていくアジアに目を向け、優秀な人材を日本に紹介するビジネスを立ち上げようと決めました。最初は自宅マンションの一室に机と電話を置いただけの小さなスタートです。資本金もなく、法人格を取得する費用も捻出できなかったため、「留学生を支援する会」という民間団体の名義で営業を始めました。
まず取り組んだのは徹底したヒアリングです。大学のキャンパスに出向いて留学生と会い、何に困っているかを一人ひとりから聴き取りました。多くの声が寄せられたのは、「就職情報が少ない」「履歴書の書き方や面接のやり方がわからない」「保証人がおらず住まいを借りられない」などでした。特に生活上の悩みは多岐にわたり、国際電話料金の高さも切実な課題でした。私は「一度に全部は解決できない。できるところから始めよう」と思い立ち、提供するサービスを国際電話と就職情報の二つに絞りました。
国際電話の事業では、当時参入したばかりの通信会社のサービスを学校で紹介し、無料でかけられるキャンペーンを行って契約を獲得。これが通信分野に足を踏み入れるきっかけでした。その後、プリペイドカード、インターネットサービスへと取り扱いを広げ、最終的に携帯電話契約の販売代理へと発展しました。
通信事業を成長させていくなかで、どのような苦労や工夫があったのでしょうか。

外国人顧客は、日本語が読めず請求書を破棄してしまったり、銀行引き落としを嫌がって支払いが滞ったりと、知識不足が原因でトラブルになるケースが多くありました。イーストブリッジは外国語を話せるスタッフを採用し、請求方法や携帯の使い方を母国語で丁寧に説明しました。営業マンではなく「日本に来た先輩」として後輩に教えるスタンスで、信頼関係を築いていったのです。この取り組みによって、料金の滞納やトラブルが減り、通信会社からは「このやり方をもっと広げてほしい」と頼まれたことで、東京・大阪だけだった拠点を全国に拡大していきました。
現場では単なる通信契約のサポートにとどまらず、生活全般の相談に対応しています。社員は通訳の役割をしたり、日本の習慣を教えたりと、顧客に寄り添い続けています。
現在は通信と外国人向け人材紹介の二本柱が事業の中心です。社員の9割が外国籍ですが、公用語は日本語です。社内では多国籍メンバーが互いの文化を紹介し合い、時に価値観の違いで衝突しながらも共鳴して成長しています。
後継者不在のなかでの体調不安をきっかけに決断したM&A
M&Aについて考え始めたきっかけは何でしたか。

本格的にM&Aの検討を始める数年前から、会社の未来について漠然と考えていました。私の子供は会社を継ぐ意思がなく、社内にも明確な後継者候補はいません。そんな状況の中、2024年に私は大病を患い入院しました。幸い大事には至らなかったものの、仕事を一時的に離れざるを得なくなったことで、会社が自分抜きでも回る体制を早急に整えなければと強く感じました。それまで「あと5〜10年は自分が現役で続けられるだろう」と思っていましたが、その前提が崩れてしまったのです。
もう一つ、私には長年の夢がありました。通信事業だけではなく、金融・不動産・教育など、日本に暮らす外国人が必要とするあらゆるサービスを提供する事業を作りたいということです。全ての在留外国人に、「イーストブリッジの社名を知ってもらいたい」という想いがありまして、社員にも「いつかはそういう会社にしよう」と言い続けてきました。しかし、通信以外の領域はなかなか育たず、夢の実現は遠いままでした。
そこで私は、「自分一人の力でやれる範囲は限りがある。他社の力を借りれば、もっと早く、もっと大きなことが実現できるかもしれない」と考えるようになったのです。
こうして私の中で、後継者問題の解決と夢の実現という二つを同時に叶える手段としてM&Aが現実味を帯びてきました。
M&Aに向けて、具体的にどのような行動をされたのでしょうか。

退院して1〜2カ月のうちに、以前に出会ったM&Aキャピタルパートナーズの山田さんに連絡しました。実は数年前に山田さんとお会いし、いくつか候補の企業を紹介していただいたことがあったからです。その時は私自身がまだ事業承継を急ぐ気持ちになれず、話は自然消滅しました。ところが今回、電話をすると山田さんは私のことを覚えていて、「じゃあ、すぐ動きましょう」と即答してくれました。
山田さんは、単に譲渡先を紹介するだけでなく、私の立場に立って「会社の未来にとっての最善とは何か」を一緒に考えてくれました。良いことも悪いことも隠さず話しても大丈夫だと思えましたし、提案のたびに納得感のあるアドバイスをいただきました。パートナーとして伴走する姿勢が心強かったですね。
現場で汗をかく姿勢と事業拡大への思いが共鳴
ここからは譲受企業であるREVA株式会社の阿部様に参加していただき、お話を伺います。REVA様の投資方針と体制について、ご紹介いただけますか。

REVA(Re Value=価値の再定義)という社名のとおり、事業と人・組織の価値を再定義し、その潜在力を引き出すことを理念にしています。設立は2021年2月で、本格的なファンド運用は2023年3月からです。現在は約300億円規模のファンドを運用し、住友商事から一部出資を受けつつも、意思決定はREVA側が担うという独立系の体制をとっています。
私たちは自らをファンドにとどまらない“事業投資会社”として位置づけています。特徴はオペレーションに踏み込んで価値を引き出すハンズオンです。メンバーも金融だけではなく、自動車エンジニアリング、工場ロジスティクス、デジタル化など各機能に特化した実務家が多数在籍し、戦略コンサルタントもいます。さらにDXコンソーシアムで外部の最新知見を束ね、事業開発力と実装力を併せてご提供しています。事業開発から展開まで一貫して手掛ける”総合商社のミニ版”のイメージですね。
加えて、投資先にはメンバーが常駐し、現場で伴走する体制を敷いています。私自身も現在イーストブリッジに常駐し、REVAのもう一人のメンバーと一緒に日々の経営や現場の課題に並走しています。単に月次会議で数字を確認するだけでなく、どこにボトルネックがあるか、どう改善すればいいかを現場で検討し、必要に応じて人材や外部の専門家をアサインして実行に移しています。こうした伴走型の支援により、「投資会社=数字を見て口を出すだけ」という従来のイメージを覆すことができているのではないかと思います。
イーストブリッジの最初の印象はどうでしたか。

正直、すぐには腹落ちしませんでした。日本の外国人市場が確実に伸びることは直感できましたが、なぜそこでイーストブリッジが強いのかを理解するまで時間が必要でした。そこで有識者へのヒアリングや公開情報の読み込み、社内の打ち合わせなどを重ね、およそ1カ月かけて解像度を上げていきました。
見えてきたのは、外国人市場には「これさえやれば勝てる」という定石がないことです。国籍・文化・価値観が多様であって、個々のマーケットは小さく見えます。一方でイーストブリッジは、留学生の通信分野でトップポジションを築き、日本語学校や留学エージェントなどとの強固かつ広範なネットワークを持っています。そこに至るまでの現場の積み上げと試行錯誤こそが競争力の源泉であると理解しました。日本全体の成長が鈍いなかでも、この市場は右肩上がりで伸びしろが大きい。ここにREVAの事業開発・デジタル・人材の力を重ねれば、さらに成長を加速できると、確信しました。
M&Aの検討段階で重視された点を教えてください。
私たちは検討対象の企業を“査定する”よりも“成長の仮説を描く”ことから始めます。初期から「この施策を打てばどう伸びるか」「未開拓の余地はどこか」といったポテンシャルの具体化を、齊藤社長と率直に議論しました。
実務では現場に入って一緒に動くのがREVAの流儀です。別案件の実例も踏まえつつ、イーストブリッジでも契約前から頻繁にお会いし、将来の具体策まで踏み込んで話し合いました。このハンズオンの感覚が、イーストブリッジの現場主義と自然に噛み合ったと感じています。
最終的に、齊藤社長はなぜREVAを選ばれたのでしょうか。

決め手は、「一緒に事業を築き上げてくれる相手」と感じたことでした。株式の売買益だけを目的にせず、同じ土俵で汗をかき、アポイント獲得などの実務まで手伝ってくれるという姿勢に驚きました。もちろん大手ネットワークの強さも魅力ですが、一番心に響いたのは伴走の方針です。
既存の取引先やパートナーへの影響については、いかがでしょう。
一般論として、ファンドが入ると短期志向になるという懸念はあります。私たちの主要パートナーである通信キャリア各社も、当初は慎重に様子を見ていたかもしれません。ただREVAと接していると、短期の数字合わせではなく、長期の価値づくりに重きを置いていることが伝わっていくと思います。従来のやり方や方針を尊重しつつ、そこに“新しい武器(強み)”が加わるといった感覚です。ご一緒する時間が積み重なれば、取引先やパートナーにこれまで以上の価値を提供できると自信を持って言えます。
お二人の関係が深まった印象的な場面があれば、教えてください。

齊藤社長は誠実で、契約する前から「会社のことを全て知ってほしい」と、良い点も課題も率直に共有していただきました。ある日、お酒が得意ではない社長のほうから二次会にお声がけくださることもあり、お人柄の温かさやお茶目な一面に触れて、「この方となら深くやれる」と実感しました。
阿部さんは私の立場で考え、良いことも困りごとも正面から受け止め、具体的な方策に落としこんでくれます。距離感でいえば、“相談相手”を越えて“同じ課題を一緒に考えるパートナー”に近いですね。仲介の山田さんも私の本音を引き出し、REVAへ適切に伝えてくれました。
成約時のお気持ちはいかがでしたか。
M&Aという未知の領域への不安が全くなかったわけではありませんでしたが、期待と安心が上回っていたのは事実です。REVAからは、短期で“売り抜く”発想ではなく、長期的に価値を高める姿勢が一貫して伝わってきました。「良い文化を守りながら、新しい文化を融合する」という取り組み方が、社員や取引先に向けた私の約束にもなると感じました。
私たちのファンドは有期限ゆえに、関与の期間中にベストオーナーを作り、次の最良の持ち主へつなぐという責任があります。投資としての成功は前提として、従業員・取引先からも「REVAと組んで良かった」と言っていただけることを目指します。三方よしでなければ、私たちのビジネスモデルは成立しません。契約前からの話し合いで積み上げた相互理解を土台にし、全ての関係者が幸せになるような事業を築いていけるよう、気持ちが引き締まる思いでした。
“異次元の拡大スピード”と伴走の安心感、そして次の世代へ
M&A成立後、社内外でどんな変化が起きましたか。

想像以上のパワーをいただいています。以前は取引実績のない大手企業に連絡しても、受付で止まってしまうことが多くありました。ところが今は、最初の面談から役員クラスにアポイントが入り、案件が一気に前に進みます。これまで「課長まで会えたら御の字(おんのじ)」だったのが、意思決定層に直接届く感覚があります。REVAのネットワークによって、取引のスタート地点が全く違うところに置かれました。
現場の手応えとしても、日本語学校様の新規開拓がこれまでにないスピードで進んでいます。以前は現場スタッフが地道に訪問しても門前払いだった学校へも、今ではオーナーレベルの紹介で入れるようになりました。こちらが「営業したい」と思っていた矢先にキーパーソンが次々と現れ、従業員からも「以前は落とせなかった訪問先と次々に取引が始まった」と驚きの声が上がっています。まさに“異次元の拡大スピード”に入ったのを実感しています。

住友商事からも出向メンバーが入ってくださっていまして、そのネットワークもフルに活用しています。役員層への紹介や取引先との接点が一気に広がることで、ビジネス立ち上げまでの時間が劇的に短縮されました。こうした「ショートカット」がいくつも重なることで、通常の会社ではなかなか経験できないスピードで案件が動いています。
もちろん、ネットワークの力だけではありません。現場に入っているメンバーが「どうすれば事業を伸ばせるか」を日々考え、行動しながら新しい商機を作ることで、その積み重ねが目に見える成果につながっています。
社内の管理体制にも変化はありましたか。
はい。人事やシステムなどの弱さは中小企業にありがちな課題ですが、そこに専門家が常駐する形で伴走しています。顧客データベースや契約情報の整理・一元管理が進み、「どの取引先に、どの手を打つべきか」「どこにボトルネックがあるか」を瞬時に把握できる仕組みが整ってきました。これまでのイーストブリッジの規模では難しかった体制です。
さらに現場では、社員が「留学生の生活まで支援する」というイーストブリッジの強みをそのまま活かし、アポイント取得や提携づくり、商品開発の場づくりまで、REVAさんが実務として一緒に動いています。数字を眺めるだけでなく、手と足が動いているという実感が、日々の意思決定を加速させています。
M&Aを検討される経営者の多くが悩むのは、「社員は幸せになれるのか」という点だと思います。私たちのケースでは、パートナーが加わったことで企業力がさらに強まり、総合力で社員の将来を支えられる実感があります。まだ道半ばですが、今はむしろ「これからもっと社員が幸せになれる」と思える段階です。
実際、少しですが給与も上がりました。こうした変化は従業員のモチベーションにもつながっています。
REVAとしては、イーストブリッジのどのような「良さ」を残したいですか。
多国籍・多様な価値観が一つの目標に向かう文化です。国籍やバックグラウンドが多様で正解を一括りにできないなか、“現場で解を作る習慣”が根づいています。日本語学校様へのアプローチも国や個人に応じて最適化して実績につなげてきました。この文化は今後も守るべき強さだと思います。
もう一つは結束力の強さです。先日、泊まりがけの社員総会に出席しました。投資会社のメンバーだからといって壁を作らず、夜通しゲームや議論で盛り上がりました。ただ仲が良いだけではなく、チームワークがビジネスの成果にもつながっています。この一体感は、齊藤社長が築いてきた重要な資産です。
今後の事業拡大について、展望を聞かせてください。

まずは外国人向け通信での圧倒的地位を追求し、誰もが名前を知っている会社にしたいと思います。並行して、金融・不動産など生活の基盤領域に広げ、外国人の困りごとと日本企業の困りごとをつなぐ解決策を提供していきます。
戦略の順序としては、まず通信でダントツNo.1を固めます。キャリアの皆様の表彰実績など手応えはあります。次いで、人材に続く第3・第4の柱として不動産・金融・付帯サービスを着実に立ち上げます。市場環境としても、留学生はすでに40万人規模に達し、特定技能を含む就労領域の拡大や制度の見直しが続いている状態です。需要は構造的に増えますから、単なる拡大ではなく、社会を支える事業体として多面的に取り組みたいと思います。
認知の点でも、イーストブリッジの社名が出る回数は増えている実感があります。ここは引き続き推し進めながら、“外国人向けならイーストブリッジ”という認知を確立していきます。
事業承継の不安について、変化はありましたか。

大きく変わりました。極端な話ですが、もし私が突然現場に出られなくなっても、以前のような大混乱にはならないという手応えがあります。後継者は社内育成と外部採用の両輪で検討中ですが、REVAが実務の内側に入り、必要な人材の要件定義からオンボーディングまで一緒に考えてくれます。私一人で抱えない体制ができたことで、将来に向けた安心感は明らかに増しました。
社員目線でも、少しずつ待遇が改善し、会社の将来像が具体化しました。「会社の価値をどう高めるか」を土日や深夜まで考える仲間が増えています。以前は私一人の頭の中にあった悩みや構想が、今はチームの言葉になり、行動になっている。これは本当に大きい変化です。
事業承継の具体的なスケジュール感はいかがですか。
すでに人材の採用・育成を開始しており、2025年から2026年には一定のイメージを描きたいと考えています。ただ、プロパーの強み・弱み、外部登用の強み・弱みを見極め、納得感のある選び方にこだわります。
「人をあてがう」だけであれば難しくないのですが、肝心なのは入社後の活躍です。だからこそ、私たち自身が一定期間、現場に入り肌感を持つことを重視します。そのうえで実際に候補者様と会い、一緒に悩み、会社として納得できる選定を支援します。もちろん、齊藤社長とご一緒に、持続的に経営できる体制を整えていきます。
仲介担当の山田について、今回どのような感想を抱きましたか。
レスポンスが早く、守備範囲が広いと感じました。候補先の紹介はもちろんとして、分社化のようなM&Aとは直接関係のない周辺テーマでも、専門家を束ねて実務的な助言をいただきました。時間外でも丁寧に伴走してくださり、交渉の着地点を双方にとって妥当な形に整えてくれます。いわゆる「どちらかが勝つ・負ける」ではない合意形成の設計に長けている印象です。スケジュールがタイトな局面でも、一つひとつのステップを確実に前に進める推進力があり、非常に助けられました。
仲介会社は多様ですが、山田さんのプロフェッショナリズムと公平性、そして実行力の強さは、今回の成約の重要な要因でした。お互いの利がある点に着地させるのは一見すると簡単なようで、実は非常に難しい仕事です。本当に感謝しております。
最後に、M&Aを検討する経営者に向けたメッセージをお願いします。
偉そうなことは言えませんが、私の実感としては、一人の力では越えられない壁を越えられるのがM&Aでした。同じ目線で会社の未来を考える仲間ができ、スピードと安心感の両方が手に入ります。イーストブリッジのような結果が一般的なケースかどうかはわかりませんが、私はやって良かったと心から思っています。
妥協せず、自社に合う相手を探すことをおすすめします。私たちは中堅・中小企業のフルポテンシャルを引き出すことにこだわっていますが、世の中には投資会社やファンドが他にもたくさんあります。課題や悩みに合う相手を、まずは信頼できる仲介会社様と一緒に見極めてください。M&Aは“卒業”にも“新しいスタート”にもなり得ます。社員の幸せまで含めて三方よしの結果となるよう、悔いのない決断にしていきましょう。
それともう一つ。私たちと同じく、外国人向けの事業を営むオーナー様がいらっしゃれば、ぜひご連絡をいただきたいです。事業承継や将来像の情報交換をできたらと思います。補完関係のシナジーによって、もっと速く、遠くまで行けるはずです。自信を持ってそう言えます。掛け合わせのスピード感は、もう体験済みですから…。ぜひ、外国人向けの事業の展望について意見交換出来れば幸いです。

文:山田 悠記 写真:壬生 マリコ 取材日:2025/9/18
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。











