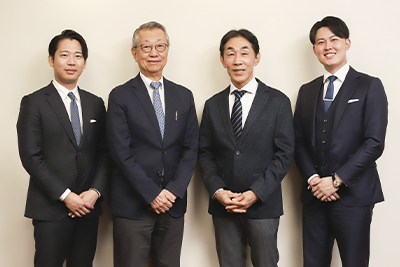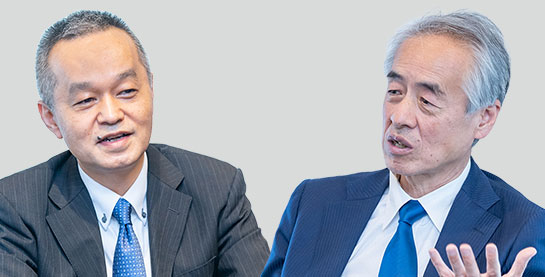
×
譲渡企業も譲受企業も平等に、
互いに尊重し合えるM&A
創業以来、幅広い金融ビジネスソリューションを提供する株式会社プレスティージ。顧客からも厚い信頼を得てきた優良企業が、なぜM&Aを決意することになったのか。元代表取締役社長である伊藤 憲義氏と、譲受側のセイコーソリューションズ株式会社の代表取締役社長 関根 淳氏にこれまでの経緯と未来についてうかがった。
徹底した“現場主義”と“顧客第一主義”により絶大な信頼を得てきた

元々、ソフトウェアを開発・販売する企業に勤務していたのですが、そのクライアントである金融機関に常駐し、プレイングマネージャーとして大きなプロジェクトを任されていました。
業務が拡大するにつれ、会社の方針が現場やお客様の実情にマッチしていないと感じるようになりました。もちろん、メンバーを束ねる立場として、当時の経営陣にもかけあってきましたが、なかなか自分の思いは届きません。
そこでいきついたのが“自分自身でやる”という選択でした。非常に嬉しかったのが、当時のお客様、すなわち常駐先の金融機関が、私の背中を押してくれたことです。もちろん、勤めていた会社に承認を得たうえではありますが、私がメインで受け持っていたプロジェクトを継承するかたちで、新しい会社をスタートさせることができました。あれは2003年の夏、私が35歳の時でした。
当時、ビジネスという感覚ではなく、しっかりお客様と向き合い、貢献しようという意識がありました。また、お客様から褒められる、認められることに大きなやりがいを感じていました。「伊藤さん、すごい」と言われることが最大のモチベーションになっていましたし、そのために積極的に仕事に取り組み、お客様の役に立とうと考えていました。その結果、お客様から信頼を獲得していったのだと思います。

創業当初から“現場主義”、そして“限られたリソースを一つのお客様に全て集中すること”を貫いてきました。時間をかけることで私たちはノウハウを獲得し、結果的にお客様から信頼を得ることができます。
そういった考えのもと、とにかく創業時からお世話になってきた大切なお客様だけに絞って仕事をしていたため、ノウハウも信頼も唯一無二のものとなっていきました。また、私個人の姿勢であった“お客様のために真摯に取り組む”スタイルに共感してくれる人だけを採用していけば、組織的に信頼を得られるであろうと考えました。
結果的には、そのスタンスが組織の文化、風習として継承されてきたように思えます。
若手社員が成長し、組織が飛躍するきっかけを探していた。
創業から10年間は、私自身がプレイングマネージャーとして複数のプロジェクトを担当し、一エンジニアとしても並行して活動していました。しかし、このままではリーダークラスの社員たちが次のステップに上がれないと気づき、そこで現場から一線をひくことを決意しました。マネージャー制度を設け、組織的に業務を遂行する体制を構築しました。当時、8名いたマネージャーたちが成長し、活躍していけば4~5年後には300名規模の会社になるだろうと楽観視していたのですが、蓋を開けるとそうではありませんでした。会社が50名規模になった頃から、組織としての停滞感が生まれました。社員数は増えたり減ったりを繰り返す状態に。そこから一歩踏み出し、停滞感を打破するきっかけを探していました。

同時にその頃から漠然と、会社を誰かに任せたいと考えるようになっていました。50代にさしかかったばかりでしたが、事業を継ぐために必要な時間を確保しようと考えると、5~10年ほどの時間が必要になります。そういった観点から、かなり前より、“50を過ぎた時にイメージを持っておかなければならない”という感覚はありました。その時に、社内のメンバーを見渡してみても、「君に任せる」と言えるメンバーがいなかったのは事実としてあります。さらにネットで調べてみると、事業承継には個人保証など“お金の問題”が付きまとうことがわかります。事業を継ぐことが容易でないことに気づき、悩んでいたものの、まだ先の話として遠ざけようとしていたのも事実です。
その頃、多くのM&A仲介会社からダイレクトメールが届くようになっていました。当初は中身を見ることもなく、そのまま捨てていたのですが、何となく“M&Aはどうだろう?”と、気になり始めたタイミングでした。そんな時、ちょうどM&Aキャピタルパートナーズさんから電話がありました。“1社ぐらいだったら話をきいてみてもいいだろう”という軽い気持ちでお会いすることにしました。

“意外と若い方が来たな”と感じると同時に、ものすごく誠実な印象を受けました。一番良かったのは、営業的にゴリゴリ押してこないこと。実はその後、他の仲介会社の方にもお会いしたのですが、押しが強い担当者ばかりだったので、その差は鮮明になりました。また、終始、「あくまでM&Aは選択肢の一つである」と説明してくれました。そこで、M&Aに対して抱いていた、若干ネガティブなイメージは払しょくされ、“選択肢のひとつとして考えるべきなのではないだろうか”と思うようになりました。
本格的にM&Aを考えようと思ったのは、昨今のDX推進の波に乗り、去年あたりから業界全体が盛り上がってきたことが、きっかけとなりました。恐らく、この波は長期的なものになるだろうと予測しました。実際、私の会社も仕事が膨らみ始めていました。しかし、その一方で業界全体において深刻な人材不足が発生していました。私の会社でも人材確保の難しさを感じていました。私がこの業界で30年生きてきた中で経験したことのないうねりが起きていると感じました。私や次の世代のマネージャー連中はそこそこの業績をあげていれば、食うに困らない、仕事は選べるほどあるという状態ですが、その次の世代である今の中堅や若手がまだ成長していません。若手、中堅を成長させるには、仕事を増やし、彼らの下につく更に若手を増やすことが必要です。しかし、人材不足が続く以上、やみくもに仕事を増やすことはできません。できることが限られている中で、スピード感をもって組織を成長させることは、限りなく難しいと感じていました。その時にM&Aが急に現実味を帯びてきたと感じました。どこか大手の力を借りなければ成長できないと考えて、すぐに決意。定期的に情報交換をしていたM&Aキャピタルパートナーズにお声がけさせていただきました。
実を言うと、半ば強引に営業を掛けられていた仲介会社もあって、結果的に3社競合というカタチになりました。皆さんに株式評価をしてもらったのですが、M&Aキャピタルパートナーズ以外の仲介会社の提案書にはいくつかの疑問点がありました。ところがM&Aキャピタルパートナーズが作成した書類には、その疑問に対するすべての回答がすでに記載されていました。また、M&Aありきではなく、「最終フェーズでお断りする可能性は必ず捨てないでください」とアドバイスをくださいました。その言葉で誠実な姿勢を実感しましたし、それが最後のトリガーとなりましたね。もっとも誠実で、信頼できると確信できたのでM&Aキャピタルパートナーズをパートナーに選びました。
委ねられるのであれば、私が身を引くということが大前提としてありました。M&Aの形としては大きく分けて2つあります。それは資本を締結するが、オーナーは変わらず引き続きバックアップを行い、経営を続けるパターン。そして、オーナーが完全に身を引くパターン。私は後者を選びました。なぜなら、私が続けると会社を変えることができないと考えたからです。そのまま続けていては、良くも悪くもプレスティージがその時のプレスティージのままとなってしまい、私が願う社員の成長を阻害してしまうと思いました。ですので、M&Aで委ねるのであれば、私が身を引かなければ意味がありません。しかし、身を引くとなると将来が安定しなければ引くに引けません。私自身が経済的な部分で納得ができ、さらに社員の成長を委ねることができるお相手を選びたいという思いがありました。
伊藤様からご自身の会社に対する思いを聞かせていただいて、何としてもご希望に沿ったお相手をご紹介したいと考えました。前提として従業員の方が縛られない、譲渡企業も譲受企業も尊重し合えるという条件があり、かつ、ご自身は身を引いて会社を委ねたいというお話から、親会社・子会社という親子意識がなく、相手に対して対等で敬意を持っていただける会社である必要があると考えました。そして、セイコーソリューションズ株式会社をご提案しようと考えました。
互いに尊重し、学び合えるM&Aを求めていた。
お話を聞かせていただければと思います。M&Aに対する基本的なお考えからお聞かせください。

M&Aを実行するにあたり、もっとも重要視するのは、社員一人ひとりがどれだけ成長できるかどうかという点です。人が成長するためには、学ぶ情報の総量を増やすことが大切です。しかし、謙虚に学ぶ姿勢がなければ、この情報過多な時代の中で、真に意味のある情報を蓄えることはできませんし、成長することもできません。
学び方も重要です。人は良いもの、良い人に触れて学び成長します。特に人との触れ合いの中から得る学びほど成長に直結するものはありません。M&Aで大切なのは、別々の組織が一緒になることで、お互いが尊敬し、お互いに影響を受けることです。ですから、それが可能な会社の人たちと一緒になりたいという強い意向があります。
互いに学べる会社を見極めるには、それは社長とお会いすればわかります。会社は社長の器以上に大きくならないとよく言いますが、明らかに社長の色が濃く出ます。そういった意味でもトップ会談は重要です。お会いした時、直感的に伊藤さんは“長らく社員、お客様を大事にしている”と感じましたし、その直感は的中しました。後から知った事実ですが、私がプレスティージのお客様のところにご挨拶に行ったら、皆さま口を揃えて絶賛していました。思った以上にその信頼関係は強固なものでした。
私の中では、はじめてお会いし、伊藤さんの話を伺った時に即決していました。もちろんエビデンスとしてデューデリジェンスは行いますが、進める段階で差異がでるのは当たり前のことですし、そこに目くじらを立てるつもりはありませんでした。

業務領域の違いから、正直、直接お会いするまでは、M&Aのお相手としてのイメージはありませんでした。ところが関根社長とお会いして10分ぐらいで、95%の決心がつきました。言葉では説明できませんが、ほぼ確信に近い感覚を得ました。「トップ面談は大事」という関根社長のお話に同感します。お会いするまでは様々な資料の中で、文字として表現された情報を元に想像したり考えたりしていたに過ぎませんでしたが、会話を交わした10分間で、それらが全て吹き飛ぶほどの強烈な印象を持ちました。
お話を伺えば伺うほど、魅了されていきましたし、関根社長が目指している方向性やおっしゃることに強く共感を覚えました。例えば、IT企業としてダイバーシティを目指し、それはお互いが尊敬して組み立てていくものであるという考え。また、M&Aをしても社員は誰もが平等であるという考え方にも感銘を受けました。
正直言って、関根社長はすごい人ですが、会社組織としてどうなのかという不安はありました。その不安を解消してくださったのがトップ面談で関根さんと同席された経営企画部の半田さんでした。このような若い方がM&Aの大事な場面に同席し対応していることに、セイコーソリューションズという組織自体が今後もさらなる成長を目指し、着実にそこに向かって歩んでいる姿勢を読み取りました。その後、色々な社員の方とお会いしましたが、どなたも良い方ばかりで、関根社長がおっしゃっていることを共通意識として持たれていることも理解しました。残りの5%のほとんどを半田さんに埋めていただいたという感覚です。
お二人がおっしゃるようにトップ面談の場で全てが決まった空気を感じました。伊藤さんにお会いする前に、M&Aキャピタルパートナーズさんから「伊藤さんは寡黙な方である」と伺っていましたし、うちの関根も喋るタイプではないため多少、不安を感じていたのですが、トップ面談では話が弾み、その時点で“うまくいくのではないか”と感じました。本当にトップ面談は重要なポイントになったと思っています。
本来のダイバーシティは、互いに尊敬することで生まれる。

基本的な初動は、伊藤さんが築き上げてきたプレスティージの良さ、年月を重ねて積み上げてきた顧客との信頼関係を、弊社の社員に見せることによって、“自分たちもこういうふうになりたい”“まだまだ足りない”ということに気付かせるところから始めたいと思っています。それについてはダイバーシティ&シナジーをミッションにしている経営企画部のメンバーが取り組んでいきます。まさにM&Aはダイバーシティ実現の手段であり、お互いに成長する機会です。M&Aだからといっても吸収する、親子関係になるという考えは一切ありません。大きな船を作るつもりはなく、ゆるやかに連なる船団のイメージで、みな平等です。平等感はシナジーを起こす上で最も重要な要素だと思います。本来のダイバーシティは男性、女性、国籍に関係なく、互いに尊敬することで生まれるものです。

東京を離れ、自然を感じることができる場所で、まずは体の健康を取り戻したいと思っています。会社を譲渡すると妻に話した時に、「もういいんじゃないの」と言われましたし、母親に報告した際にも「よかったね」との反応がありました。それだけ辛そうに見えていたのか…と改めて思いました。
妻が旅行好きなため、仕事していた時に行けなかった場所に行きたいと思います。健康を取り戻すことができても、せいぜい75歳まで生きていればいいかと思いますし、そう考えると決して早すぎるリタイヤではないかなとも感じています。元々は社員の成長のためと考えて決断したものの、実際にやり始めて思ったのは、もっと早く取り掛かるべきであったなということ。それだけは反省点としてありますね。
色々な仲介会社がありますが、IT業界のM&Aに対する知識がどれだけあるかどうかは重要です。その点でM&AキャピタルパートナーズはIT業界に長けており、信頼できると感じています。そうでないとPLとBSだけ見て終わりになってしまいます。数字だけで判断されては、シナジーを生む出会いを実現できないでしょう。

率直にM&Aキャピタルパートナーズで良かったと感じています。M&Aは、普通は一生に一回、多い人でも二回ぐらいしか経験できないでしょうから残念ながら比較はできませんが、M&Aキャピタルパートナーズがパートナーだったからうまくいったと思っています。
非常に迷われるとは思いますが、これは決断であり、自分の意思であり、それを常日頃どこまで本気で考えているかどうかで見えてくるものがあるはずです。経営は簡単なものではありません。様々な荒波があり、それを乗り越えてきた経験から経営者としての考え方、リーダーシップが醸成されるはずです。創業から今までに達成した意思や思いを大事にしたいし、そこから尊敬が生まれます。私は大きい企業を作りたいわけではありません。ダイバーシティ&シナジー、互いに学んでいく。それぞれが互いに成長できる企業にしたいと思いますし、そのような思いを持って社長様に育てられた企業の皆様と一緒になりたいと思います。

(左から)関根 淳 様、伊藤 憲義 様
文:伊藤 秋廣 写真:伊藤 元章 取材日:2022/4/28
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。