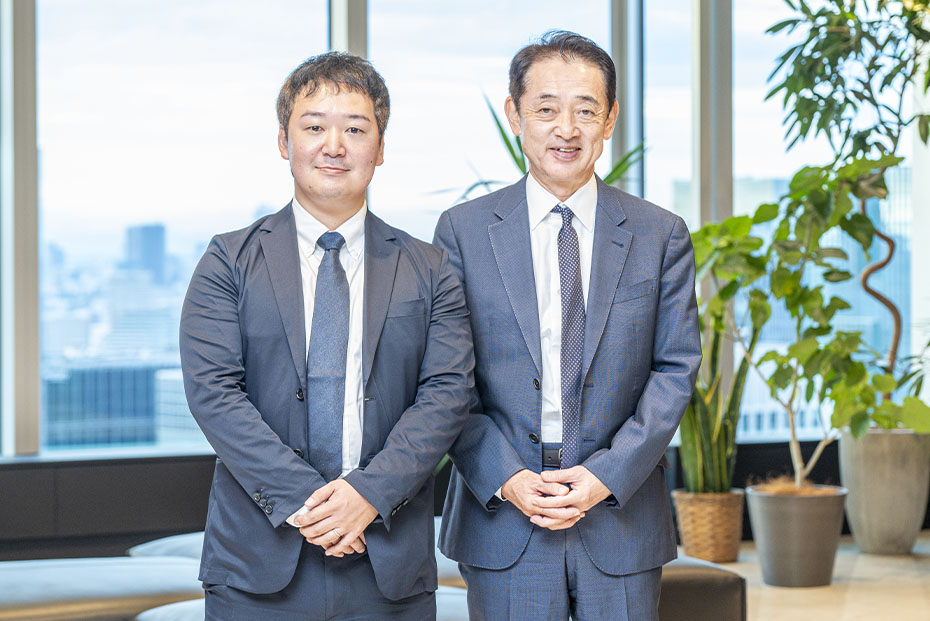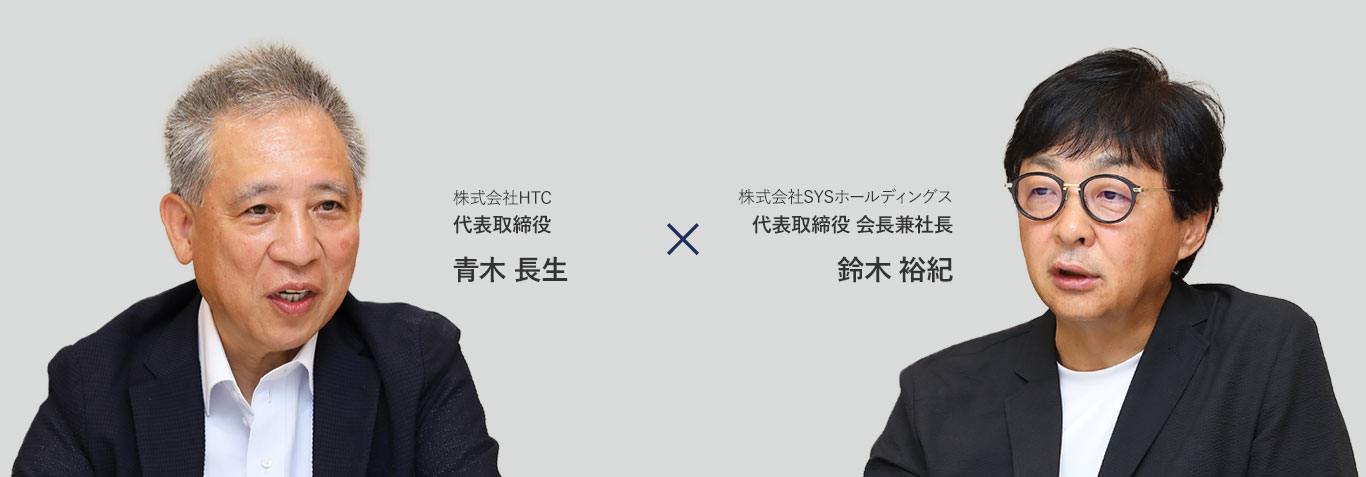

会社と従業員を守るため、事業承継の葛藤の末にたどり着いた
「経営同盟」という名のM&A
2009年の創業以来、組込・制御システムのソフトウェア開発で成長を続けてきた株式会社HTC。社会の変化に柔軟に対応し、多様なニーズをとらえてきた同社は、2025年に株式会社SYSホールディングスへの株式譲渡を決断した。その経緯と今後の展望について株式会社HTC 青木 長生 様、株式会社SYSホールディングス 鈴木 裕紀 様に伺った。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社HTC
- 所在地
- 大阪府大阪市
- 設立
- 2009年
- 資本金
- 1,500万円
- 事業内容
- 組込み系ソフトウェア開発、制御系システム開発、Web系システム開発
- M&Aの検討理由
- 後継者不在のため
-
譲受企業
- 会社名
- 株式会社SYSホールディングス
- 所在地
- 愛知県名古屋市
- 設立
- 2013年
- 資本金
- 4億1,799万4,000円
- 事業内容
- ソフトウェアに関わるコンサルティング、システム構築、サポートの総合情報サービス
- M&Aの検討理由
- 事業の領域拡大のため
築いてきた信頼関係を礎に右肩上がりの成長を実現したソフトウェア開発事業
創業の経緯と事業内容を教えていただけますか。

前職ではソフトウェア開発に携わっており、電話交換機や通信ケーブルといった基幹的な大型通信システムの構築が主な業務でした。特に印象深いのは、ロサンゼルスオリンピックを東京で同時放映するため、グアムを経由して千葉までケーブルを敷設するプロジェクトの一部を担当したことです。その後、携帯電話の普及に伴い、基地局や交換機などのシステム開発を手がけるようになりました。黒電話の時代やアナログ交換機からデジタル交換機、そしてISDN(統合デジタル通信網の略称で、デジタル方式で音声やデータを伝送するための通信技術)へと進化していくなかで、常に技術革新の最前線に立ち会えたことは、私にとって挑戦の連続であり、大変貴重な経験になったと思っています。
一部上場企業という大きな組織で大規模な仕事をさせてもらう環境にありましたが、次第に「利益追求よりも技術で社会貢献し、その結果として利益がついてくるような仕事がしたい」という思いが強くなりました。50歳を目前にして独立を決意した最大の理由は、“技術者としての考え方”に行き着きます。会社が大きくなれば利益を追求するのは当然ですが、私は「まず技術で社会貢献し、その結果として利益がついてくる」という形を実現したかったのです。
前職の組織の方向性に対する行き詰まりを感じるなか、「新しい挑戦をするなら50歳になる前が最後のチャンスだ」という思いもあり、49歳で「自分でやるしかない」と独立を決意するに至りました。当然、家族からは「なぜ今そんなリスクを冒すのか」と猛反対されましたが、私の決意が揺らぐことはありませんでした。ちょうどその頃、知人から「3年間、うちの会社を経営してくれないか」というお話をいただきました。その経験は、独立に向けて経営者としての実務を本格的に学ぶ、またとない機会となりました。そして、いよいよ自分の会社を立ち上げるというときには、心強い仲間と支援者に支えられました。前職で支社長をしていた私の考えに賛同したメンバーが、各地の支社から集まってくれたのです。また、長年お付き合いのあった取引先の皆様も「頑張れ」と声をかけてくださり、創業当初から開発の仕事をご紹介いただきました。これまでに築いてきた信頼関係が、何よりの力となり、本当に恵まれたスタートを切ることができました。
順調な滑り出しだったのですね。その後の事業の歩みはいかがでしたか。
「このまま順風満帆に進んでいくだろう」と期待に胸を膨らませていた矢先、リーマンショックが世界を襲いました。私たちも例外ではなく、大きな打撃を受けました。頼みの綱だった取引先も経営が危ぶまれる事態に陥り、当時の私たちは実績も乏しく、会社の規模も小さかったため、銀行からの融資もままならない状況でした。その後、約2年間は仕事の受注も思うようにいかず、赤字を経験するなど非常に厳しい時期が続きました。しかし、この最大の危機を救ってくれたのも、過去に築いた“人とのつながり”でした。かつて前職で一緒に仕事をしていた方が、時を経て責任ある立場に就かれており、「自社で初めて伝送システムを受注したものの、ノウハウがないのでぜひ手伝ってほしい」と声がかかりました。当時の私の人となりや技術力の高さを評価してくださったことを、ブランクがあったにもかかわらず覚えていてくれたのです。このプロジェクトを成功させたことを機に継続的なお付き合いが始まり、事業は再び軌道に乗りました。さらに、これをきっかけに、他の企業からも「ぜひ力を貸してほしい」という相談をいただくようになりました。
新しい挑戦にあたって、「大きな利益が見込めないなら協力できない」と断る企業も少なくありません。しかし、私たちはお客様の挑戦を支える機会を最優先に考え、真摯に取り組む姿勢を貫いてきました。その姿勢が信頼を生み、結果として着実な成長へとつながったのだと思います。
60歳を過ぎて発覚した健康問題を機に「会社と従業員を守る」という覚悟を決める
堅調に事業を成長させてこられた中で、どのようなきっかけからM&Aを意識されるようになったのでしょうか。

現在私は68歳ですが、事業承継を本格的に意識し始めたのは、60歳を過ぎてからです。「この会社を次の世代にどうつないでいくか」という課題が、現実的なものとして迫ってくるのを感じていました。その決定的なきっかけは、自身の健康問題です。
数年前、胸に苦しさを覚えて病院を受診したところ、血管の疾患からくる狭心症が見つかりました。医師からは「完治は望めず、薬で上手に付き合っていくしかない」と告げられました。幸い、日常生活に支障はありませんでしたが、その3年後には突発性難聴を患い、2週間ほど入院したのです。
これらの経験から、「もし自分に万が一のことがあったら……」という危機感が、かつてないほど強くなりました。私が倒れた瞬間に会社の経営が止まり、長年苦楽をともにしてきた従業員とその家族を路頭に迷わせてしまうかもしれない。それだけは絶対に避けなければならない、と強く思うようになりました。事業の引き継ぎには、どのような形をとるにしても数年単位の準備が必要です。だからこそ、自分が万全な状態でいられるうちに会社を未来へつなぐ準備を始めなければならないと固く決意したのです。
さまざまな事業承継の選択肢がある中で、どのように検討を進められたのでしょうか。
実は、当初からM&Aを前提に考えていたわけではありません。事業承継にあたっては、「社内での承継」「外部からの人材招聘」「M&A」という3つの選択肢を並行して検討しており、中でも従業員への社内承継を最優先に考えていました。
しかし、そこには中小企業の経営に付きものである「個人保証」という大きな壁がありました。運転資金の借り入れなどで生じるこの重い責任を、大切な従業員に負わせるわけにはいかない。その一心で、まずは個人保証の解除を大前提として銀行との交渉に臨みました。そして約3年前、交渉の末に個人保証の撤廃を実現し、最大の障壁を取り除くことができたのです。これで道が拓けたかと思われましたが、いざ「誰が事業を継ぐのか」となると誰も手を挙げなかったのです。そのとき、事業承継の難しさを改めて痛感しました。
また、私には息子がいますが、家業とは異なる業界で働いており、承継の対象とはなりませんでした。私たちのような専門性の高い会社では、経営者自身が業界や技術を深く理解していなければ、お客様との対話はおろか、的確な事業リスクの判断も困難です。その難しさを息子自身もよく理解しており、話し合いを重ねた結果、承継は難しいという結論に至りました。
他の選択肢が難しい状況となり、M&Aの検討が本格化したのですね。
そうですね。社内も親族も承継が難しいという現実に直面し、時間だけが過ぎていく状況に行き詰まりを感じていました。M&Aという手法は知っていましたが、周囲で成功事例を聞いたことがなかったため、正直なところ、当初はあまりポジティブな印象を持てませんでした。しかし、他に選択肢がない以上、あらゆる可能性を真剣に検討しなければなりません。そう考えていた矢先、ご縁があって知人からM&Aキャピタルパートナーズのアドバイザーをご紹介されたのをきっかけに、M&Aが本格的な選択肢として動き出したのです。
その際、私が最も重視したのは、「単にどこかに吸収されるのではなく、これまで私たちが築いてきた会社の方針をそのまま活かしてほしい」という点です。これは、譲渡にあたっての絶対的な条件として、最初に明確にお伝えしました。加えて、上場企業を候補から外していただくようお願いしました。というのも、私自身が上場企業から独立した経緯があり、トップの交代によって経営方針が大きく変わるリスクを避けたかったからです。その上で重視したのは、私たちの理念や思いに真摯に耳を傾け、深く共感してくださること。そして、「この相手となら一緒にやっていける」とHTCの創業メンバーでもある幹部全員が心から納得できるかどうか。それがクリアできなければ、話は進めないという方針を明確に伝えていました。幸い、当時の業績は非常に好調でしたので、「ほぼ100%満足できるお相手でなければお受けするつもりはない」という前提で、「本当に良いご縁があれば」というスタンスで臨んでいました。
幹部である創業メンバーの「全員一致」がM&A決断の大きな後押しに
ここからは、担当アドバイザーの 東小薗さんにも加わっていただきお話を伺います。
M&Aプロセスの様子をお聞かせください。

今回の最終的なお相手は上場企業でしたが、当初は「上場企業はNG」という青木社長のご意向がありました。そのため、まずは我々のネットワークを駆使し、未上場の企業を中心にご紹介させていただきました。過去の事例などもご紹介しながらお相手先の考え方などをお伝えし、多くの企業とご面談いただきましたが、残念ながら「100点満点」と言えるお相手には、なかなか巡り会えませんでした。
たしかに「上場企業は避けたい」という思いはありましたが、「会って話をしてみなければ分からない」と考え直し、熱意を示してくださる会社とはすべてお会いしました。私が一貫して重視していたのは、「もし我々と一緒になったら、何を期待し、どんな未来図を描いてくれるのか」という点です。しかし、そのビジョンを明確に示してくださる企業は残念ながら多くはありませんでした。
また、お相手が希望すれば、2回目、3回目の面談も行いましたが、お話に一貫性がある方もいれば、回を重ねるごとに話が微妙に変わってくる方もいました。こちらのスタンスは終始変わりませんので、お相手にも一貫した考え方を持っていただかないと、後から「話が違う」となっては困ります。書類で分かる情報だけでなく、「お相手が何を考え、どのような方向を目指しているのか」、その真意を慎重に見極めていきました。
青木社長が最も重視されていたのは、「互いに良い影響を与え合い、共に貢献できる、具体的な未来が描けるか」という点でした。
また、同席された創業メンバーの方々も「現場の技術者同士のように、地に足の着いた会話ができるか」を非常に重要視されていたと感じました。普段の打ち合わせの延長のように、自然なコミュニケーションが取れるお相手を求めていらっしゃったのです。
面談の際は、技術的な話から少し離れ、経営者目線でのお話に終始してしまうケースが少なくありませんでしたが、青木社長は「まずはお会いしてみないと分からない」というスタンスで、すべての面談機会を大切にしてくださいました。
今回のお相手先が、「この会社なら大丈夫だ」という確信に変わっていったのは、どのような経緯からでしょうか。
今回のお相手は上場企業でしたので、正直なところ、当初は少し懸念を抱いていました。
お相手先は、一般的な上場企業とは異なり、グループ各社の自主性を尊重する、いわば“企業連合”とも言える非常に特徴的な経営をされています。そこで私は、企業形態という枠組みよりも、まずトップである会長ご本人の哲学や人柄に触れていただくことが最も重要だと考え、「一度お会いになりませんか」と青木社長にご提案しました。

初回の面談では、鈴木会長ご自身が多くの役員の方々と一緒に出迎えてくださり、まずその真摯な姿勢に心を動かされました。お話の中からも、「本当に一緒にやりたい」という熱意がひしひしと伝わってきましたし、面談後には直筆のお手紙までいただき、その誠実さに触れて懸念はすっかり払拭されました。
そして複数回の面談を重ねる中で、「上場企業である御社と一緒になっても、私たちのやりたいことを継続できるのか」という、最大の懸念を率直にぶつけました。すると、鈴木会長は「できます」とはっきり明言してくださいました。さらに決定的だったのは、私たちのために特別な場を設けてくださったことです。ホールディングス傘下のグループ会社の方々と、私たちが直接ざっくばらんに話せる場を設けてくださり、しかも会長を含めたホールディングスの方々は途中で席を外されたのです。
M&Aの交渉過程で、譲受企業のグループ会社と譲渡企業が直接話せる場を設けるのは、非常に珍しいことです。これは、「すべてを包み隠さずお見せできる」という、度量の大きさと自信の表れだと感じました。良い面だけでなく、ありのままを見せる誠実でオープンな姿勢に、我々も感銘を受けました。
今回のお相手とお話を進めようと思った決め手を教えてください。
数回の面談で、相手企業のすべてを理解するのは難しいものです。だからこそ、トップの思いはもちろん、実際にグループに参加されている方々の生の声を聞けたのが、私たちにとっては非常に大きな意味がありました。その貴重な機会に、グループ会社の皆さんは「グループに参画した当初はどうだったか」「今はどうか」といったことを本当に赤裸々に話してくださいました。そのフランクな情報交換の輪に、私たちのメンバーも技術的な話で大いに盛り上がっていたのです。「本当に一緒に仕事をしている」というダイレクトな感覚が、彼らの心を動かしたのだと思います。
実は、これまで何十社と面談を重ねても、幹部全員の意見が一致したことは一度もありませんでした。しかし、この面談の後、初めて全員が「この会社と進みたい」と言ってくれたのです。最終的には、私自身の思い以上に、従業員たちの反応が決め手となりました。私が彼らを説得したのではなく、これから会社を担っていく彼ら自身が、自ら未来を選び取ってくれた。その事実こそが、今回の決断において、最も大きな後押しとなったのです。
現場が主役となるグループの力で、より大きな挑戦を可能にする未来へ
ここからは、譲受企業である株式会社SYSホールディングスの鈴木様にもご参加いただき、お話を伺います。
まずは御社の事業についてご紹介いただけますか。

SYSホールディングスは、大企業向けの基幹システム開発を手がける会社です。私が26歳で創業してから約35年が経ち、現在では東京・大阪・名古屋を拠点に、約300社の企業とお取引をいただいています。IT業界を取り巻く環境は、日々目覚ましい変化を遂げており、1社だけですべてに対応するのは難しい時代です。そこで当社では、友好的なM&Aを重ねながら、異なる技術やサービスを持つ企業が集まり、それぞれの強みを活かし合える“企業集団”として、変化に柔軟に対応できる体制を築いています。
どのような経緯や思いを持って、M&Aを重ねてこられたのでしょうか。
最初のM&Aは、リーマンショックで経営難に陥った会社の再建を依頼されたのがきっかけでした。 私自身がその会社に行って立て直しを図ったのですが、そこで初めて「思いが通じない」という壁にぶつかったのです。 こちらとしては良かれと思って意見をしても、従業員の皆さんからすれば、外部の人間に「あなたたちのやり方は間違っている」と言われ、これまでの働き方を否定されているように感じてしまう。そのことに、この経験を通じて初めて気づかされたのです。この失敗から、M&Aに対する考え方は180度変わりました。 私たちはM&Aを“結婚”と一緒だと考えています。もしお金だけで決めるのであれば、もっと資本力のある大企業と一緒になればいい。私たちは中堅企業ですから、「これだけしか出せませんが、生涯幸せにする自信があります」というスタンスで臨んでいます。
そこで、M&Aを「合併・買収」ではなく、“経営同盟(Management Alliance)”だと再定義しました。その核となる考え方は、「企業文化を無理に染めようとせず、それぞれの個性や違いこそをグループ全体の力に変える」というものです。私たちのグループでは現場で働く皆さんこそが主役です。私自身もかつて常駐エンジニアとして働いていた経験があるからこそ、「現場が輝くグループにしたい」という思いを強く持っています。せっかく来ていただいたのだから、給料を上げ、就労環境を整える。そして各社の自主性は尊重しつつ、グループ全体のガバナンスはDXやシステム導入によって最適化する。この独自の手法をもとにM&Aを進めてきた結果、これまでご一緒した24社は、すべて順調に成長を続けています。
そのような思いから、今回HTCと一緒になられたのですね。
はい。HTCは、長年にわたって社会インフラの組み込み開発という、私たちにはない事業領域や文化、そして確固たるポリシーを築いてこられた会社です。何よりも印象的だったのは、そのポリシーに誇りを持ち、「私たちのグループの中でさらに成長したい」という強い意志をお持ちだったことです。青木社長は数十社と面談されたとうかがっていますが、私からすれば「もっと早く出会いたかった」と心から思えるお相手でした。
青木様は、鈴木会長のお話を聞かれて、やはり「この会社だ」と思われたのでしょうか。
そうですね。初めて鈴木会長にお会いして、今お話しされたような「経営同盟」というお考えを伺い、「この会社となら、当初の条件とは異なっても、一緒にやっていけるのではないか」と強く感じました。
実は以前、私の同僚がSYSホールディングスとお話をする機会があり、その際に鈴木会長の“経営同盟”というお考えを伺っておりました。その哲学が、青木社長が理想とされていたM&Aの考え方と一致すると感じ、「これこそが最高のパートナーシップになる」と確信したのです。 そのため、「未上場企業を希望」という条件はありましたが、「上場企業ですが、こういう理由で素晴らしい会社です」と、自信を持ってご提案させていただきました。
ありがとうございます。この“企業連合”という形は、お客様と、グループに参加してくれた会社双方に大きなメリットをもたらします。グループ全体として幅広いサービスをご提供できるようになりますし、グループ会社がより大きな仕事に挑戦するサポートもできます。従業員の皆様にとっても、たとえば住宅ローンの審査が通りやすくなるなど、実務的・生活面でのメリットもあります。私たちの考え方を評価してくださる方が多く、本当にありがたいです。
「自分に何かあっても、会社は続いていく」。肩の荷が下りた安堵感
成約直後の率直なお気持ちや今後に向けた思いをお聞かせください。

まずは、「自分に万が一のことがあっても会社が存続できる体制」、つまりリスク管理の面で、目標としていた形を整えることができ、心から安堵しています。そして今回の成約を一番喜んでくれたのは、妻でした。「あなたに何かあっても、会社と従業員の皆さんの生活が守られる環境ができて本当によかった」と言ってくれたのです。家族が安心してくれたことで、私自身もようやく肩の荷が下りました。
HTCは、もともと非常にしっかりとした経営基盤をお持ちです。その強みを、私たちのグループ内でさらに広げ、高く積み上げていければと考えています。
そのための取り組みは、まさに今、動き始めているところです。
今回の取り組みにおける、M&Aキャピタルパートナーズの支援について、どのようにご評価されていますか。

以前はM&Aに対して、ポジティブなイメージではありませんでした。M&A仲介会社は「成約したら終わり」という印象があったからです。しかし、M&Aキャピタルパートナーズは、成約後も継続的に気にかけてくださり、フォローも含めて真摯に向き合っていただける会社だと感じました。
お互いに言いづらい価格や条件を、客観的な立場で調整していただける点は、M&A仲介会社ならではの価値だと思います。また、M&Aキャピタルパートナーズの財務評価は非常に正確で、信頼できるものでした。
そして何より、私が「良いM&A仲介会社」だと感じるのは、売り手・買い手のどちらか一方に偏るのではなく、双方の立場に誠実に寄り添いながら、最適な落としどころを共に探ってくれることです。
特に今回、M&Aキャピタルパートナーズは、売り手の思いを丁寧に汲み取りつつ、買い手である私たちにも誠意をもって対応してくださり、その調整力と中立的な立場に深く信頼を寄せることができました。
ありがとうございます。最後に、東小薗さんから今回の取り組みに関する総括をお願いします。
今回のM&Aは、私にとっても非常に印象深いものとなりました。何より、青木社長が長年にわたって築かれてきた企業文化、そして「従業員の皆様の未来を第一に考える」という確固たる信念に、強く心を打たれました。「100%満足できるお相手でなければ決断しない」という粘り強く真摯な姿勢こそが、今回の素晴らしいご縁につながったのだと思います。一方、SYSホールディングスの鈴木会長が掲げる“経営同盟”という哲学は、まさに青木社長の思いを実現できる最高の形だと確信しました。たとえ当初の条件とは異なっていたとしても、自信を持ってご提案させていただいた背景には、その深い理念の一致がありました。
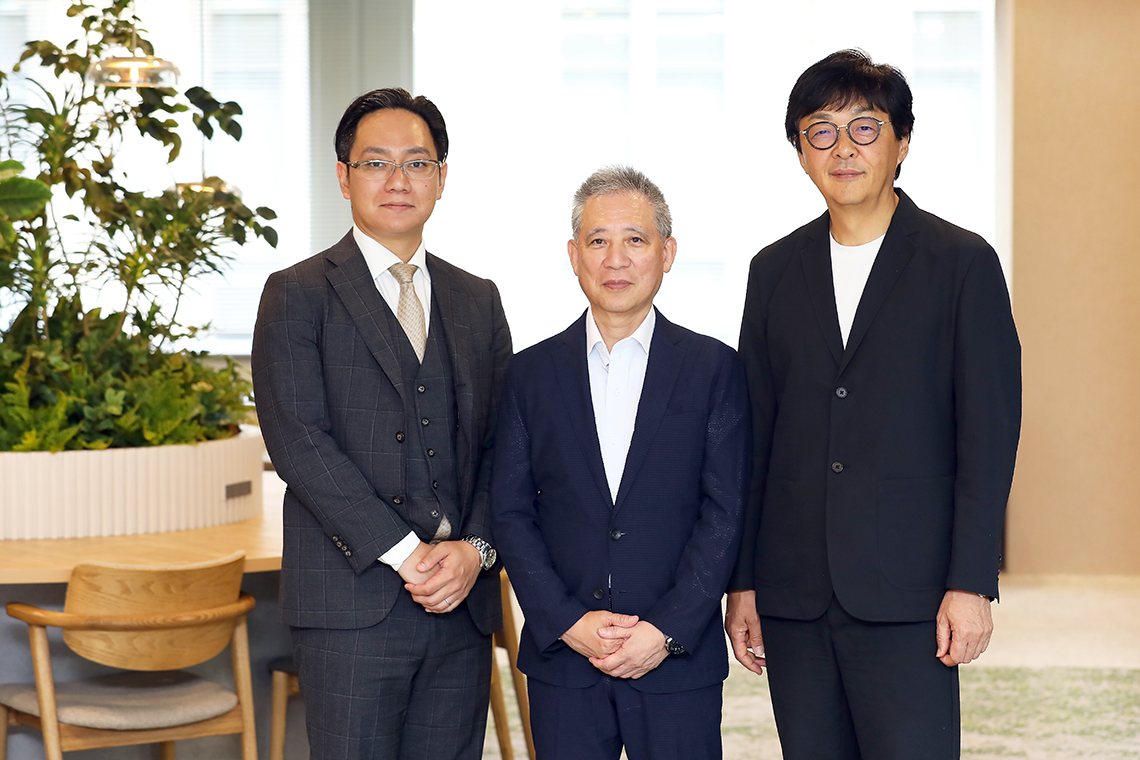
文:伊藤 秋廣 写真:小野 綾子 取材日:2025/6/13
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。