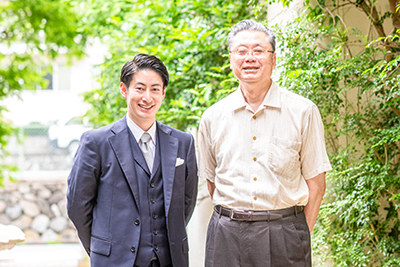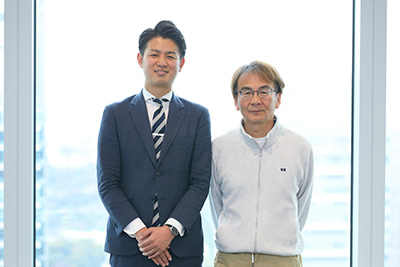「ロボット薬局」を自社にとどめるのではなく、
社会へ実装するための決断
株式会社メディカルユアーズは、日本でいち早くロボット薬局を導入し、調剤にかかる単純作業を減らし、調剤ミスや待ち時間のゼロを実現した自動調剤技術のリーディングカンパニーである。2024年7月、大手総合商社で、東日本を中心にドラッグストアや保険調剤薬局を展開する住友商事株式会社との資本業務提携を発表した。
自らロボットの試作と開発を重ねてきたファウンダー(創業者)兼最高顧問の渡部 正之 様に、資本業務提携を決断した背景、今後の薬局および薬剤師に課せられる役割、そして将来的な自身のミッションを語っていただいた。
-
- 会社名
- 株式会社メディカルユアーズ
- 所在地
- 兵庫県神戸市
- 事業内容
- 保険調剤薬局の経営
- 資本金
- 3000万円
- 従業員数
- 73名
- M&Aの検討理由
- 更なる成長発展、調剤ロボット事業に注力するため
-
- 会社名
- 住友商事株式会社
- 所在地
- 東京都千代田区
- 事業内容
- 多様な商品・サービスの販売、輸出入および三国間取引、さらには国内外における事業投資など、総合力を生かした多角的な事業活動を展開
- 資本金
- 2,204億円
- 従業員数
- 5,152人(連結ベース79,692人)
- M&Aの検討理由
- 事業の拡大のため
独自の調剤ロボットを開発、これまでにない薬局経営を実現してきた
メディカルユアーズの事業概要を教えてください。

メディカルユアーズは、もともと医師の開業支援に取り組むコンサルタント業からスタートしました。製薬会社でMR(医薬情報担当者)として大学病院の担当を経て、調剤薬局で薬剤師として勤務するかたわら「開業したい」と考えている医師の依頼を受けて、物件探しや競争相手となる医院の調査を行い、開業までをサポートしていたのです。MR時代に培った営業力、医師とのコネクションが役立ちました。
こうした地道な活動のおかげで、信頼関係のある医師と共に医療モール(診療科が異なるいくつかのクリニックや調剤薬局が1カ所に集まって運営するエリア)を造り、そこに私たちが薬局を開設できるようになった訳です。当時、大きな病院で出される処方せんを目当てとした門前薬局は既に飽和状態だったので、こうした出店方法は画期的でした。現在は、神戸や大阪などで11店舗を展開しています。
もう一つの特徴は、ゼロから注力してきた調剤ロボットの事業です。私たちは創業以来、薬局の近代化やDX化を掲げてきました。調剤ロボットを導入することで、薬剤師の業務効率を大幅に向上させ、より多くの時間を患者さんとの対話や服薬指導に充てることが重要だと考えたからです。

調剤ロボットは世間から脚光を浴びて、貴社が注目されるきっかけとなりました。なぜこうした事業を始めたのでしょうか。
きっかけは、私が薬剤師として働き始めた13年前にさかのぼります。初めて調剤薬局の現場に立ったときの衝撃は、今も忘れられません。調剤業務といっても大半は単純なピッキング作業、つまり処方せんに基づいて薬を選ぶだけで、6年も専門教育を受けた人材に任せるには、あまりにも生産性の低い仕事だと言わざるを得ませんでした。
せっかく高度な教育を受けた人材の能力を、十分に発揮できるようにするには「自動化が欠かせない」と考えた次第です。その実現のカギを握るのが、ロボットによる調剤の無人化でした。
このままでは日本中の薬局経営が立ち行かなくなる。
たった一人感じていた危機感
まだこの世に存在しないロボットを自ら作り出すには、相当な覚悟が必要だったかと思います。

私を突き動かしたのは、2018年にアメリカから飛び込んできた1本のニュースでした。Amazonがある会社の買収を発表したのです。買収先は、オンラインで処方せんを受け付け、全国各地へ配送を行うことで知られる新興企業でした。書籍や家電製品などと同様に、医薬品もビジネスの対象に広げようという狙いは明らかでした。
それまで自社の薬局を増やし、国内の大手調剤チェーンと闘っていた私は身震いし、今すぐAmazon型のオンライン薬局経営への対抗策を講じなければならないと考えました。かつて多くの書店が大打撃を受けて経営が立ち行かなくなったように、薬局にも深刻なインパクトをもたらすことは確実だと思えたためです。
しかし当時、私の危機感は周りの薬局経営者にはまるで伝わらず、薬剤師会からは「不確かな説を並べ立て、不安を煽るのはやめるべきだ」と言われたほどです。それでも、私の考えは変わりませんでした。すぐに欧米各国へと赴き、業務の自動化や薬局の無人化のために調査を始めました。
既にドイツなどでは調剤ロボットの導入が進んでいましたが、日本とは調剤業務の作業の流れが異なるため、日本型のカスタマイズにはずいぶん苦労しました。開発を決意してから1年以上が経った2019年3月に、梅田薬局を「日本初のロボット薬局」としてオープンした訳です。
苦労を経て作り上げた調剤ロボットは、新聞やテレビにも大きく取り上げられました。
薬剤師が患者に服薬指導を行ったうえで自動薬剤受取機を使うと、無人で薬が受け取れる仕組みは画期的でした。しかし、イノベーションには必ず批判がつきもので、薬剤師の仕事を奪う、専門性の否定につながるといった声もあります。
厚生労働省の反応も「何か問題が起こるのではないか」という冷ややかなものでしたが、報道によって周囲の目が変わり、徐々に理解者が増えていきました。特に若い薬剤師は「医療や薬剤師の将来を切り開く重要な取り組み」だと感じてくれていて、応援の輪が広がっています。
「調剤ロボットを導入したい」という問い合わせも、少しずつ増加している傾向です。
自らの使命である薬局の近代化を果たすためには、
自身にしかできないことに専念すべき
ロボット薬局でイノベーションを起こしたにも関わらず、資本業務提携を検討・決断したのはなぜでしょうか。

薬局経営も順調で、ロボットの形態もさらに改良を進めていたものの、本格的にロボット事業を展開していくには新たな課題も見えてきていました。
特に大きな転機となったのは、2023年の調剤ロボットに関する特許の取得です。特許が認められたことで、自分の社会的な使命を強く意識しました。私たちの薬局だけが自動化しても、社会に与える効果は限定的です。一方、日本中に調剤自動化を広められる人間は限られており、片手間でできることではありません。
本気でロボット薬局を全国に広げて社会に実装するには、薬局経営を誰かに任せる必要があると考えるようになりました。また、安価とはいえないロボット事業を展開するには、資金面の課題もあります。薬局の展開に対して融資をしてくれた銀行は、未知なロボット事業には消極的で、歯がゆい思いもしていました。
なんとか別の方法で資金を調達したいと考えたとき、資本業務提携がひとつの選択肢として浮かび上がってきたという経緯です。
ここからは、担当アドバイザーの本山さんにも加わっていただきます。どのように支援をしていかれたのでしょうか。

渡部様とお会いした当初から、「ロボット薬局を普及させたい」という壮大な目標への思いを伺っていました。
一方で2019年当時は、薬局業界の再編が活発化し、多くの中小薬局が譲渡先を探していたため、渡部様は中小薬局の譲り受けによる事業規模の拡張も検討されていました。結果的に調剤ロボットの特許取得が先行して進められ、ロボット事業推進の優先順位が高くなっていきました。
たとえ既存の一般的な薬局を合併しても、これまでメディカルユアーズが実現してきた、高効率な経営モデルがなじまない懸念もあります。それであれば、「譲り受けにかかる資金をロボット事業に活用した方が良いのではないか」という議論も出てきました。
そこで私は、薬局の譲り受けだけではなく、ロボット事業を成長拡大させるための大手企業との資本業務提携の可能性について、ご提案をさせていただきました。
提案を聞いたとき、渡部様はどのように思われましたか。
本山さんからの提案は、私の考えていたこととかなり一致していました。特に「ロボット事業に集中する」という筋書きは、とても魅力的でした。
また、パートナー候補である住友商事が、既に東日本で多数の薬局を手がけていることはもちろん存じあげていましたし、私たちの地元である関西圏への展開を望むことも想像できました。
住友商事は、以前からロボット薬局の意義や成長性を高く評価していたので、資本業務提携が成立した際には、資金面のサポートはもちろん、同社のネットワークの活用によってロボット普及事業の推進にも寄与できると考えました。
パートナーの高い評価は経営者としての一つの喜び
両者の顔合わせの印象はいかがでしたか。

住友商事との顔合わせは、非常にスムーズに行われたと感じています。本山さんから伺っていたとおり、私たちの事業を深く理解し、共感してくれたことには良い意味で驚きました。
特に印象的だったのは、ロボット事業の可能性を応援する姿勢を示してくれたことです。単なる資本提携ではなく、私自身がミッションとして定めてきた「日本の薬局の近代化」に対しても、共に実現するためのパートナーであると明言してくれました。
また、住友商事のコンプライアンスの厳しさも印象に残っています。こうした企業に、私たちの事業の組織体制や経営状況を認めてもらえたことは、一人の経営者として率直にうれしく感じました。
私も渡部様の印象と同じで、住友商事との顔合わせはとても円滑に進んだと感じています。既に住友商事側が、メディカルユアーズの薬局経営やロボット事業について十分な調査を行っていたため、具体的な質問、建設的な議論が交わされ、話題は、ロボット事業の将来性や、結果的にもたらされる医療の変革という未来などにも多岐にわたって盛り上がったと記憶しております。
住友商事が、メディカルユアーズの経営状況や組織体制を高く評価していたことは、その後のPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション:業務提携後の効果を最大化するために行われる統合プロセス)でも有効であったと感じております。
基本的な合意までスムーズだったようですが、M&Aキャピタルパートナーズのサポートはどのように評価されていますか。
本山さんからは、住友グループのコンプライアンスが特に厳しいと伺っていました。業務提携の話が具体化していくなかで、本山さんの迅速なサポートには本当に助けられました。何しろ私たちにとっては初めての経験ですので、次々に細かな不安が思い浮かびます。ときには夜遅い時間帯にやむを得ず連絡することもありましたが、ほぼリアルタイムで返事をくださる姿勢を心強く感じました。
単なる資金調達や企業価値の向上にとどまらず、「薬局の近代化」という最終目標からぶれることなく、またストレスを感じさせることなくサポートいただけたことに感謝しています。
渡部様からありがたいお言葉をいただき、大変光栄です。
ひとえに渡部様を中心に、堅実で透明性のある経営を実践されてきたこと、特にデューデリジェンス(企業監査)では、経理全般を支える渡部様の奥様のご貢献が大きかったのは間違いありません。住友商事との提携に関しては、渡部様のビジョンと住友商事が保有するリソースやネットワークとのシナジーを強く感じていたので、両者をお引き合わせできたことを非常にうれしく感じると同時に、必然だったと感じております。
調剤ロボット普及を通して、多くの薬局の企業価値向上に寄与したい
資本業務提携は、ロボット事業にどのような影響が出ているのでしょうか。

まずは、住友商事のグループ内におけるロボット導入の準備が始まっています。グループ外の薬局からも調剤ロボットの設置要請が増えており、1年で新たに9台の設置が完了する予定です。今も、数十件の問い合わせをいただいています。
私たちはロボットを販売するだけでなく、導入を検討している薬局に対してコンサルティングも行っています。現地調査を行い、各薬局に最適なロボットの提案や導入後のサポートも実施中です。
ロボット事業に専念できる意義は大きいとお考えでしょうか。
はい。しかし、さらに普及を加速していかなければなりません。普及のカギは、薬局業務の根本的な変革を実現できるかにかかっています。日本では、薬を一つずつ箱から取り出して計数する業務が基本ですが、他の先進国では当たり前になっている「箱出し」に変革することが目標です。
これにより、薬剤師が専門性を活かせる業務に一層集中できるようになるのは明白ですが、慎重論も根強く残っています。少しずつ理解は広まっているものの、まだ道半ばです。
調剤ロボットの導入は、単なる業務効率化ではありません。薬剤師の働き方を、より本質に近づけるものです。具体的には、患者さんと接する時間を増やすことが挙げられます。高齢化が進み、在宅医療のニーズが増えるなかで、薬剤師が専門職として安全で効果の大きい服薬を促すこと、また医師や看護師の役割を補完することは国民の医療満足度向上、ひいては医療費抑制につながる重要なテーマです。
薬局経営に捉われなくなったメリットを活かして、改革に向かって推進したいと決意しています。
今後、資本業務提携などを検討される経営者の皆さまに向けたメッセージをお願いします。
資本業務提携を単なる資金調達や事業売却の手段としてではなく、自社のビジョンを実現するための「戦略的な一つの選択肢」として考えて良かったと思います。自社の枠組みを越えて実現したい目標があるなら、実現の手段として資本業務提携が有効なのか判断できるはずです。
次にパートナー選びですが、単に規模が大きい企業や条件の良さではなく、自社のビジョンや価値観と合致する企業を探すことが大切です。私の場合は、パートナーがロボット事業を本気で応援する姿勢を示してくれたことが、決め手となりました。さらに双方の事業のシナジー、今回でいえばロボット事業の推進力をもたらしてくれることも大きな要因でした。
また、信頼できるアドバイザーの存在も非常に重要だと感じます。取引を完結させるには、経験豊富なアドバイザーによる顧客目線の支援が不可欠であると感じます。
今後も薬局業界に関わらず、知り合いが資本業務提携を模索するなら、ぜひ本山さんを紹介したいですね。
今回満足、納得のいく資本業務提携となったのは、店舗へのロボットの導入を通して薬局の企業価値を高めることができていたからだと考えています。再編が進む調剤薬局業界において、将来的な資本業務提携も視野にいれている経営者も多くいらっしゃると思いますが、そういった選択に備えて企業価値を高める努力をしていくべきではないでしょうか。
私がこれから注力していくロボット事業がその一助になれればと考えていますので、他薬局との差別化や企業価値向上を目指している薬局経営者の方々には、株式会社メディカルユアーズロボティクスの調剤ロボットをぜひ活用いただきたいです。
今回のプロジェクトに携われたことは、私にとっても大きな学びとなりました。企業単体の将来だけでなく、業界の未来を左右するような提携のご支援をすることができ、とても誇らしく感じています。
薬局は単なる業界再編だけでなく、私たち国民の健康に関わる大切な産業です。これまでの知見を活かして、さらに貢献してまいりたいと思います。

(左から)弊社本山、渡部様
文:蒲原 雄介 写真:松本 哲 取材日:2024/8/7
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。