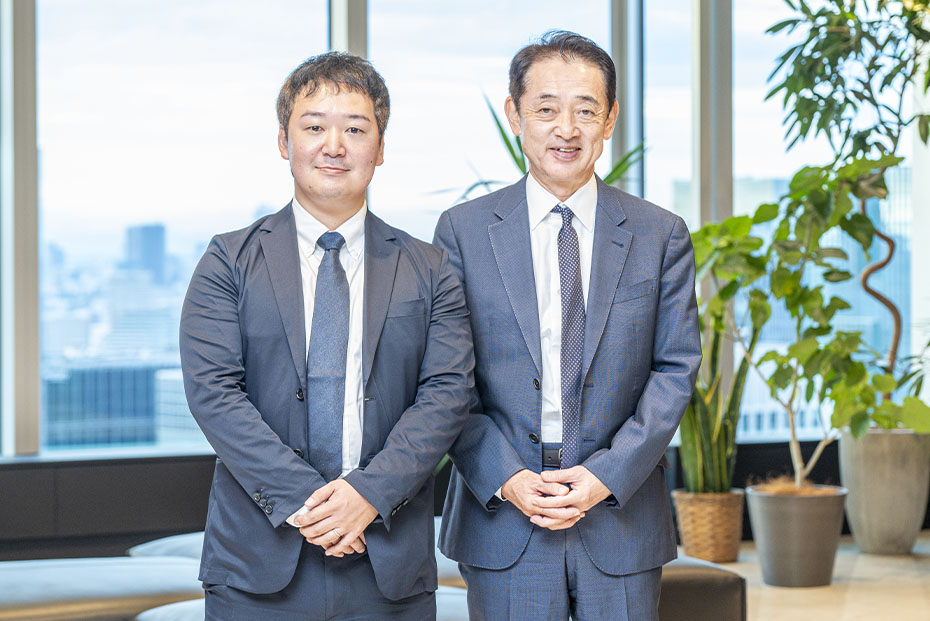自動認識技術一筋の挑戦。
自社の独立性を守りながらも限界を乗り越えるための決断
自動認識技術のソリューション開発を手がける株式会社ケーウェイズ。RFID技術を核とした専門性の高いシステム開発によって、大手メーカーとの信頼を礎に、確固たる地位を築いてきた。RFIDは、ICタグに記録された情報を電波で読み取る技術で、Suicaやさまざまなスマートフォン決済にも欠かせない技術だ。
創業から16年、技術一筋で成長を続けてきた同社が、さらなる飛躍のためにOrchestra Holdings株式会社とのM&Aを決断したのはなぜだったのか。その経緯と今後の展望について、代表取締役社長の諸田健一様、取締役の松浦王保様にお話を伺った。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社ケーウェイズ
- 所在地
- 横浜市港北区
- 設立
- 2010年
- 資本金
- 2,000万円
- 事業内容
- バーコード、二次元コード、ICカードやRFIDを利用したシステムの開発
- M&Aの検討理由
- 後継者不在のため
-
譲受企業
- 会社名
- 株式会社Orchestra Holdings
(東証プライム上場) - 所在地
- 東京都渋谷区
- 設立
- 2009年
- 資本金
- 3億5,400万円
- 事業内容
- デジタルトランスフォーメーション事業、デジタルマーケティング事業
- M&Aの検討理由
- 事業拡大のため
自動認識技術を追求し続けるために自ら起業
お二人の出会いから創業に至るまでの経緯を教えていただけますか。

松浦とは、かつての勤務先が同じでした。当時はまだ珍しかったインターネットファッションモールを立ち上げるというプロジェクトに、松浦と私が参画したのです。
しかし、いわゆるITバブルが弾けた影響で景気が低迷し、一時は別々の会社でシステム開発の仕事を続けることになりました。ところが、再びリーマンショックでそれぞれの会社が厳しい状況に追い込まれたのです。そんな中で、「一緒に事業を始めてみないか」という話になりました。

私の視点で申し上げると、新卒で入社した会社に中途入社で入ってきた上司が諸田だったという経緯です。不景気のあおりを受けて、給与は大幅に減らされたり、途中でプロジェクトが立ち消えになったり、苦渋を味わいました。そんな状況下では明るい未来を見通せるはずもなく「このままいてもダメだろう」ということで、ともに独立することを決心したのです。取引先との契約を解消することに納得できず、私は早く会社を辞めてしまい、諸田を慌てさせてしまいました。
RFID技術に着目したのはなぜだったのでしょうか。
私は以前にいた会社で、バーコードを利用したシステムの開発に携わってきました。その延長線上で自動認識技術にも関わるようになります。今では社会に欠かせないインフラとなったSuicaがスタートしたのは2001年ですが、普及し始めた頃からRFID技術は広く注目されるようになっていました。
ケーウェイズの強みは、ハードウェアとともに現場で行われる業務についての知見を有していることだと考えています。一般的にハード系のアプリケーション開発者は、業務について知りません。業務に詳しい現場では、逆に技術的なことが分からないケースが多く見られます。私たちは、RFID専従で開発に取り組んできたおかげで、どちらも高い解像度で理解できるため、顧客の業務に合わせた最適な提案ができると考えています。
創業時はデンソーウェーブとの取引が命綱でした。一般的にもQRコードを作った会社としても広く知られています。さらに、RFIDリーダーやタグの開発をはじめ、デバイスの製造やシステム構築まで手がけるなど、幅広い事業を展開する業界のトップカンパニーです。以前からの取引というつながりがあったからこそ、新会社としての最初の受注が決まりました。創業から3年、顧客は同社を含めてわずか2社でしたが、強固で太いパイプがあったからこそ、今日までやってこられたのだと思っています。
人材受け入れによる転機が呼び込んだ事業の拡大
ここまで会社が成長できた理由はどのようにお考えですか。

大きな転機はデンソーウェーブからの依頼によって、ある会社の技術者2名を受け入れ、雇用したことです。彼らの勤務先が経営不振で、もし失業することになれば自動認識に関する高度な知識と技術を持つ人材が他の業界に流出してしまう恐れがありました。それはRFID業界全体にとっても損失だと、私たちが引き受けることになったのです。
この2名は今でも在籍していて、とても貴重な戦力として活躍中です。RFIDはニッチですが、決してなくなることのない技術だと考えています。そこで、こうして業界内で信頼を積み上げることができたことが事業の成長にもつながっていったように感じています。
一方で、自動認識の事業1本のままではいざという時にリスクがあると考えていました。そこで、もう1つの売上の柱としてワークフローのアプリケーション開発の事業も育てていたのです。ちょうど売上も半々ぐらいのバランスとなり、理想的な状態でした。しかし、結果的にはこのワークフロー事業では、発注元の会社にメンバーが丸ごと移ってしまうという事態になりました。2019年のことです。
時期的には直後にコロナ禍も重なるタイミングでしたね。
あの時は本当に必死でした。なぜあの危機を乗り越えることができたのか、いまだに自分たちでも理由がわからないほどです。再び自動認識の事業だけになりましたが、じわじわと業界内での知名度が広がり、さまざまな取引先から信頼を得られるようになっていたのは大きかったと思います。黒子的な存在としてアプリケーションだけを開発するケースもあれば、直接エンドユーザーとビジネスする案件もありました。
コロナ禍では各社の開発も滞り、当社としてはなんとか耐えしのぐ時期でした。しかしコロナ禍にも収束の兆しが見えてきた頃から、一気に仕事が戻ってきました。DXというワードが注目されるようになったのもこの頃です。「今までのやり方ではなく、もっと効率化しないといけない」という機運が高まったように思います。非接触型のRFIDはこうした時代の要請にもぴったりでした。気がつけば、コロナ禍前よりも事業としては大きな成長を果たすことができました。
DXの波に乗り遅れないために自社以外の力を頼りたい
お二人の人脈やお人柄があって成長を遂げたのでしょう。その中でなぜM&Aを検討し始めたのでしょうか。
DXが市民権を得るにつれて「このまま自動認識技術の一本で勝負できるのか」という不安を感じ始めました。私たちはエッジデータ(主に端末で収集されるRFIDの使用データ)を集めるのは得意ですが、その先の活用方法には限界があります。せっかくDXの波という大きなチャンスが到来しているので、この機会を逃したくないと考えていました。そのためには、単独ではなく、どこかと一緒になってビジネスを推進する必要性を感じていたのです。それに人材不足が進み、自社だけで採用活動を行うことへの不安もありましたし、人材確保できないのではないかという危機感もありました。
また、いつの日か経営のバトンを渡す相手がいない事実にも向き合わなくてはなりません。松浦自身にも、これまで何度か意志を確認したことがあります。けれども本人は、「自分は社長を務めるタイプではない」と言っていたので、外部への承継を考えるようになりました。
これまでずっと現場主義を貫いてきました。この15年間、目の前のお客様のために全力を尽くしてきた自負はあります。私自身、マネジメントよりも現場での対応に適性があると思っています。だから諸田に相談された際も「自分は現場にいたい」と言い続けていました。
M&Aキャピタルパートナーズに任せてみようと思ったのはなぜだったのでしょうか。
松木さんとお会いしたときの印象が良かったというのが一番です。誠実で決して嘘をつかなそうだとお見受けしました。将来的な選択肢の一つではありましたが、その時点で今すぐに検討を始めたいとは考えていませんでした。ただ、お会いしたときの対応がしっかりしていたので、信頼できると感じたのです。ケーウェイズという組織をしっかり残しつつ、事業を発展させてくれるパートナーがいるのなら、詳しい話を聞いてもよいかもしれないと思うようになりました。

諸田様は初めてお会いしたときから、真摯に私の話を聞いてくださいました。私も同様に、誠実な経営者様だという印象が心に残っています。まだM&Aをするタイミングではないとおっしゃっていた頃も、定期的に他社の成約事例などをご紹介していました。その頃から、自分事のようにとても興味を示してくださったのを覚えています。M&Aに限らず何か業界の情報があればお伝えするように心がけていました。
他社のお話、特にM&Aについての情報を教わる機会はなかなかありません。1回決めたら、私はずっと「その人」とご一緒するタイプなので、M&Aの候補選びや一連の準備もすべて松木さんにお任せすることにしました。
理想的なシナジーがイメージできた。
これまで単独では提案できなかったトータルソリューションの可能性
複数の候補先からパートナーを選んだ決め手は何でしたか。

当初、Orchestra Holdingsという名前は存じ上げませんでした。業界が異なり直接的な関わりがなかったので、無理もなかったように思います。リストには自動認識技術でよく知られた会社もありましたし、当社の取引先の名前も載っていました。しかし既存のお客様を選んだ場合、他の20社以上のお取引先との関係が危ぶまれます。
その中で、Orchestra Holdingsを選んだのは、先方の話しぶりや姿勢に惹かれるものがあったからです。私たちが重視する事業の独立性をしっかり守ってくれそうだと感じられました。
社名の「オーケストラ」のように、グループにはさまざまな特徴をもった会社がすでに加わっています。オーケストラにも多数の楽器が加わるように、それぞれの会社の特色を活かしながらシナジーを起こすという考え方は魅力的だと思ったのです。
まさにその通りで、私たちはRFIDを駆使してエッジデータを収集するのは得意ですが、そのデータを活用するまでが単独では困難でした。それでは顧客に対して真のDX提案ができません。一方、Orchestra Holdingsには具体的なソリューションの提案力があります。こうしたアセットを活かしてトータル的な提案ができるようになるのは、とても楽しみです。

正直なところ、当社だけでは手に負えず、お断りしていた案件も少なくありません。これで今度は断るどころか、顧客が期待している以上の成果をご提供できるように思います。
逆にグループにもたくさんのお客様がいます。ここに私たちの自動認識技術がメニューとして加わることで、私たちの受注もグループ全体のビジネスも拡大すると見込んでいます。
これまでも多数のM&Aを支援してきましたが、初回の顔合わせにおける印象の良さ、また経営者同士の相性が良いことも、両社面談の雰囲気から伝わってきました。
デューデリジェンス(企業監査)など、M&Aの手続きに苦労する経営者も多いとお聞きしますが、いかがだったでしょうか。

苦労と感じるような場面は、ほとんどありませんでした。以前にM&Aを経験した経営者からは、このプロセスが一番大変で、二度とやりたくないという話まで聞いていたので覚悟はしていました。しかし、実際には拍子抜けするほどスムーズに進んだのです。
松木さんの対応の速さには本当に助けられました。財務面の質問なども、松木さんが答えられるところはすべて答えてくれました。その中で、わからないところだけ聞いてくれるという形だったので、負担がとても軽かったのだと思っています。
嬉しいお言葉をいただき、ありがとうございます。できる限り諸田様のご負担を減らせるように努力しました。しかし、提出をお願いした書類を遅滞なくご用意いただくなど、諸田様の迅速かつ正確なご対応があってこそ、スムーズに進めることができたのだと思います。
早くも人材採用で成果。自動認識ソリューションのナンバーワンに向かって
社員の皆さんの反応と、採用面での効果について教えてください。
社員からのネガティブな反応は一切ありませんでした。これまで取り組めなかった分野や技術にもチャレンジできると伝えたことで、前向きな空気が生まれたように思います。
採用については、すでに効果が出始めました。これまでなかなか新卒採用ができなかったのですが、Orchestra Holdingsが採用したメンバーが当社に転籍しています。今回のご縁がなければ、その新入社員との出会いもなかったと想像すると、感慨深いものがあります。
若手メンバーも、上場企業がバックについたことで安心してくれているかもしれません。それでいて、独立性もしっかり保たれており、経理や労務といった制度面では歩調を合わせなくてはならない要素もあります。一方で、現場の仕事の進め方は何も変わっていません。よいところばかりが目立っています。
今後もお二人がリーダーを務める中で、どのような会社にしていきたいですか。
自動認識ソリューションでナンバーワンになるという会社としての目標は、グループ入りする前から変わっていません。ナンバーワンを実現するための答えが、今回のM&Aだと考えています。
このナンバーワンというのは、自動認識の機器やソリューションなら何でも知っている、ケーウェイズに相談すれば最適な方法が分かると、多くのお客様に認識していただける状態だと考えています。
今回を経てさまざまな新しい強みを手に入れたケーウェイズの提案により、多くのお客様のDXを支援したいと思います。これまで自社だけでは取り組めなかったことができるようになるという事実に、現場の皆もワクワクしています。
M&Aを検討している経営者の方々にメッセージをお願いします。
時代が移り変わり、1社だけで何かを成し遂げるのは大変難しい時代になっていると思います。M&Aというワードからは、弱肉強食のような偏ったイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし実は、お互いの不足や不得意な部分を補完するための合理的な選択肢だと感じています。独立性を確保しながらも、一定以上の規模のバックを使ってビジネスを展開するのがこれからの時代にマッチしているのではないでしょうか。
15年間地道に努力してきたことで、今回このようなご縁が生まれたと思います。声をかけていただいたこと自体、とても光栄なことでした。
M&Aは積み上げてきた成果や信頼に対する1つの評価だと受け止めました。もし今後の事業の方向性について迷いのある経営者がいるなら、評価してくれる会社がいるのか、そしてどのようなシナジーが期待できるか、話だけでも聞いてみたほうがいいと思います。
M&Aは、あくまでも選択肢の一つです。そのご検討を深めるお手伝いをするのが私たちです。優れた技術や製品をお持ちでも、自社のリソースだけでなく、パートナーの力を借りることで新たな展望が開ける可能性も十分に考えられます。情報収集の一環として気軽にご相談いただければ、M&Aも含めたさまざまなご提案をできると思いますので、ぜひ私たちを活用していただけたらと思います。

文:蒲原 雄介 写真:平瀬 拓 取材日:2025/6/24
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。