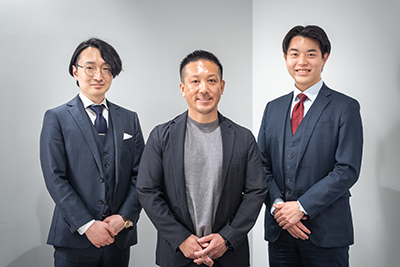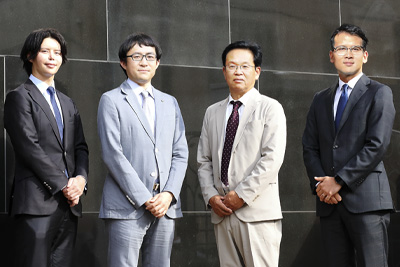創業時から心配だった後継者不在問題をM&Aで解決。
50歳で起業した創業者オーナーの想い
宮城県仙台市に本社を置き、理化学機械器具の受託販売、研究の受託、および測定機器の開発、製造に従事する株式会社和泉テック。その技術力と信頼性を武器に、日本全国の国立大学の研究室から依頼を受け、堅実に成長を果たしてきた同社は、2024年に株式会社鳥羽洋行へ株式譲渡によるM&Aを行った。M&Aまでの経緯とこれからの想いについて、創業者で代表取締役の大滝 善二様に伺った。
-
譲渡企業
- 会社名
- 株式会社和泉テック
- 所在地
- 宮城県仙台市
- 事業内容
- 分析・計測機器商社
- 資本金
- 1億円
- 従業員数
- 9名
- M&Aの検討理由
- 後継者不在のため
-
譲受企業
- 会社名
- 株式会社鳥羽洋行
- 所在地
- 東京都文京区
- 事業内容
- 制御機器、FA機器、産業機器などの
機械工具の専門商社 - 資本金
- 11億4,800万円
- 従業員数
- 256名(連結)
- M&Aの検討理由
- 事業領域の拡大のため
50歳で起業。大学を相手に付加価値の高いビジネスを展開
まずは大滝様が、株式会社和泉テックを創業した経緯からお話しいただけますでしょうか。

大学卒業後に船の部品を扱う会社に就職し、商社マンのような働き方をしていました。しかし、もともと“起業をしたい”という気持ちがあったので、出身地は山形県ですが、仙台で知り合った3人と会社を始めました。その時から、現在のような理化学機器の販売に従事することになりました。
その会社がだんだんと大きくなる中で、“自分ひとりの力で会社を経営したい”と思うようになり、起業することにしました。すでに50歳になっていましたから、年齢的には遅かったのですが、取引のある主力メーカーやお客様の中には、私を信頼してついてきてくれる会社がいくつかありました。
起業するにあたっては、これまでと同じようなやり方をしていても仕方がないと思っていました。前職では、民間企業に営業をかけサービスを提供していましたが、民間企業だけではなく大学などを対象に付加価値の高いビジネスを進めようと考えました。しかし大学の入札に参加するためには、会社として最低でも2年間の実績が必要で、起業したばかりの会社ではそもそも入札すらできなかったので、取引のあった町工場を持つ会社を譲り受けて入札に参加しました。社名にある“和泉”は、その町工場からとったものです。もちろんその町工場が、大学に部品を納入していたことも知っていました。
私は経営だけでなく、しばらく営業も続けていましました。やがて町工場の納入先である東北大学が中心になって進めている大きなプロジェクトに参画することになり、そこから和泉テックの名前が浸透し、日本各地、さまざまな大学から声がかかるようになりました。国立大学の教授は、いろいろな大学に異動しますが、科学研究費の使い道はその教授に付いているものなので、たとえ勤務する大学が変わっても使える研究費は変わらないのですね。私たちの取引があったのは工学部ですが、そこではさまざまな実験や研究が実施されるので、そのたびに新しい依頼が来るようになっていきました。
大学教授からお声がかかるのは、単純に“良いものを売っているから”という理由だけではなさそうですね。どうして、そこまでの信頼を集めてこられたのでしょうか。

単に、右から左に機器を納入するのではなく、私たち自体、“モノづくりができる商社”であることが大きかったと思います。自分たちに技術力があるからこそ、教授からの要望を正確にメーカーに伝えることができたので、測定器メーカーも教授もやりやすいのだと思います。また教授と密に連携を図りながら、完全オリジナルの“一品もの”を自分たちで作って納入しています。これまでどんな要望にもお応えしてきました。
会社の信用と評判が高まり、どんどん業績は拡大していきましたが、業務の内容が内容だけに営業担当の育成が難航しましたね。難しい営業だから、入社してもそんなに長く続かないのです。好きでなければ続かない仕事だと思います。結果的に、今、会社に残っているのはこの営業が好きで、10年以上続けている人ばかりになっています。
自分の要望を10項目ほどにまとめて提示した
大滝様がリードして成長をさせてきた会社です。どのようなきっかけからM&Aを意識するようになったのでしょう。

私は50歳で起業したので、“後継者がいない”という悩みは、創業当初から常に頭の中にありました。従業員を後継者として教育していたこともありましたがうまくいかず、経理をしている義理の息子も経営者向きのタイプではないと、私も本人もわかっていました。お客様からの信頼にこたえ続ける会社を“終わらせる”という考えはなかったので、なんとか継続させようと考えてはいました。今から5年ほど前には、経営コンサルタントと契約して承継について相談したり、社員の意見を聞いたりしていたのですが、なかなか明確な解決法が見つからないままでした。
そう考えていた時にタイミングよく、M&Aの仲介会社からダイレクトメールが届くようになりました。その内容をしっかり読んでいるうちに“これはM&Aしかないのではないか?”と、思うようになりました。“任せられる人を早く見つけて、自分は引退しても大丈夫な体制を作りたい”という気持ちが徐々に高まっていきました。
ダイレクトメールを送ってきた会社は20社ほどありましたが、直接、電話をかけてきたのは4社だったので、その4社全てと面談することにしました。私は今回に限らず、電話をくれた営業担当者とは必ず一度は会うことにしていました。実際に会わなければ、正しい情報を得ることができないと考えているからです。意味のある面談をするために、事前に「社名を残すこと」や「社員の雇用」、そして「譲渡対価」など自分の要望を10項目ほどにまとめておきました。4人に会って、同じことを何度も説明するのが面倒だったので、そのような準備をしたのですが、結果的には各社の提案の差が明確になり、判断がしやすくなったと思います。
仲介会社の中には、仙台にある同業者を紹介してくる人もいましたが、近隣の同業者と手を組むことになったら、自分たちの会社名が無くなってしまう可能性がありますし、そもそも社員が嫌がります。その話を持ってきた人に対しては、“一体何を考えているのか”と不信感をいだきました。ほかにも「わざわざ九州まで行って買手候補を見つけてきました!」と報告してくる人もいましたが、そもそもその会社は私の出した条件に合っていませんでした。こちらの要望をきちんと把握してくれているのか?疑問を感じざるを得ない状況が続きました。そんな中、条件に合う提案をしてくれたのはM&Aキャピタルパートナーズの竹内さんだけでした。
竹内さんは和泉テックに対してどのような印象を持たれたのですか。

会社に強力な営業マンがいて、単純な商社ではなくモノづくりもできるという、会社としての強みはあるものの、その一方で、大滝社長のような経営者の目線を持つ後継者がいないという点で、将来的な課題があると感じました。そこで、会社の強みやこだわりなどを聞き取りしながら、提案を重ねていきました。何度かお話をしていく中で、大滝社長が用意された10項目の条件を満足できるM&Aが可能で、それが選択肢のひとつになるということは分かっていました。また和泉テックは、多くの仲介会社からお声がけがあることは分かっていたのですが、私は同業仲介会社の動きはあまり意識せず、大滝社長だけを見て、どのような形がベストなのかを考えていきました。
竹内さんとお会いしたとき、大滝様のなかで、M&Aに対するお気持ちはどのようなレベル感だったのでしょうか。

すでに“100%、M&Aを進めよう”と考えていました。そもそもM&Aを実行するつもりもないのに話だけを聞くというのは、せっかくここまで来てくれる竹内さんのような方に対して失礼だと思っていましたから。
竹内さんが紹介してくれた数社と面談をしました。今回ご一緒することになった株式会社鳥羽洋行に決めた理由は、先方がM&Aをするのが初めてだったという点が大きいです。例えば子どもが生まれたとしたら、一番初めの子どもは大事にするでしょう。それと同じ発想です。私は、たくさんいる子どもの中の一人より初めての子どものような状態の方が良いのではと考えました。もちろん、こちらが提示していた条件もおおまかに満たしていました。
トップ面談の際の相手に対する第一印象はいかがでしたか。
第一印象はもちろん、良かったのですが、その時点で会社を託せるかどうかの判断は難しいので、最初の面談では正直、そこまで深く考えることはありませんでした。ただ鳥羽洋行は歴史があり、経営も安定していることはわかっていたので、すでに一定の安心感はありました。
鳥羽洋行も仙台に営業所があるので、もしもうまくいかなければ統合される可能性があるという懸念は少しありますが、反対に先方の従業員を和泉テックに出向させるということもあるかと思い、妥協できると考えました。面談後はスムーズに話が進んでいきました。成約したばかりなので、すべてはこれからという話ですが、人材面においては実際にM&Aの効果が表れています。これまで自分たちの力では難しかったのですが、鳥羽洋行の知名度もあり今年は、数名の採用ができました。
竹内さんは、トップ面談後の流れについて、どのように見ていらっしゃいましたか。

お互いが合う感覚がありました。鳥羽洋行も商社ですが、事業的にぶつかっていませんし、初めてのM&Aでありながら、“違う領域に行きたい”という要望がありました。面談の際にも、鳥羽洋行の経営陣と大滝社長のフィーリングが合っていると感じましたし、「社名を残す」などの要望も理解いただいているので、面談後には“大丈夫だろう”という印象を持ちました。
“無くなったら困る”と思われる会社であることが重要
成約後の率直なお気持ちをお聞かせください。

ホッとしていますね。例えば、主要な取引先の東北大学で一度、大きな失敗をしてしまうと、全国の国立大学にも出入りができなくなってしまいます。そういったプレッシャーとずっと戦い続けてきたので、成約後は肩の荷が降りました。これでようやく一線を退くことができると思ったのに、引継ぎなどでまだ半年は仕事を続けなければならないと聞いたときは、嬉しくもあり苦しくもありました(笑)。今後は趣味である油絵の創作にも打ち込みたいですね。
従業員の方の反応はいかがでしたか?
直接話を聞いたわけではないので、何を考えているかは分かりませんが、鳥羽洋行から新たに営業部長として来られた方の歓迎会をすると従業員が言っていたので、おそらくみんな、喜んでいると思います。40代や50代の社員が多いので、今から新しい職場を探したとしても、同じような給料をもらうのは難しい場合もあるかもしれません。でそういった意味では、会社が存続することになって、これまで通り働ける環境があることに、安心してくれていると思います。
M&Aキャピタルパートナーズはどのようにお役立ちになりましたでしょうか。
良い情報を持ってきてくれたと感謝しています。聞き上手で、こちらの考えをしっかりとくみ取ってくれました。営業の基本は相手の話を聞いて理解をすることだと思いますが、竹内さんはそれがしっかりできていたように思います。
ありがとうございます。最後に、これからM&Aを検討する経営者の方々にメッセージをお願いします。

M&Aを考えている人は、自分の要望を整理して明確にし、その基準に沿って正しい判断をするための情報をできる限り集めるべきだと思います。一度、“M&Aをする”と考えたのなら、方向性をしっかりと決めておくべきでしょうね。私は50歳で創業しましたが、それはお客様をしっかりとつかんでいたからこそできたことです。そういった大事なお客様がいるからこそ、創業時から後継者について考えることになりました。そういった意味でもやはり、お客様から“無くなったら困る”と思われる会社であることが重要でしょうね。
大滝社長の会社は強いビジネスモデルと営業マンがいて、社長からの要望もしっかりとあったため、期待に沿える提案をしようと考えてきました。その中で、今回、良いお相手が見つかり、一緒になれて良かったと思っています。
私たちは、大滝社長のように、明確にM&Aを求めている経営者の方や会社でなくても幅広くお会いし、お話を伺っていますので、まずはご相談をいただければと思います。ご相談者の想いや予定に合わせて幅広い選択肢を提供させていただきます。

(左から)弊社 竹内、大滝様
文:伊藤 秋廣 写真:尾苗 清 取材日:2024/4/16
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。