”正しいM&A”
M&Aキャピタルパートナーズ
M&Aの成立に向けたアドバイザリー業務を提供しております。
経験豊富なアドバイザーが、選択肢のひとつとしてM&Aを提案し、実現までサポートいたします。
弊社の
特長
1
着手金無料の報酬体系
弊社は着手金や月額報酬をいただくことなく、お相手企業と基本合意にいたるまで無料で支援いたします。
また、業界内で手数料率が2.7%と最も低く、すべてのオーナー経営者様が、M&Aを将来の選択肢の1つとして、検討いただけるような料金体系としております。
弊社の
特長
2
専門家による伴走
国内トップクラスの仲介実績と、業界に精通したアドバイザーが、経営者様の意思決定をサポートいたします。
また、各業界M&Aのスペシャリストを終結した業界M&Aプロフェッショナルチームも有しております。
弊社の
特長
3
豊富なM&A仲介実績
事業承継、経営戦略など、様々なご要望にM&Aという選択肢でご支援をしております。 ご成約インタビューをまとめ「それぞれの選択」と題し掲載しております。
それぞれの選択・ご成約事例M&A案件情報
-
案件詳細を見る
詳細業種 不動産賃貸業 所在地 中部・北陸 概算売上 1億円未満 -
案件詳細を見る
詳細業種 歯科医院 所在地 中部・北陸 概算売上 1億円~2.5億円 -
案件詳細を見る
詳細業種 アイラッシュサロン 所在地 非公開 概算売上 5億円~10億円 -
案件詳細を見る
詳細業種 Webサイト制作、システム開発、アプリ開発 所在地 関東 概算売上 2.5億円~5億円 -
案件詳細を見る
詳細業種 内科クリニック 所在地 北海道 概算売上 1億円~2.5億円 -
案件詳細を見る
詳細業種 健康食品・サプリ製造販売 所在地 九州・沖縄 概算売上 1億円~2.5億円 -
案件詳細を見る
詳細業種 ゲームソフトウェアの企画・開発・デザイン 所在地 関東 概算売上 2.5億円~5億円 -
案件詳細を見る
詳細業種 クリニック1施設(産婦人科)の運営 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円 -
案件詳細を見る
詳細業種 イタリアンレストラン 所在地 関西 概算売上 1億円未満
セミナー情報
-
受付中
 事業承継・事業成長オンライン・録画配信
事業承継・事業成長オンライン・録画配信開催日時
6月12日(水)15:00~16:00
詳細はこちら -
受付中
 調剤薬局業界向け会場・オンライン開催
調剤薬局業界向け会場・オンライン開催開催日時
2024年6月4日(火)15:00~17:00
詳細はこちら -
受付中
 経営戦略会場・オンライン開催
経営戦略会場・オンライン開催開催日時
2024年5月15日(水)
詳細はこちら -
録画配信
 業界動向・M&A録画配信
業界動向・M&A録画配信配信期間
2024年5月31日(金)まで
詳細はこちら -
録画配信
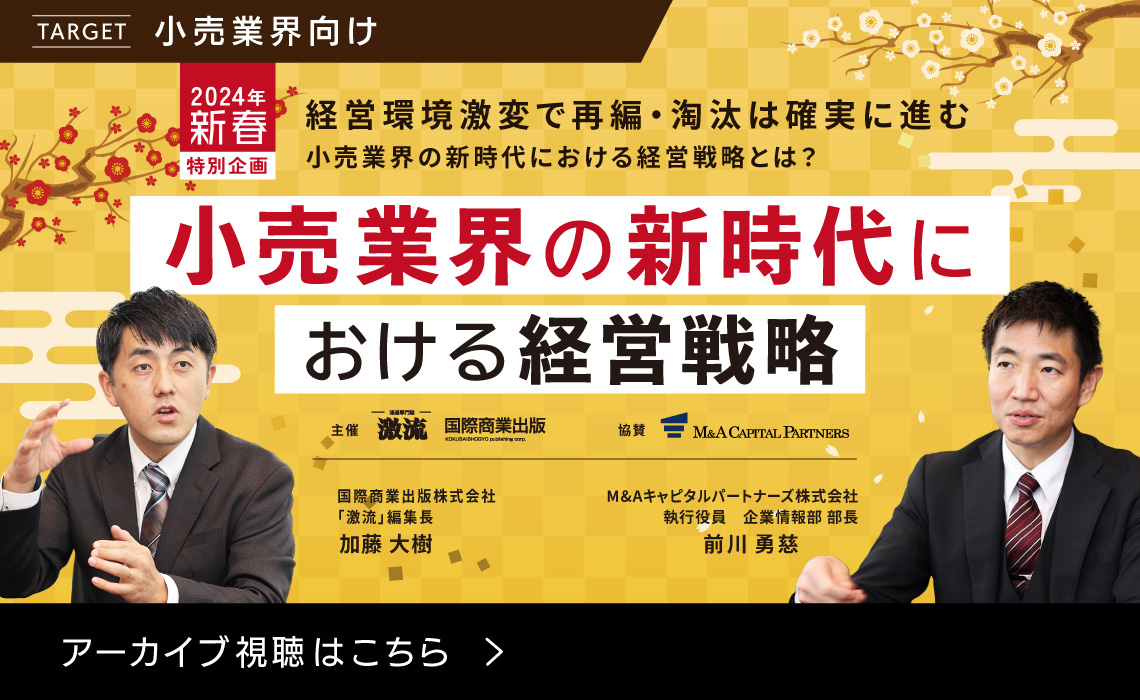 小売業界向け録画配信
小売業界向け録画配信配信期間
2024年5月31日(金)まで
詳細はこちら -
録画配信
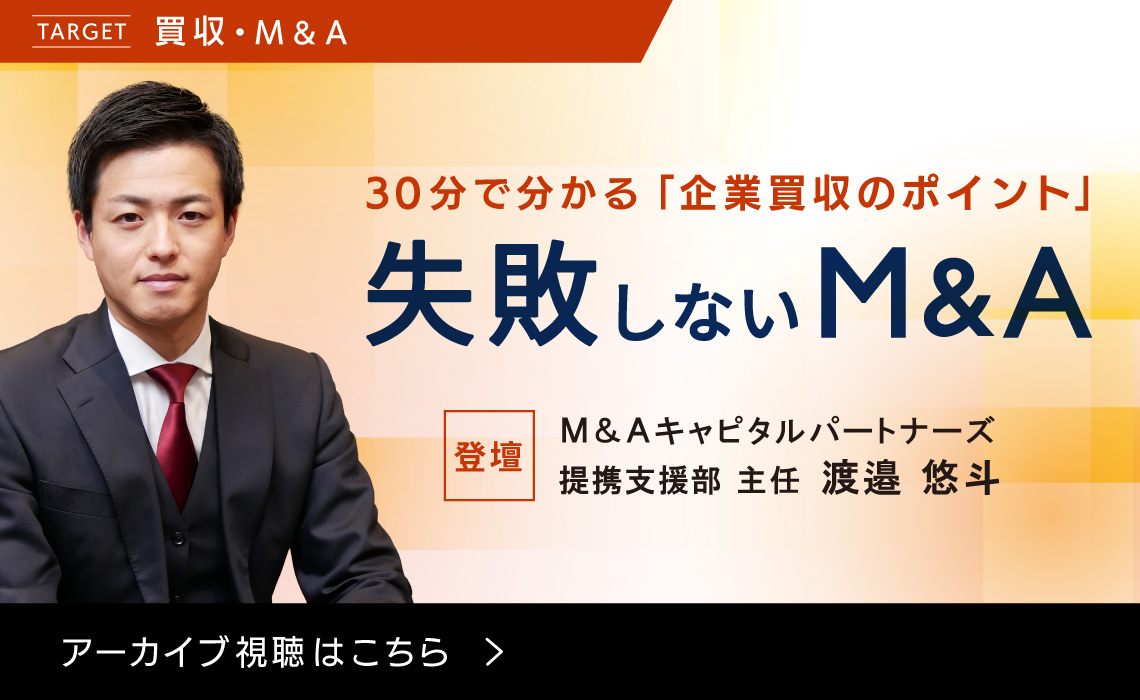 買収・M&A録画配信
買収・M&A録画配信配信期間
2024年5月31日(金)まで
詳細はこちら -
録画配信
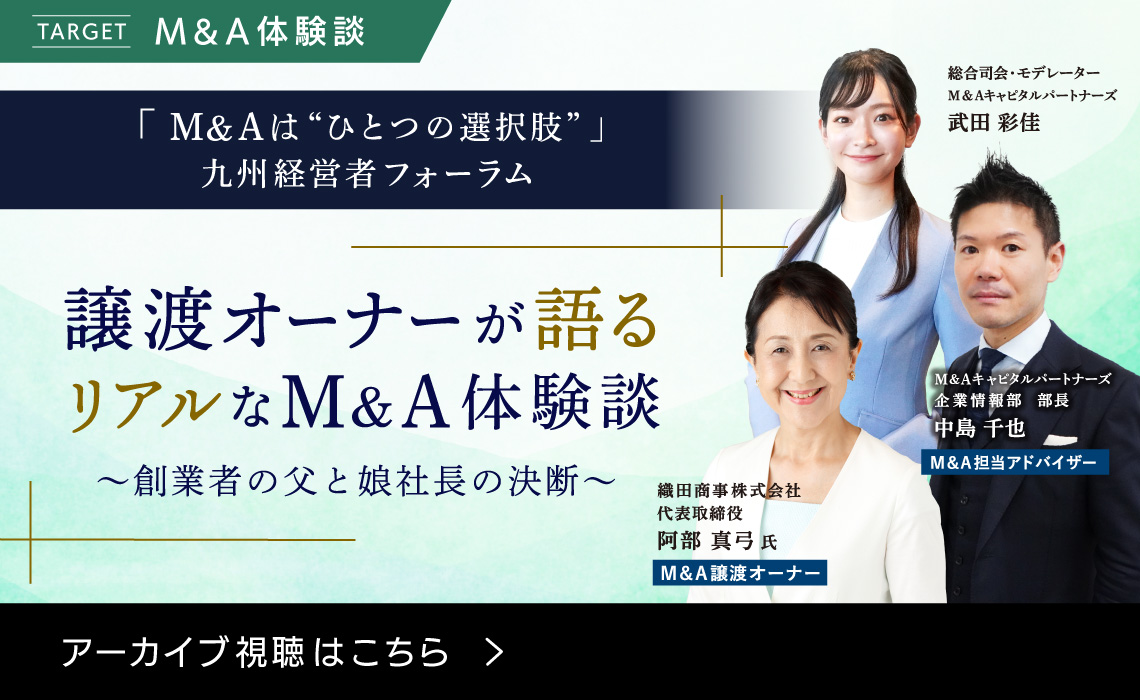 M&A体験談セミナー録画配信
M&A体験談セミナー録画配信配信期間
2024年5月31日(金)まで
詳細はこちら
お知らせ
-
お知らせ2024-04-26
-
お知らせ2024-04-25
-
お知らせ2024-04-18
M&A関連記事
-
M&A基礎知識2023-07-10
-
事業承継2023-06-06
-
M&Aの流れ2023-05-02
M&Aニュース
-
M&Aニュース2024-05-01
-
M&Aニュース2024-05-01
-
M&Aニュース2024-04-30
IR情報
-
決算2024-04-26
-
決算2024-04-26
-
お知らせ2024-04-26












