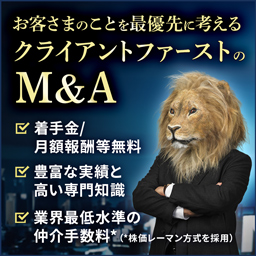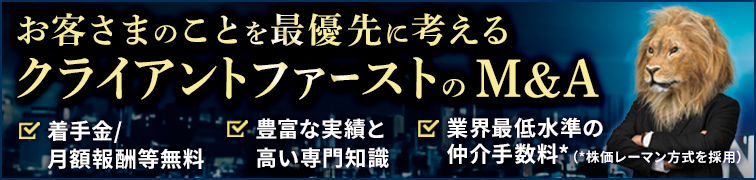更新日
企業の買収や合併を意味するM&A。従来は、大企業が既存事業の拡大や新規事業の立ち上げを目的として行われるケースが一般的でしたが、最近では中小企業の事業承継において有効な選択肢の一つとして注目を集めています。
M&Aは、専門家への相談から始まりますが、相談先の選び方を迷うこともあるでしょう。また、どのような相談内容が多いのかも気になるところです。
この記事では、M&Aの相談先について、特徴やメリット・デメリットを徹底解説します。ワンストップで対応が可能な相談先も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. M&A実施にあたっての相談内容
M&Aを実施するにあたっての相談内容には、どのようなものがあるのでしょうか。売り手企業と買い手企業に分けて、それぞれ見ていきましょう。
1-1. 売り手企業の相談内容
売り手企業の相談内容としては、次のような項目があげられます。
- M&Aを実施すべきか
- 相手となる企業は見つかるのか
- 売却価格を高める方法
- M&Aの手順
- 機密情報の守り方
- M&A完了までの期間
- M&Aにかかる費用
M&Aは完了までに膨大な手間と時間がかかりますが、成功する保証はありません。また、自社に売却するほどの価値があるのかどうか不安に思う経営者も多く、「そもそもM&Aを実施すべきなのか」「相手となる企業は見つかるのか」という相談が寄せられます。
また、会社を少しでも高値で売却する方法も、売り手にとって大きな関心事です。具体的な施策としては、技術力やブランド力を強化し、将来的な収益力を向上させることが有効でしょう。
その他、M&Aの手順や機密情報の守り方、M&Aにかかる期間、費用といった実務的な相談も多く寄せられます。
1-2. 買い手企業の相談内容
買い手企業の相談内容としては、次のような項目があげられます。
- 資金繰り
- M&Aの準備
- 買い手企業側が行う手続き
- M&A完了までの期間
M&Aには多額の資金が必要になるため、買い手企業にとって資金繰りは大きな課題です。具体的にどの程度の資金が必要で、どう調達するかといった相談が寄せられます。
また、買い手企業側の準備や手続きに関する相談も多く、あらかじめやるべきことを確認してリソースを確保しておきたいという意図が見て取れます。
M&Aにかかる期間は、売り手・買い手の双方から相談が多い項目です。
2. M&Aの相談先一覧
M&Aの相談先を表にまとめました。それぞれの特徴やメリット、デメリットについては、このあと詳しく解説します。
| 相談先 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| M&A仲介会社 |
・第三者の中立的な立場でM&Aをサポート |
・ワンストップで依頼が可能 |
・仲介手数料が発生する |
| 銀行などの金融機関 |
・資金調達と融資の相談が主な役割 |
・M&A専門の窓口がある |
・小規模な企業のM&Aには対応していないことが多い |
| 商工会議所などの団体組織 |
・地域の中小企業を対象としたM&A・事業承継支援を手がける公的機関 |
・中小企業同士のM&Aに強い |
・商工会議所の会員になるために費用がかかる |
| 事業承継・引継ぎ支援センター |
・各都道府県に設置されているM&A・事業承継専門の公的機関 |
・全国に相談窓口があり地方都市でも相談しやすい |
・手がけるM&Aは事業承継を目的としているため取扱件数が少ない |
| 弁護士 |
・法的リスクの検出と対策のための交渉や助言が可能 |
・不備の無い契約書が確実に作成できる |
・財務・税務面の知見が不足している可能性がある |
| 公認会計士や税理士 |
・M&Aに必要な税務・財務・会計の手続きのトータルサポートが可能 |
・M&Aに必要な財務や会計に関する高度な専門知識がある |
・サポート範囲が財務に限られる可能性がある |
2-1. M&A仲介会社
ここでは、M&Aの相談先としてM&A仲介会社を選んだ場合に相談できる内容と、メリット・デメリットを解説します。
対応できる内容
M&A仲介会社は、M&Aを考えている企業同士の間に入り、中立的な立場でM&Aを進めるサポートを行います。双方の企業へのヒアリングに始まり、条件交渉から計画立案、契約締結、クロージングまで、ワンストップでクライアントのM&Aを成約まで導きます。
仲介会社のなかには、FA(ファイナンシャル・アドバイザリー)として、譲渡側か譲受側どちらかの専属アドバイザーとして、M&Aのサポートを実施するところもあります。
依頼のメリット
M&A仲介会社に依頼するメリットは、独自のネットワークからM&Aの相手候補を探せることで、希望に沿ったM&Aが実現しやすい点です。また、M&Aの専門家として豊富な知識や実績を持ち、実行やアフターフォローまで幅広くサポートしてもらえます。
M&Aに関する業界ごとの傾向や最新情報、発生する費用の相場など、提供できる情報も多岐にわたるため、M&Aに関する細かい相談にも乗ってもらえるでしょう。
依頼のデメリット
M&A仲介会社にサポートを依頼すると、売却金額の5〜10%程度の成功報酬が発生するのが一般的です。規模の小さいM&Aでも数百万円単位の報酬が必要になる場合もあり、買い手企業にとって大きな負担となる可能性があります。
また、仲介会社によっては、相談料や着手金の支払いが必要になるところもあるため、契約内容をよく確認する必要があります。
ワンストップで依頼できる分、費用が高めになる点がM&A仲介会社のデメリットといえるでしょう。
2-2. 銀行などの金融機関
ここでは、M&Aの相談先として銀行などの金融機関を選んだ場合に相談できる内容と、メリット・デメリットを解説します。
対応できる内容
M&Aにおける銀行などの金融機関の役割は、資金調達と融資の相談に乗ることです。近年は、M&Aの需要の増加に伴って、専門窓口を設けている銀行も増えています。
M&Aの買い手企業にとって、融資が得られるかどうかは重要な意味を持ちます。融資にあたっては金融機関が独自の基準で審査を実施しますが、仮に審査に通らなかった場合、そのM&Aはリスクが高いということかもしれません。M&Aの直接的なサポートとは異なりますが、金融機関の観点でM&Aの実施を見直せる可能性もあるでしょう。
依頼のメリット
大規模な金融機関はM&Aの相談を専門に請け負う窓口を持ち、知識や経験が豊富な担当者に相談することが可能です。M&Aでは避けて通れない資金繰りの問題についても、専門家の目線で適切にアドバイスしてくれるでしょう。
また、弁護士や公認会計士のような専門家と同様に、金融機関は企業との結びつきが強く、定期的な訪問などのサポートも期待できます。
依頼のデメリット
金融機関が対応しているのは、基本的に大企業が実施するM&Aです。中小企業やスタートアップなど、比較的小規模な企業のM&Aは相談を受け付けていないことがあるので注意しましょう。仮に相談できたとしても、会社の規模に見合ったM&A先が見つからない可能性があります。
主要な金融機関は、ファイナンシャル・アドバイザーとしての報酬も高額になる傾向があり、大規模な組織になるためフットワークが軽いとはいえない点もデメリットです。
2-3. 商工会議所などの団体組織
ここでは、M&Aの相談先として商工会議所などの団体組織を選んだ場合に相談できる内容と、メリット・デメリットを解説します。
対応できる内容
商工会議所は、地域の商工業の改善・発展をサポートする非営利の公益経済団体です。業務の一環として、中小企業を対象としたM&A・事業承継支援を手がけています。相談は無料で、必要に応じて各分野の専門家を紹介してもらえます。
近年、後継者不足によって廃業を考える中小企業の経営者が増えており、事業承継の手段の一つとしてM&Aが注目されています。商工会議所は、M&Aや事業承継の必要性の認識や、経営状況・課題の可視化を重要視し、積極的に支援を行っています。
依頼のメリット
商工会議所などの公的機関は、中小企業の経営支援実績が豊富です。そのため、中小企業同士のM&Aであれば、相談するメリットが大きいといえるでしょう。中小企業の文化や内情を熟知しており、適切なアドバイスがもらえます。
地域密着型で相談しやすい点も、商工会議所ならではのメリットです。地元の中小企業の支援を通じて築いたネットワークは、M&Aにも大いに活用できます。
依頼のデメリット
商工会議所に相談するデメリットは、商工会議所の会員になるために費用がかかることです。相談から着手までは無料で応じてもらえますが、より充実したサポートを受けるためには、年会費を支払って会員になる必要があります。
また、公的機関であるがゆえに、スピード感のある対応が期待できないことも考えられます。サービス内容も、民間企業の有料サービスよりも劣る可能性があります。
2-4. 各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センター
ここでは、M&Aの相談先として各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターを選んだ場合に相談できる内容と、メリット・デメリットを解説します。
対応できる内容
事業承継・引継ぎ支援センターとは、後継者問題を抱える中小企業や小規模事業者を対象としたM&A・事業承継の公的な専門機関です。各都道府県に設置されており、事業承継や会社の引継ぎに関するアドバイスや情報提供、マッチング支援を行っています。
大規模な案件やスキームが複雑な事業承継の場合は、外部の専門家にサポートを依頼することもあります。
依頼のメリット
全国に相談窓口があり、地方都市でも相談しやすいのがメリットです。地元とのつながりが強く、地方自治体による法制度に関する情報を得られるだけでなく、必要に応じて専門家のネットワークを通じた紹介が受けられます。
公的機関であることから相談料は無料で、第三者目線の公平なアドバイスがもらえるでしょう。民間のM&A仲介会社や金融機関では相談が難しい、小規模なM&Aにも対応可能です。
依頼のデメリット
事業承継・引継ぎ支援センターは、事業承継を主な目的とした公的機関です。M&A案件も事業承継を目的としたもので、取扱件数が少ないうえに複雑なスキームには対応できない点がデメリットです。スピード感のある対応も難しい可能性があります。
また、M&Aを実施する場合も地元のつながりを中心に進めるため、幅広くM&Aの相手先を探したい場合はM&A仲介会社に依頼したほうが、条件に合致した企業が見つかりやすいでしょう。
2-5. 弁護士
ここでは、M&Aの相談先として弁護士を選んだ場合に相談できる内容と、メリット・デメリットを解説します。
対応できる内容
M&Aにおいて弁護士が果たす役割は、法的リスクを検出し、対策を行うための交渉・助言です。また、M&Aでは秘密保持契約(NDA)などの契約を締結するため、弁護士のような法の専門家に作成・レビューを依頼することは重要な意味を持ちます。
M&Aを進める途中で、会社法や金融証券取引法に従った形で各種手続きが行われているかどうかの確認も依頼できます。さらに、譲渡側と譲受側の企業間で訴訟に発展しそうな事態が発生しても、弁護士であれば法的な観点から適切なアドバイスを行えます。
依頼のメリット
弁護士にM&Aの相談をする最大のメリットは、各種契約書を正しく、確実に作成してもらえることです。
秘密保持契約書やアドバイザリー契約書、基本合意書など、M&Aではさまざまな契約を締結します。少しでも不備があるとのちのトラブルにつながることがあるため、法律家の目線で間違いの無い契約書を作成してもらうことは重要です。
また、相手企業とのトラブルが発生した場合にも、法の専門家であれば安心して任せられるでしょう。もともと顧問を依頼している弁護士や弁護士事務所であれば、既に信頼関係ができているため、すり合わせもスムーズに進みます。
依頼のデメリット
弁護士に依頼するデメリットとして、財務・税務面の知見が不足している可能性があげられます。
企業価値の算定や、企業の財務状況や収益性を分析する財務デューデリジェンスには、税務・財務・会計の知見が欠かせません。M&Aを進めるうえで充実したサポートを受けるためには、弁護士と平行して公認会計士や税理士への依頼が必要になるため、管理工数が増えてしまいます。
2-6. 公認会計士や税理士
ここでは、M&Aの相談先として公認会計士や税理士を選んだ場合に相談できる内容と、メリット・デメリットを解説します。
対応できる内容
公認会計士や税理士は、企業価値の算定や財務デューデリジェンス、税金対策など、M&Aに必要な税務・財務・会計の手続きのトータルサポートが可能です。会計士の監査や会計に関する専門領域は、M&Aを成立させる鍵となります。
税理士は税務申請やM&A関連の節税対策を適切に進める役割を担い、会計士は企業価値の算定や財務デューデリジェンスを支援します。
依頼のメリット
公認会計士や税理士に相談するメリットは、M&Aに必要な財務や会計に関する高度な専門知識を持つことです。M&Aの実施においては、相手先企業に簿外債務や保証債務などのリスクが潜んでいることがあります。公認会計士や税理士に相談することで、会計や財務面の問題を見落とすこと無く洗い出せます。
また、公認会計士や税理士は、顧問契約などで中小企業との付き合いが多く、内情を深く理解しています。既に顧問契約を結んでいる専門家であれば財務状況も把握しているため、相談もスムーズに進むでしょう。
依頼のデメリット
公認会計士や税理士に依頼する主なデメリットは、必ずしもM&Aに精通しているとは限らないことです。顧問契約している公認会計士・税理士がM&Aのサポートを実施していないこともあり、依頼ができたとしてもサポートしてもらえる範囲が財務に限られる可能性があります。
また、M&Aで重要なポイントとなる相手先の企業探しについても、ノウハウが不足している可能性があります。
3. M&Aの相談先を選ぶポイント
M&Aを成功させるには、自社の状況や目的に合った相談先を選ぶことが重要です。そのためのポイントをいくつか見ていきましょう。
3-1. 実績豊富で専門性が高いかどうか
M&Aには税金や法律の問題が絡んでくるため、高い専門性が求められます。また、実績が豊富であることも、M&Aを成功させるうえで重要なポイントです。
相談先を選ぶ際は、M&Aを手がけたことがある業界や業種、企業規模といった詳細を確認しましょう。自社の業種や企業規模に近い案件の実績が豊富であれば、ノウハウが溜まっていることが期待できます。
担当者と密にやり取りすることも成功のポイントになるため、実績や専門性に加えて、信頼できる担当者かどうか見極めることも大切です。
3-2. 必要な情報を漏れ無く提供してくれるか
M&Aの交渉から実行、M&A後の業務統合といった一連のプロセスには、年単位の時間がかかります。担当者は、M&Aの各フェーズでやるべきことを深く理解し、企業に対して適切に情報を提供しなければなりません。
依頼前のヒアリングの段階から円滑にコミュニケーションを取ることができ、細かいことに対しても迅速かつ親身になって対応してくれる担当者であれば、M&Aの完了までスムーズに進むでしょう。
3-3. 依頼した際の費用が妥当かどうか
M&Aには多くの費用がかかるため、自社の評価額に見合った報酬を設定しているM&A会社を探しましょう。
あとから想定外の費用がかかることを避けるため、料金体系が明確な相談先を選ぶのも大切なポイントです。主な費用はM&Aが成立した際にかかる成功報酬ですが、それ以外にも相談料や着手金、月額報酬、中間金などが発生することもあるため、契約内容をよく確認したうえで進めることが重要です。
3-4. 情報管理を徹底しているか
M&Aを進めるにあたって、相談先となる専門家や仲介会社、公的機関は、売り手側企業と買い手側企業の経営や財務の状況といった機密情報を得ることになります。
不要な情報が相手方に漏れてしまうと大きな問題に発展することがあるため、情報管理を徹底しているかどうかも相談先を選ぶ際のポイントになります。NDA(秘密保持契約)の締結など、情報漏えい対策をしっかりと行っている相談先を見極めることが大切です。
3-5. 相談先の数は増やしすぎない
少しでも良い条件でM&Aを実施するために、複数の相談先に並行して打診をすることもあるでしょう。しかし、相談先を増やし過ぎると情報漏えいのリスクが高まります。
さらに、相談先が増えることで買い手企業の重複が発生し、良い条件が引き出せなくなる可能性もあります。相談先は、ここなら信頼できると思ったパートナーに絞り、増やし過ぎないよう注意しましょう。
4. まとめ
M&Aの相談先には、弁護士や公認会計士・税理士、金融機関、M&A仲介会社など、さまざまな選択肢があります。どの相談先にもメリットとデメリットがあり、相談できる範囲も異なるため、目的に合わせて選ぶことが大切です。
ワンストップで依頼したいのであれば、M&A仲介会社の利用がおすすめです。M&Aのノウハウや経験が豊富な専任の担当者がヒアリングを丁寧に行い、要件定義から交渉、契約締結、クロージングまで、必要に応じて専門家に協力を求めながら手続きを進めます。
M&AキャピタルパートナーズはM&Aの仲介会社として、東証プライム上場の信頼性と確かな実績があります。M&Aをお考えの方は、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
M&Aの相談先に関するよくある質問
-
どこに相談したら良いか判断がつかない場合はどうする?
-
ワンストップで依頼できる相談先を希望するのであれば、M&A仲介会社がおすすめです。必要に応じて専門家に協力を求めながらトータルサポートしてくれます。実績が豊富な会社を選ぶと、交渉や手続きがスムーズに進むでしょう。
-
相談先の実績を確認することはできる?
-
ホームページなどにM&Aの成功事例が掲載されているかどうか確認してみましょう。また、直接問い合わせをすると教えてもらえる場合があります。
-
相談前に専門知識があるか判断する方法は?
-
サポート実績を参考にすると良いでしょう。自社の業種や規模感に近いM&Aの実績が豊富な相談先であれば、専門的なノウハウが蓄積されていることが期待できます。
-
途中で解約した場合の相談費用はどうなる?
-
M&Aのアドバイザリー契約を締結している場合は、解約によって違約金がかかることがあります。契約内容によっては途中解約ができないこともあるので、よく確認したうえで申し込みましょう。