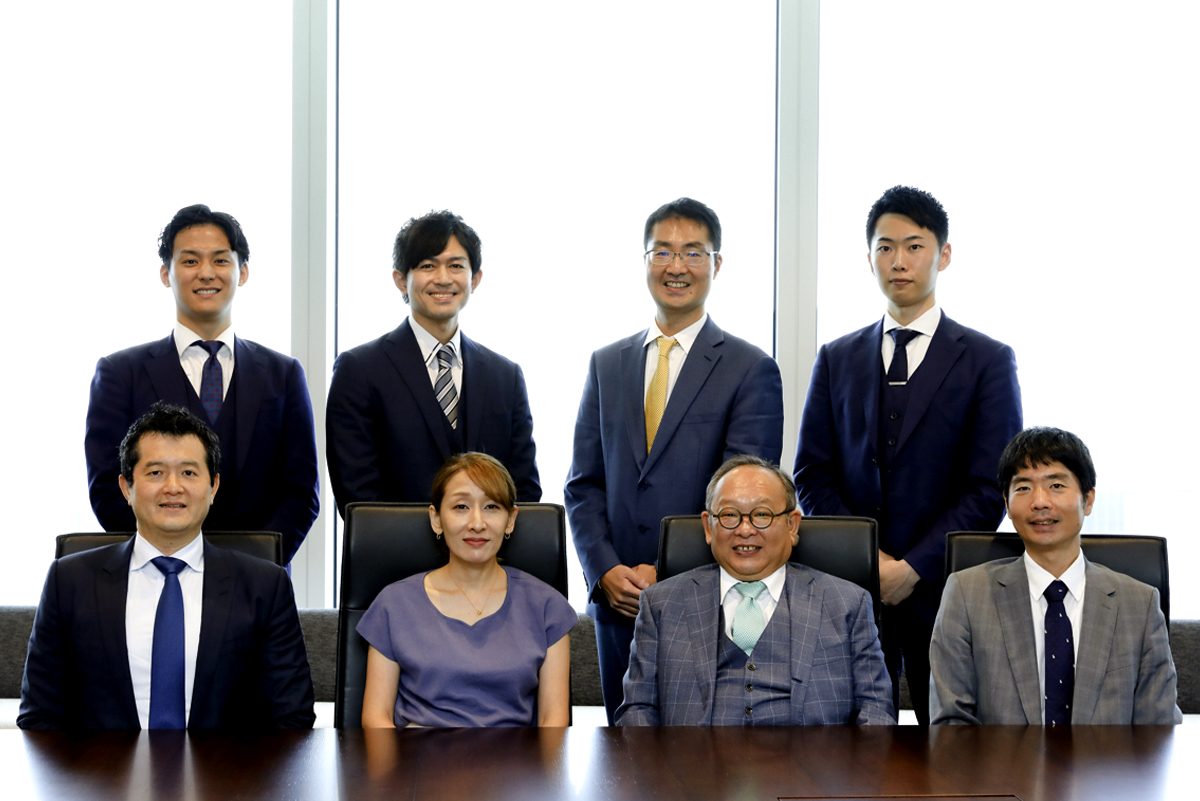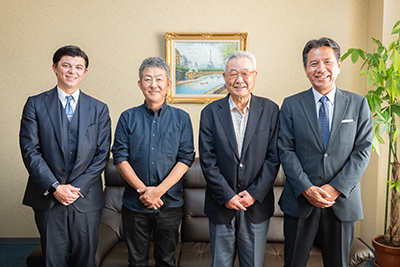更新日
日本の企業間におけるM&A(Mergers and Acquisitions、合併・買収)の動きは、近年、増加しています。M&Aは企業の成長戦略の一環として行われる一方、敵対的な買収として進められる場合も存在します。企業が敵対的な買収をしようとする場合、このような状況で登場するのが「キラー・ビー(Killer Bee)」です。今回は、キラー・ビーの概要、メリットとデメリット、事例について、詳しく説明します。
このページのポイント
~キラー・ビーとは?~
キラー・ビーとは、企業が敵対的買収を仕掛けられた場合に、その企業を特に買収から防御するために雇われる金融顧問や法律顧問を指す。一般的には、敵対的買収を仕掛けられた企業側のM&Aアドバイザー(投資銀行などの金融顧問や弁護士などの法律顧問)が、キラービーとなる。
1. キラー・ビーの概要
1-1. キラー・ビーとは?
キラー・ビーとは、企業が敵対的買収を仕掛けられた場合に、その企業を特に買収から防御するために雇われる金融顧問や法律顧問を指します。 一般的には、敵対的買収を仕掛けられた企業側のM&Aアドバイザー(投資銀行などの金融顧問や弁護士などの法律顧問)が、キラービーとなります。 キラー・ビーの語源は、研究目的でブラジルに輸入されたアフリカ産のミツバチのことです。 このミツバチは強い攻撃性を持っており、かつ、しつこく相手を攻撃する特性を持っています。 同様にキラー・ビーも、敵対的買収が仕掛けられると、防衛だけに留まらず相手企業をしつこく攻撃します。これは買収を仕掛けられた企業側にとっては、キラービーの存在は非常に心強いといえます。
2. M&Aにおけるキラー・ビー
敵対的買収では、買収側はしばしば株主価値を最大化するという名目で買収を正当化します。これに対して、キラー・ビーは敵対的買収を仕掛けられた企業に買収防衛策(ポイズン・ピル(Poison Pill)、ホワイトナイト(White Knight)、ゴールデンパラシュート(Golden parachute)など)を提案し、経営陣や株主の利益を守る役割を果たします。
3. キラー・ビーのメリットとデメリット
キラー・ビーに依頼するメリットとデメリットは以下のとおりです。
3-1. メリット
- 企業が望ましいと考えない買収から自身を守ることができる。
- 企業買収を仕掛けられた企業の株主にとってより良い条件の交渉が可能になる。
3-2. デメリット
- 高額な顧問料がかかることがある。
- 敵対的防衛策が過剰になると、将来的な買収の可能性を狭めることもある。
4. キラー・ビーの事例
具体的なキラー・ビーの事例としては、多くの大手企業が敵対的買収の際に金融顧問や法律顧問を雇用していると考えられます。日本におけるキラー・ビーの事例は、米国のような敵対的買収が頻繁に起こる環境とは異なり、敵対的買収自体がそこまで多くないため、顕著な事例は限られていますし、キラー・ビーの存在が表にでることはあまりありません。しかし、日本においても敵対的買収は発生しており、企業が自身の経営権を守るための対策や対応が重要であることからキラー・ビーに依頼することもあることが考えられます。敵対的買収においては、買収を仕掛ける側と対象企業側の互いの経営方針や株価戦略などを比較し、株主がどちらの経営方針が適しているかを検討することになります。
5. まとめ
M&Aの世界において、キラー・ビーは重要な役割を果たします。敵対的買収から企業を守るための金融顧問や法律顧問として、彼らは多岐にわたる戦略を提供し、依頼した企業の自立と成長をサポートしています。その活動は、企業経営だけでなく、株主価値にも直接的な影響を与えるため、M&Aにおけるその存在と役割は非常に重要です。