更新日
親族外承継について
親族外承継では、親族ではない第三者に事業を引き継ぎ、会社の存続と発展を図ります。親族内での事業承継が難しいケースが増加している中、多くの経営者が親族外承継に注目しています。内部昇格や外部招へい、M&Aなど、さまざまな手段を活用すれば、経営の安定性を確保しつつ、次世代の発展を目指すことが可能です。
本記事では、親族外承継の概要や方法について触れたうえで、メリット・デメリット、実施する際の流れ、成功に向けたポイントなどについても詳しく解説します。
このページのポイント
~親族外承継とは?~
親族外承継とは、親族ではない第三者に事業を引き継ぐことです。この記事では、親族外承継の概要や方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。内部昇格や外部招へい、M&Aなどの手法を紹介し、成功に向けたポイントも説明します。
関連タグ
- #M&A
- #M&A関連記事
- #事業承継
- #親族外承継とは?
~その他 M&Aについて~
目次
親族外承継とは
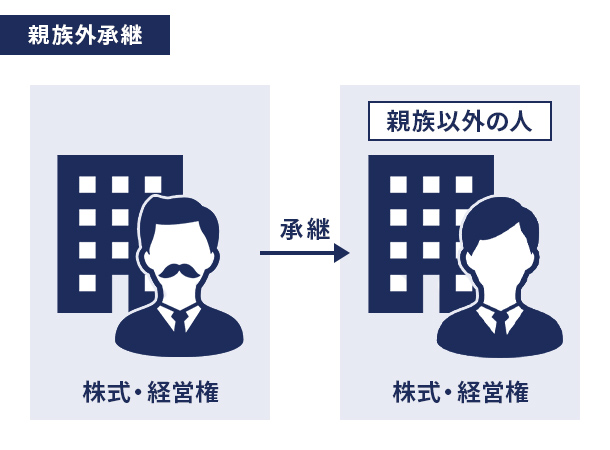
親族外承継とは、血縁や親族関係ではない第三者に事業を引き継ぐことです。承継先は、社内の人材か、社外の人材かの2通りに大別できます。
社内の人材から選ぶ際の手法としては、役員や従業員による内部昇格、MBO(マネジメント・バイアウト)、EBO(エンプロイー・バイアウト)などが代表的です。
社外の人材から選ぶ際の手法としては、外部の経営者を招へいするケースやM&A(企業買収・合併)による承継があります。
それぞれの手法の詳細については後述します。
親族外承継と親族内承継の違い
親族外承継との違いは、承継先が「戸籍上の親族であるか」どうかです。
親族内承継とは、経営者の子供や親族などに事業を引き継がせる方法です。
親族内で事業を引き継ぐことは既定路線だと思われている場合も多く、取引先や従業員とのトラブルが生まれにくい承継方法といえます。
ただし、経営者の子どもや親族とはいえ、本当に経営能力を持っているかは別問題です。
承継後に経営が傾き事業を辞めなければならない可能性もあるため、本当に承継させるかは、冷静に判断する必要があります。
親族外承継と第三者承継の違い
第三者承継とは、親族外承継のうち、承継先が社外の第三者であるものを指します。M&Aを活用したり、外部から経営者を招へいしたりするケースが該当します。一方、既存の役員や従業員が承継先となるケースは、親族外承継ではあるものの、第三者承継には該当しません。
比較すると、第三者承継では、それまで自社になかった新たな視点や専門性を取り入れることで、事業の拡大が期待できます。一方、第三者承継ではない親族外承継では、事業の継続性が高くなる点が特徴です。
親族外承継の現状

日本における親族外承継は、近年大きな転換期を迎えています。
2024年の調査によると、事業承継の形態として「内部昇格」が36.4%を占め、従来主流だった「同族承継」(32.2%)を初めて上回りました。また、M&Aなどによる外部への承継が20.5%、外部からの経営者招へいが7.5%と、社外人材を承継先とするケースが増加しています。
こうした「脱ファミリー化」の進展には、経営者の高齢化や後継者不足が背景にあります。

全国の中小企業では、後継者不在率が52.1%に達しており、これが事業承継が多様化している要因の一つです。さらに、事業承継税制や各種支援制度の充実も、親族外承継を後押ししています。

後継者候補の属性にも変化が見られます。2024年は「非同族」が全体の39.3%を占め、3年連続で最多となりました。特に、現代表者が外部から招聘された企業では、後継者候補が非同族となる割合が9割に達しており、外部人材への期待の高まりを示しています。
これらの背景を踏まえ、事業承継の手段として、親族外承継は今後より一般的になっていくことが見込まれます。
親族外承継の方法
親族外承継には、経営のみを承継する方法と、自社株式を含めて承継する方法の2種類があります。それぞれ紹介します。
経営を承継する方法
経営のみを承継する場合、現オーナーが株式を保有したまま、経営権を親族外の人材に引き継ぎます。この方法には、内部昇格と外部招へいの2つのアプローチがあります。
内部昇格
内部昇格とは、社内の役員や従業員を後継者として選定し、経営を引き継ぐ方法です。
この方法の利点は、後継者が会社の業務や文化に精通しているため、円滑な引継ぎが可能な点にあります。従業員のモチベーションや、社内の一体感を維持しやすいことも特徴です。
一方で、新しい視点や斬新なアイデアを欠く可能性がある点には注意が必要です。
外部招へい
外部招へいは、取引先企業や金融機関など、社外から経営者を招いて事業を承継する方法です。
この方法では、新しい視点や専門知識を経営に取り入れることによる、企業の競争力向上が期待できるでしょう。また、業界動向や最新の経営手法に精通した人材を迎えることで、企業の成長が促進される可能性があります。
ただし、社内文化との融和や従業員との関係構築には、時間を要する場合があります。
自社株式を承継する方法
自社株式を承継する場合は、経営権だけでなく株式や事業用資産も親族外の人材に引き継ぎます。この方法には、MBO・EBOとM&Aの2つのアプローチがあります。
MBO・EBO

MBO(Management BuyOut)は経営陣が、EBO(Employee BuyOut)は従業員が、それぞれ自社株式を取得する方法です。
この方法の利点は、会社の事情に精通した人材が経営を引き継ぐことによる、事業の継続性が高い点にあります。また、従業員のモチベーション向上や、オーナーシップ意識の醸成にもつながります。
一方で、株式取得のための資金調達が課題となる場合があり、金融機関からの融資や補助金の活用が必要です。
M&A
M&A(Mergers and Acquisitions)は、外部の企業や個人に自社株式や事業を売却し、承継する方法です。
この方法の利点は、幅広い候補者の中から承継先を選択できることです。社内外問わず後継者を広く探せるため、親族や従業員に適任者がいない場合でも事業承継が実現できます。また、売却により得られる資金を、オーナーの退職金や事業拡大に活用できる点も魅力です。
一方で、従業員の雇用維持や取引先との関係構築など、多くの調整が必要になるため、専門家の助言を得ることが望まれます。
親族外承継のメリット
親族外承継の主なメリットとしては、以下が挙げられます。
それぞれ見ていきましょう。
後継者選択が自由になる
親族内承継では、自社を良く知っている人材に承継できる反面、子どもや親族内の狭い範囲で後継者を選ばなければならないため、適任者が見つけられない可能性があります。
しかし、親族外承継は、社内社外問わず多くの人材を後継者候補として選べるため、本当に自社に合った人材へ承継させられます。
また、ヘッドハンティングという形で優秀な人材に承継できれば、業績や会社の規模を拡大することができるでしょう。
経営の一体性を確保できる
自社で勤務したことのない子供や親族が承継する場合、経営の方針や理念が大きく変わり、業務内容や進め方が大きく変わる可能性があります。
一方、親族外承継を行い、社内の幹部や長期間勤務している従業員に引き継ぐことができれば、事業の方向性が大きく変わる可能性は低いといえます。
親族外承継のデメリット
親族外承継には多くの利点がありますが、以下のようなデメリットも存在します。
一つずつ解説します。
関係者からの理解獲得に時間を要する
親族外承継では、親族内承継と比べて、関係者からの理解を得るために多くの時間と努力を要します。
親族外承継では、親族外の後継者に株式を集中して譲渡する手法が多く取られます。しかし、これに対して親族内の株主が、議決権比率が低下することに不満を示し、協力を得られないケースも見られます。
また、経営権移転にともない、取引先や従業員などのステークホルダーが不安を抱くことも考えられるでしょう。
こうした不満や不安を払拭し、円滑な承継を実現するためには、透明性のある説明や丁寧な対話が欠かせません。
個人保証の引き継ぎに多くのコストを要する
経営者保証が事業承継の障害となっていると回答した企業は全体の約60%を占めています。
このような課題を解消するためには、後継者への保証負担を軽減する手段や、金融機関との連携による調整が不可欠です。また、経営者保証ガイドラインの活用も選択肢の1つとして検討されるべきでしょう。
株式を承継する場合、購入に伴う後継者の負担が大きい
親族外承継では、自社株式や事業用資産を後継者が購入する必要がある場合が多く、これが大きな障壁となることがあります。
特に、後継者が十分な資金を持たないケースでは、事業承継の実現が難しくなることもあるでしょう。こうした問題を解決するためには、MBOなどの手法により、資金調達のハードルを下げることも検討する必要があります。
株式譲渡による親族外承継の流れ
株式譲渡により親族外承継する場合を例にあげて解説する
1.後継者の選定
安定した会社経営ができる優秀な後継者を探すことが最も重要です。
MBOであれば、後継者の人柄や能力を十分に把握しているうえで、自社に理解もある人材を選ぶことができるため、安心して事業を任せられるでしょう。
一方、外部招へいの場合には、これまでの自社になかった新しいビジネスが生まれるかもしれません。
これからの自社に何を期待するのか、どういう未来を描いているのかを明確にして後継者選びを行いましょう。
2.株式譲渡の交渉
後継者候補との株式譲渡の交渉です。
一般的に株式の譲渡価格は、貸借対照表や損益計算書やキャッシュフローの状況など、企業価値の客観的な評価によって決定されます。
企業価値の客観的な評価は、会計事務所が専門的に行っているため、スムーズな承継のためには、会計事務所との円滑な連携が必要です。
また、主な議題は株式の譲渡価格になりますが、従業員の雇用維持や会社経営の方針などが条件として付与されるケースもあります。
3.株式譲渡契約の締結
後継者と株式譲渡の条件が合致すれば、内容を株式譲渡契約にまとめて、経営者と後継者の間で契約を締結させます。
株式譲渡契約書は、契約条件を網羅的にわかりやすく記載することが重要です。
双方での認識が変わる記載をしてしまうと、締結後にトラブルになる可能性があります。
トラブルを防ぐために、株式譲渡契約の作成、締結の際は、専門家である弁護士への相談がおすすめです。
4.株式譲渡、株主名簿の書き換え
契約締結後、前提条件が満たされたことを確認してから、株式譲渡を行います。
株式譲渡の実行は、下記のように会社によって各種「会社法」で定められている手続きを行う必要があります。
- 株式会社の場合:株式譲渡について対抗要件を用いるために、名義変更(株主名簿の書き換え)が必要【会社法 第130条 第1項】
- 非公開会社の場合、株式譲渡を行うこと自体に、原則株主総会決議での承認が必要。【会社法 第139条 第1項・第309条 第2項】
ただし、取締役会を設置している企業の場合、取締役会決議の決定で承認を行えます。
親族外承継を成功させるためのポイント
親族外承継を成功させるためのポイントは下記の4つです。
親族外承継は、事前準備が重要です。
ポイントを押さえてスムーズに承継できるようにしましょう。
計画的に後継者を育成する
親族外承継では、後継者を社内、社外問わず多くの人材から選択できます。
そのため自社へのマッチ度や熱意の見極めや後継者としての育成も必要になるため、多くの時間がかかります。
計画的に後継者を探して育成しているほうが、事業を続けていくうえで心理的に安心です。
また、後継者に経営だけでなく事務や営業、製造といった多様な学びの機会を与えることで、業務遂行能力以外に経営能力をさらに向上させられます。
「まだ早い」と思わず、自社を継続して発展させていきたいと考える場合は、できるだけ早い内から後継者候補を探して、育成しておきましょう。
事業関係者に対して丁寧に説明する
先に述べたように、親族内承継に比べて、親族外承継は事業関係者に理解してもらうのに時間がかかる場合があります。
例えば、取引先の金融機関への説明を怠ると、新たな借入ができなくなる可能性もあります。
一般的に、金融機関が中小企業に借入を実行する場合は経営者が個人保証を立てます。
これは、担当者と経営者の信頼関係があってこその承認につながる場合もあるため、無断で承継を行うと信頼関係が崩れてしまいます。
事業関係者への説明は必ず行いましょう。
事業承継税制を活用する
事業承継税制は、非上場企業や中小企業の後継者が株式を相続した際、贈与税や相続税の支払いを猶予または免除する制度です。
この制度の背景には、中小企業経営者の高齢化や、後継者不足による廃業の増加といった社会的課題が挙げられます。特に、優秀な人材への承継が資金面の理由から断念されることの無いよう設立されました。
ただし、この制度の適用を受ける場合、対象となる株式の範囲や承継方法などに細かい制限がかかります。適用条件や手続きについては、公的機関が発表しているマニュアルを参照してください。
制度を適切に活用し、後継者が資金面の負担を軽減できれば、事業承継が円滑に進む可能性が高まるでしょう。
参考:-経営承継円滑化法- 申請マニュアル専門家へ相談する
会社によって抱える悩みや課題は異なります。
そのため、インターネット検索で表示される情報ではカバーしきれず、詳細がわからないケースが多くあります。
自社が抱える疑問を完全に解決したい場合は、専門家への相談がベストです。
事業承継のなかもM&Aを検討されている方は、ぜひ弊社へご相談ください。
経営者様へ寄り添い抱えている課題の解決をサポートいたします。
まとめ
親族外承継は、後継者不在問題の解決策として効果的な手法です。内部昇格やM&Aなど、多様な方法があるため、自社の状況に応じた最適な手段を見極めることが成功の鍵となります。
承継の際は、計画的な後継者育成や関係者への丁寧な説明や、事業承継税制もうまく活用しましょう。また、専門家への相談を通じて、複雑なプロセスや課題を乗り越えるサポートを受けることも有効です。
M&Aキャピタルパートナーズでは、安心して事業承継を進められるよう、専門的な支援を提供しています。
M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。
着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。
以下より、お気軽にお問い合わせください。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
よくある質問
- 親族外承継とは何ですか?
- 親族外承継とは、血縁や親族関係ではない第三者に事業を引き継ぐことです。社内の人材や社外の人材を承継先とすることができます。
- 親族外承継の方法にはどんなものがありますか?
- 内部昇格、外部招へい、MBO・EBO、M&Aなどの方法があります。それぞれの方法には異なる特徴とメリットがあります。
- 親族外承継のメリットとデメリットは何ですか?
- メリットには後継者選択の自由度が高いことや経営の一体性が確保できることが挙げられます。デメリットには関係者からの理解獲得に時間がかかることや個人保証の引き継ぎにコストがかかることがあります。

















