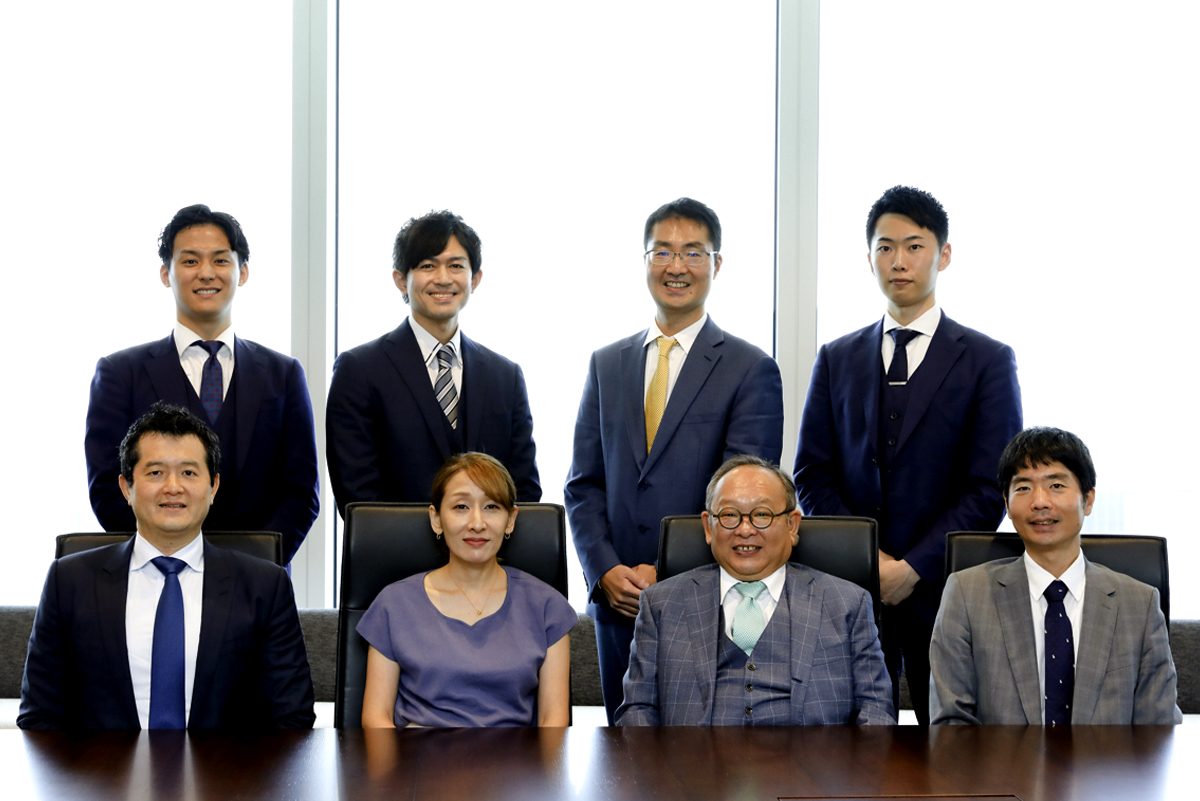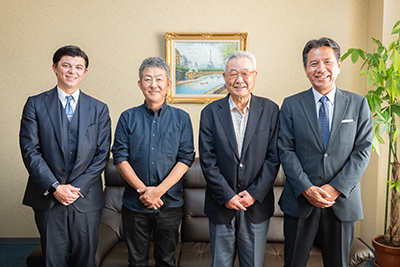更新日
業務提携とは、通常、資本関係を持たない企業同士が業務を協働することを指します。一方の業務委託は、企業が自社の業務の一部を外部の企業や個人に依頼することです。似て非なる両者の概念を理解し、適切に活用することは、企業の成長戦略において重要です。
本記事では、それぞれの定義やメリット・デメリット、どのような状況でどちらを選ぶべきかについて詳しく解説します。自社のビジネス戦略において、適切な選択をするための知識が得られますので、経営判断を行う際の参考にしてください。
このページのポイント
~業務提携と業務委託の違いとは?~
業務提携とは、通常、資本の移動を伴わない形態の提携で、企業が共同で事業を行うことで、業務委託とは、企業が社外の法人や個人に対して仕事(業務)を委託すること。業務提携と業務委託は、相手方との関係性や目的が大きく異なるため、ケースによって使い分けることが重要である。
目次
1. 業務提携と業務委託の違いは?
業務提携と業務委託は、一見似ている言葉ではあるものの、意味するところは大きく異なります。両者の主な相違点は、下表のとおりです。
| 業務提携 | 業務委託 | |
|---|---|---|
|
特徴 |
双方が経営資源を提供しあって |
企業が社外の法人や個人に |
| 双方の関係 | 協力者 | 委託者と受託者 |
|
目的 |
相乗効果によって |
発注者が依頼した業務を |
ここからは、両者の違いを詳しく解説します。
1-1. 業務提携とは
業務提携とは、通常、資本の移動を伴わない形態の提携で、企業が共同で事業を行うことです。企業間で資金・技術・人材などの経営資源を提供し合い、相乗効果(シナジー)を得ることで事業競争力の強化を図ります。
業務提携は、提携する企業間に上下関係は無く、単独では達成できない目標に対し、双方がパートナーとして成果をあげることを目的としてなされるのが一般的です。
具体的な目的としては、新規事業への進出や、販売力・技術力の強化・補充、技術の共同開発などがあります。業務提携の主な種類は、以下をご覧ください。
業務提携の種類
1技術提携
ライセンス契約、共同開発契約等を結び技術を利用する
2生産提携
製造委託契約等を結び、製品を生産する
3販売提携
販売店契約、代理店契約、OEM契約等を結び、商品を販売する
その他
仕入提携、調達提携等
1-2. 業務委託とは
一方、業務委託とは、企業が社外の法人や個人に対して仕事(業務)を委託することです。
受託者は委託された仕事を行い、その成果により報酬を受け取ります。業務委託では、委託者と受託者の間に明確な上下関係が存在します。双方が協力して目標達成を行う業務提携とは異なり、発注者から依頼された業務を受注者が遂行し、完結させることが目的です。
業務委託は、特定の業務を専門的に行うことが可能な外部の専門家への依頼であることが多く、業務効率化やコスト削減の実現が期待できます。しかし、委託する業務の品質管理や情報管理には注意が必要です。
2. 業務提携と業務委託のメリット
業務提携と業務委託には、独自の強みや優れている部分があります。下記では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
2-1. 業務提携のメリット
業務提携には、以下のようなメリットが挙げられます。
他社のリソースを活用できる
業務提携を行った場合、双方の経営資源を共有するため、他社のリソースを活用できます。他社の設備やノウハウを使用するため、既存事業の強化や、必要な設備にかかる費用を抑えることが可能です。
また、提携企業の保有するブランド力や顧客ネットワークも利用できるため、自社だけでは獲得の難しかった顧客層へのアプローチにもつながります。
リスクを分散できる
新規事業の立ち上げや、新たな技術開発には多くのリスクが伴います。しかし、業務提携を行うことにより、提携企業との間でリスクの分散が可能です。事業や開発の規模が大きくなればなるほど、リスク分散のメリットも拡大します。
独立性を保ちながら協働体制を築ける
業務提携では、M&Aや資本提携と異なり、資本によるつながりは無いため、相互に独立性を保ちながら協力関係を築くことが可能です。
仮に、提携企業の業績が悪化したとしても、自社に影響が及ぶことはありません。また、業務提携が失敗したとしても、契約を解除することで、比較的容易に関係性を解消できます。
2-2. 業務委託のメリット
業務委託にも、以下のようなメリットがあります。
社内の人件費を抑えられる
業務委託のメリットは、社内の人件費を抑えることができる点です。
社内に新たな人材を確保する場合、採用活動にかかる費用から、給与や通勤費、社会保険料といった採用後に毎月かかる経費など、多くのコストが発生します。また、即戦力となるまでには、教育や研修の時間が必要です。
一方、業務委託を行う場合、外部のプロに業務を委任することになり、自社でイチから人材を教育する手間もコストもかかりません。発注側の出費としては業務委託料のみで、すぐに専門性の高い役務やサービスの提供を受けられます。
社内人材を効率的に活用できる
社内人材を効率的に活用できる点も、業務委託のメリットです。例えば、専門性の高い知識が必要な業務が発生し、社内人材で賄おうとした場合、業務時間が必要以上に長くなったり、パフォーマンスが低下したりする恐れがあります。
業務委託を利用すれば、難しい業務にかかっていた時間を他の業務に回すことが可能です。手が空いた社内人材の業務適性を見直し、より適切な業務の割り当てができれば、企業全体の生産性向上も期待できるでしょう。
これらのメリットを理解し、自社の状況に合わせて業務提携と業務委託を適正に活用することで、事業の発展につながります。
3. 業務提携と業務委託のデメリット
業務提携と業務委託には、独自の弱みやマイナスな部分があります。下記では、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
3-1. 業務提携のデメリット
業務提携には、以下のようなデメリットがあります。
情報漏洩のリスクがある
業務提携では双方のリソースを共有します。他社のリソースやノウハウを享受できる場合はメリットですが、反対に提携先へ提供する場合には、自社のリソースやノウハウが外部に流出し、思わぬ損害を被る可能性があります。
協働関係として、事業目標の達成を目指す際には情報共有が欠かせないため、情報の漏洩や悪用が発生しないよう、秘密保持契約の締結やセキュリティ対策を行うことが大切です。
トラブルに発展する可能性がある
資本の移動が発生しない業務提携では、契約書の内容に法的な不備が無いかを調べる「リーガルチェック」が行われないケースも見られます。したがって、いざ提携を始めると、提携企業との間で利益の分配や経費負担についてトラブルが発生することがあります。
リーガルチェックを行っていない場合には、契約書に不備があることから双方間のトラブル解消が難しくなり、訴訟に発展する可能性もゼロではありません。できる限り、業務提携契約を結ぶ前に専門家へ依頼し、調査を行ってもらうと良いでしょう。
提携関係解消のリスクがある
業務提携は資本提携やM&Aのように、資本を介した強力な結びつきは無いことが通常です。自社として比較的容易に関係性を解消できることは、提携会社にとっても提携関係を解消しやすいということです。
提携相手から見て思うような成果が得られていない場合や、業務提携担当者の異動や離職があった場合には、提携関係が希薄化し、自然消滅してしまう可能性も生じます。
相乗効果が得られない可能性がある
業務提携では、従来期待していた相乗効果が得られない恐れがあります。主な理由は2つ挙げられます。一つ目は、コミュニケーション不足によって事業提携の目標が曖昧になってしまい、方向性がズレてしまうことです。
2つ目は、パートナー選定が適切ではないことです。事前に多くの手間とコストをかけて提携準備を行っても、結果的に思うような効果が出ない場合は、かけた手間やコストが無駄になってしまいます。
提携企業の経営状況や信頼性、会社文化や事業内容の親和性を考慮したうえで、慎重に提携相手を選定し、提携後には密接なコミュニケーションをとることが不可欠です。
3-2. 業務委託のデメリット
業務委託にも、以下のようなデメリットがあります。
社内にノウハウを残しづらい
業務委託では、プロに委ねることで即効性がある反面、社内にノウハウが蓄積されにくいデメリットがあります。専門性が高い分野であればあるほど、業務委託の比重が高くなりがちです。結果的に、社内人材の育成が進みにくくなってしまいます。
業務委託を利用する際は、業務の完遂だけを目的とせず、受託者とのミーティングや情報共有の場を設けるなど、社内に情報を残すための仕組みづくりを整えることも大切です。
委託内容によってはコストが大きくなる
業務委託は、社内の人件費を抑えられるメリットがある一方、委託する業務内容や期間によってはコストがかさんでしまう可能性もあります。
なかでも、IT分野や会計士、弁護士といった専門性の高い領域になるほど、費用は高くなります。自社にとって必要な分野を絞り、委託期間の見通しを立てたうえで依頼を行うことがポイントです。
デメリットを理解し、自社の状況に合わせて業務提携や業務委託を適切に活用することで、事業の発展につながります。
4. 業務提携と業務委託はどちらを選択すべき?
業務提携と業務委託は、相手方との関係性や目的が大きく異なるため、ケースによって使い分けることが重要です。
例えば、自社のリソースやノウハウだけでは、既存事業の拡大や新規事業の立ち上げといった目標を達成することが難しい企業同士ならば、対等な立場で、お互いのリソースやノウハウを活用する「業務提携」の形態を取ったほうが良いでしょう。
一方、単に一部の業務について自社にリソースとノウハウが無く、すぐにその業務を遂行したい場合には、委託者と受託者の上下関係が存在する「業務委託」の形態を取ったほうが、お互いに割り切って目的を遂行できます。
5. まとめ
業務提携と業務委託は、言葉は似ていますが、意味するところは大きく異なります。それぞれの特性と目的に合わせ、ケースごとに使い分けることが必要です。
業務提携との対比では、資本取引を含む「資本業務提携」という選択肢も存在します。その場合は、M&A仲介会社やFA会社などの専門家に相談すると良いでしょう。
M&Aキャピタルパートナーズは、東証プライムに上場しており、企業の成長戦略の一環としてM&Aを活用する企業を支援しています。業務提携や業務委託に関して、疑問のある方や検討中の経営者様は、お気軽にお問い合わせください。