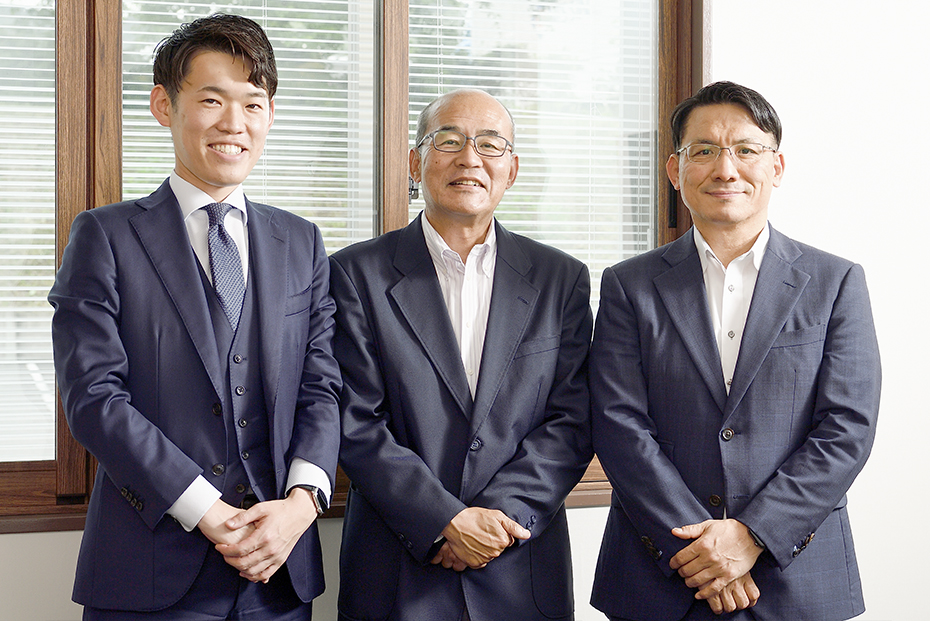更新日
スコーチドアースディフェンスについて
日本の企業間におけるM&A(Mergers and Acquisitions、合併・買収)の動きは、近年、増加しています。M&Aは企業の成長戦略の一環として行われる一方、敵対的な買収として進められる場合も存在します。企業が敵対的な買収から身を守るための数々の手段の中で、特に強力かつ極端と認識されるのが「スコーチドアースディフェンス(Scorched-earth Defense)」です。今回は、日本におけるスコーチドアースディフェンスの定義、メリットとデメリット、具体的な事例について、詳しく説明します。
このページのポイント
~スコーチドアースディフェンスとは?~
スコーチドアースディフェンスは、企業が敵対的買収から身を守るため、意図的に自社の価値を減少させる買収防衛策です。資産の売却や負債増加などで買収者の魅力を削ります。本記事では、スコーチドアースディフェンスの定義、メリット・デメリット、実際の事例を解説し、その極端な手法が企業経営に与える影響について解説します。
関連タグ
- #M&A
- #M&A関連記事
- #M&A用語集
- #スコーチドアースディフェンスとは?
~その他 M&Aについて~
目次
1. スコーチドアースディフェンスの概要
1-1. スコーチドアースディフェンスとは?
スコーチドアースディフェンス、直訳すると「焦土作戦の防御」となり、焦土作戦は古くからの軍事上の戦術及び作戦を指します。戦闘において攻撃側に奪われる地域に所在する家屋、田畑、森林など利用価値のあるインフラを破壊、焼き尽くします。これにより、攻撃側は敵の領土内で食料や燃料の調達が不可能になり、戦闘どころではなくなります。この軍事上の戦術である焦土作戦は、M&Aにおける買収防衛策の一つとしても知られており、自社の資産や価値を故意に減少させる行為を指します。具体的には、クラウンジュエルと呼ばれる優良資産や収益性の高い資産や事業を売却したり、大量の負債の増加させるなど、買収の魅力を下げる、あるいは買収を不可能にするための行動をとることを指します。この方法は、企業が「焦げつくまで戦う」という姿勢を示しており、極端な防衛策と一般的に認識されています。
2. M&Aにおけるスコーチドアースディフェンス
敵対的なM&Aは、時として企業の経営陣と株主間の利益が対立する場面で見られます。経営陣が自らのポジションを保つため、もしくは企業文化や方針を守るために、買収を回避したいと考えることがあります。その際に、スコーチドアースディフェンスを適用することで、買収を難しくすることができます。特に日本では、伝統的に企業間の関係性や経営の継続性が重視されてきた文化的背景から、このような極端な防御策が取られる可能性もあると考えられています。
2-1. スコーチドアースディフェンスのメリットとデメリット
スコーチドアースディフェンスのメリット
- 買収企業の意欲を減退させることができる
- 被買収企業が単独の判断で行うことができるため、第三者の支援が必要ない
スコーチドアースディフェンスのデメリット
- 事業継続に必要な優良な資産や技術、ノウハウ等を売却することで企業の価値が毀損してしまうリスクがある
- 自社の事業用資産を売却する際には株主総会で株主の同意が必要となる
- 企業価値の毀損について、取締役が善管注意義務に違反しているとみなされる可能性がある
3. スコーチドアースディフェンスの事例
スコーチドアースディフェンスを実施すると企業価値の毀損や株主からの反発といった実害が出るので、実際に実行に移されたケースは多くはありません。
スコーチドアースディフェンスが注目を集める契機となったのは、2005年のライブドア社によるニッポン放送への敵対的買収です。この事件の発端はニッポン放送という小さな親会社がフジテレビという大きな子会社を保有しているという不安定な資本関係でした。ここで、ライブドア社はニッポン放送を買収することで、その子会社であるフジテレビの支配を狙いました。
ライブドア社による敵対的買収に対して、ニッポン放送はフジテレビに対する新株予約権の発行やニッポン放送子会社のポニーキャニオンの売却など様々な対抗策を講じましたが、ライブドア社が諦める気配を見せませんでした。
そこで、ニッポン放送はフジテレビの株式を売却するという、スコーチドアースディフェンスを検討しました。しかし、その後、ソフトバンク・インベストメントがホワイトナイトとなって、フジテレビ株の貸借をすることを決定したため、スコーチドアースディフェンスは回避されました。
4. まとめ
スコーチドアースディフェンスは、その名の通り極端な防御策として位置づけられています。敵対的買収の阻止は企業の継続的な経営や文化を保つ上で重要な要素となる場合もありますが、その手段によって企業価値を自ら損なう行動は、長期的な視点での経営の健全性や株主の利益をどう捉えるかという観点からも慎重な判断が求められると考えられます。
M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。
着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。
以下より、お気軽にお問い合わせください。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
よくある質問
- スコーチドアースディフェンスとは何ですか?
- スコーチドアースディフェンスは、企業が敵対的買収者から身を守るために、資産を故意に減少させたり、負債を増加させて買収者の意欲を減退させる防衛策です。
- スコーチドアースディフェンスのメリットは?
- スコーチドアースディフェンスのメリットは、敵対的買収者の意欲を減退させ、買収を防ぐ可能性がある点です。
- スコーチドアースディフェンスのデメリットは?
- 企業の資産や価値を減少させることで、事業継続に必要な重要な資産を失うリスクや、取締役の善管注意義務違反と見なされるリスクがあります。