更新日
所有する資産をもとに利益を得るには、キャピタルゲインとインカムゲインという性質の異なる2種類の手法がありますが、会社の経営戦略を検討する際には重要なポイントとなります。本記事ではキャピタルゲインに注目して、インカムゲインとの違いやキャピタルゲインのメリットとデメリット、さらにはM&Aによるキャピタルゲインに対する税金計算などについて分かりやすく解説します。
本記事でキャピタルゲインに関する理解を深めるのにお役立てください。
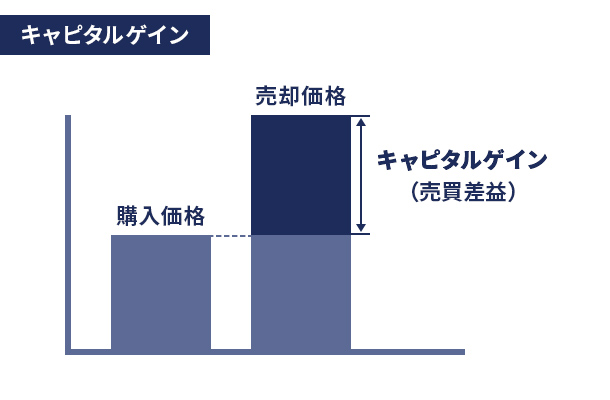
このページのポイント
~キャピタルゲインとは?~
キャピタルゲインとは、資産を購入した価格とそれを後に売却した価格との差額の利益のことを指す。M&Aなどで企業や個人が保有している株式が購入価格よりも高い価格で買収された場合、その差額がキャピタルゲインとして認識される。インカムゲインは資産の保有によって継続的に得られる利益を指し、それぞれ得た利益に対する課税の仕組みが異なる。
関連タグ
- #M&A
- #M&A関連記事
- #M&A用語集
- #キャピタルゲインとは?
~その他 M&Aについて~
目次
1. キャピタルゲインとは
まずはキャピタルゲインから詳しく説明していきます。
1-1. キャピタルゲインとは
キャピタルゲイン(Capital Gain)とは、資産を購入した価格とそれを後に売却した価格との差額の利益のことを指します。M&Aの際には、企業や個人が保有している株式が、他の企業によって高い価格で買収されることがよくあります。このとき、株式の売却価格が購入価格を上回る場合、その差額が利益としてキャピタルゲインとして認識されます。逆に、株式の売却価格が購入価格を下回る場合、その差額が損失としてキャピタルロスという損失が発生します。
1-2. インカムゲインとは
所有する資産をもとに利益を得る手法には、キャピタルゲインとは別にインカムゲインというものがあります。インカムゲイン(Income Gain)とは、資産の保有によって得られる継続的な利益のことをいいます。
具体的には、株式の配当金や不動産の賃貸収入、銀行預金の受取利息などがインカムゲインの代表例として挙げられます。
1-3. キャピタルゲインとインカムゲインの違い
キャピタルゲインとインカムゲインの主な相違点を整理すると、以下の表のとおりとなります。
| キャピタルゲイン | インカムゲイン | |
|---|---|---|
| 主な資産 | 株式、FX、不動産、暗号資産等 | 株式、不動産銀行預金等 |
| 発生タイミング | 資産を売却した時に発生する | 継続的に発生する |
| 利益の大きさ | 短期的に大きな利益が得られる可能性がある | 短期的に大きな利益の獲得は見込めない |
| リスク | ハイリスクの傾向がある | ローリスクの傾向がある |
2. キャピタルゲインの具体的な事例
キャピタルゲインは、投資手法によっていくつかの種類に分類されますが、具体的な事例として、株式投資、FX投資、不動産投資、暗号資産投資があります。それぞれのキャピタルゲインについて、解説します。
2-1. 株式投資から得られるキャピタルゲイン
株式投資は、株式市場において企業の成長や収益の向上等によって株価が上昇することを期待し株式を購入することです。株式投資の利益は、株価が上昇した後に売却して得る売買差益であるキャピタルゲインと企業が株主に支払う配当金であるインカムゲインがあります。キャピタルゲインは、株価の上昇によってリターンを得ることになるため、大きなリターンを得られる可能性もありますが、株価が下落してキャピタルロスとなるリスクもあります。
2-2. FX投資から得られるキャピタルゲイン
FX(Foreign Exchange)投資は、世界最大の金融市場の1つで、外国為替市場で異なる通貨間の相対的な価値の上昇や下落を予測し利益を得ることです。例えば、米ドル対日本円の場合では、将来の米ドル高を予測し日本円で購入した後、実際に米ドルの価格が上昇すれば売却し売買差益であるキャピタルゲインを得ることができます。しかし、FX市場は短期的な価格変動が頻繁に起こるため、株式投資と同様にキャピタルロスとなるリスクがあります。
2-3. 不動産投資から得られるキャピタルゲイン
不動産投資とは、不動産の所有または売買によって利益を得る投資手法です。例えば、不動産の価格が上昇した後に売却して得る売買差益であるキャピタルゲインや住居用の賃貸物件や商業用の不動産を購入し賃貸に出すことで得る賃料収入であるインカムゲインなどがあります。不動産投資には資金調達、物件調査、関係法令の遵守、不動産の適正管理などが求められ、一般的には長期的な視点で行う投資といえます。
2-4. 暗号資産投資から得られるキャピタルゲイン
暗号資産投資とは、ビットコインなどの暗号資産を売買することで利益を得る投資手法をいいます。例えば、1BTC(ビットコイン)を100万円で購入し300万円に値上した後に売却すると、手数料や関連費用を考慮しなければ200万円のキャピタルゲインが得られます。ただし、暗号資産は値動きが激しいためハイリスク・ハイリターンの投資と一般的に認識されています。
2-5. キャピタルゲインの一種である創業者利益
創業者利益とは、会社の創業者が保有する会社の株式を第三者に譲渡して得た利益のことで、広義ではキャピタルゲインの一種といえますが、厳密には、すでに存在している会社を売買して得るキャピタルゲインとは異なります。具体例としては、創業者自身が出資した株式資本によって会社を立ち上げてから、経営努力により企業価値を高めるので、売却額から株式資本を差し引いた額が創業者利益となります。
3. M&Aとキャピタルゲインの関係
キャピタルゲインは、M&Aにおいては、株式譲渡や事業譲渡によって発生しますが、株主が得る場合と会社が得る場合があります。ここでは、M&Aにおけるキャピタルゲインについて、説明します。
3-1. 株式譲渡から得られるキャピタルゲイン
M&Aにおいて株式譲渡は、株主が保有する会社の株式を第三者に譲渡することで、支配権を譲受企業に承継する手法で事業譲渡とともによく選択されるスキームです。創業者が株式譲渡を行う場合には創業者利益、株主が買収した会社の株式を譲渡する場合にはキャピタルゲインとなり、創業した会社や買収した会社の企業価値を高めた上で株式を譲渡すると大きなキャピタルゲインが得られます。また、株式を譲渡する場合、個人と会社である法人では税率や課税方式が異なるので注意が必要です。
3-2. 事業譲渡から得られるキャピタルゲイン
M&Aにおいて事業譲渡は、自社の事業の全部又は一部を第三者に譲渡することで、株式譲渡などと比べて譲受企業が事業に関する資産や負債を選択できるメリットがありますが、手続きが複雑で時間がかかるなどのデメリットもあります。事業譲渡によるキャピタルゲインは、譲渡価格から資産及び負債の合計を差し引いた金額となり、税金は株主ではなく事業を譲渡した会社に課せられます。
3-3. 企業買収から得られるキャピタルゲイン
買収した企業が、買収後に成長しその企業の株価や企業価値が向上した場合にも、潜在的なキャピタルゲインが生じます。しかし、キャピタルゲインは資産などの売却によって得られる売買差益なので、株価や企業価値の向上はキャピタルゲインをもたらす要素の一つとなり得ますが、それ自体がキャピタルゲインではなく、実際に対象企業を第三者に売却した段階でキャピタルゲインは生じます。
4. キャピタルゲインのメリットとデメリット
次にキャピタルゲインのメリットとデメリットについて、整理したいと思います。
4-1. キャピタルゲインのメリット
キャピタルゲインのメリットは主に以下の通りです。
- 短期間で利益を獲得できる可能性がある
- 多額の利益を獲得できる可能性がある
それぞれについて、詳しく説明していきます。
・短期間で利益を獲得できる可能性がある
キャピタルゲインは資産の売却で得た売買差益のことですから、株式を購入した後値上がりを待って売却する際に、株価の値動きが速いほど短期間でキャピタルゲインを獲得することが可能になります。また、M&Aでベンチャー企業などを買収した場合でも、その企業の事業活動を通じて利益を獲得するのに比べて、技術開発などで企業価値を高め売却すれば業績が黒字化していなくても短期間でキャピタルゲインの獲得が可能になります。
・多額の利益を獲得できる可能性がある
キャピタルゲインはインカムゲインと比べて、資産の値動きによって大きな売買差益を獲得できる可能性があります。かつてのビットコインのように数年で数万倍以上になるケースは稀ですが、近年でもAIなどのように成長期待が大きい分野の株式は大きな値上がりを見せており、銘柄と投資時期によっては膨大なキャピタルゲインが得られる可能性があります。
4-2. キャピタルゲインのデメリット
キャピタルゲインのデメリットは主に以下の通りです。
- 多額の損失を被るリスクがある
- 資産を失い、継続的な利益取得ができなくなるリスクがある
それぞれについて、詳しく説明していきます。
・多額の損失を被るリスクがある
キャピタルゲインは、資産の値上がりによって大きなリターンを獲得できる一方、資産が大きく値下がりした場合には多額の損失を被るリスクがあります。M&Aの場合でも、買収した会社が業績不振に陥り、最悪倒産する可能性あります。このように、キャピタルゲインには大きな利益が得られる可能性とともに、大きな損失を被るリスクがある点がデメリットの一つといえます。
・資産を失い、継続的な利益取得ができなくなる
キャピタルゲインには、資産を売却して売買差益を獲得する引換えに保有していた資産を失うため、インカムゲインのように資産を活用して継続的な利益を得ることができなくなるデメリットがあります。
5. キャピタルゲインの計算例
キャピタルゲインは、保有資産の売買差益と説明してきましたが、厳密には次の計算式で算出します。
キャピタルゲイン = 売買差益 - 税金
=【売却価格 −(購入価格 + 手数料等)】− 税金
=【売却価格 −(購入価格 + 手数料等)】−(売買差益 × 税率)
資産の売却には、手数料等や売買差益にかかる税金も発生するため、売買差益からそれらを差引いた金額がキャピタルゲインとなります。なお、資産の取得に要した経費などは購入価格(原価)に算入されます。また、キャピタルロスとなった場合には上記計算式の税金は0となります。
6. M&Aによるキャピタルゲインに対する税金計算
M&Aによりキャピタルゲインに対する税金は、主に不動産、株式、不動産以外の課税資産に分類することができ、それぞれに対する課税方式や税率について、以下で説明していきます。
6-1. 投資に対する税金
投資資産の売却によって得た譲渡所得に対する税金の扱いは、個人と法人では異なります。個人の場合、株式・FX・不動産の譲渡所得は給与などの所得とは分けて課税(申告分離課税)され、長期保有の不動産に対しては次のような軽減税率があります。
| 区分 | 保有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 所得税15%+復興特別所得税0.315%(※)+住民税5% 合計 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 所得税30%+復興特別所得税0.63%(※)+住民税9% 合計 39.630% |
2013年〜2037年は、所得税率に2.1%を乗じた復興特別所得税が加算されます。
また、暗号資産(仮想通貨)の取引で獲得した利益は雑所得に分類され、給与所得などと合計した金額に課税(総合課税)されるので、現行制度では金額が大きければ累進課税によって最大約55%(住民税を含む)の税率になることに注意が必要です。
法人の場合は、資産の種類に関わらず譲渡所得は本業の収益と合計した金額に対して課税(総合課税)され、法人の種類、資本金額、年間所得金額、登記している地方自治体などで各種税金の税率が変化します。また、不動産の譲渡所得の場合には購入価格から減価償却費を差し引いた金額(簿価)を用いるところが個人とは大きく異なります。
6-2. 株式譲渡に対する税金
M&Aにおける株式譲渡に対する税金も前述したように、創業者などの個人と法人では扱いが異なります。また、土地・有価証券・債権等は非課税資産に該当するので株式譲渡に対して消費税は課せられません。
6-3. 事業譲渡に対する税金
M&Aにおける事業譲渡の場合、株主ではなく事業を譲渡した法人に対して税金が課せられます。また、株式譲渡には消費税は課せられませんが、事業譲渡の場合には法人税・事業税・地方法人税・法人住民税以外に、譲渡対象に含まれる課税資産(無形固定資産、土地を除く有形固定資産、棚卸資産、営業権等)に対して消費税が課せられるので、M&Aのスキームによって税金の負担額が変わる点にも注意が必要です。また、課税資産の譲渡所得の計算には不動産と同様に減価償却費を差し引いた簿価が用いられます。
なお、特にM&Aでは、この税金計算の金額的影響が大きいため、税務の専門家と相談しながら進めることが強く推奨されます。
7. まとめ
今回は、キャピタルゲインについて解説しました。
M&Aは企業の成長や戦略の一部として行われ、その過程でキャピタルゲインが発生することが実務上、多く見られます。そのため、M&Aを検討する際は、キャピタルゲインに関する税務の側面も考慮に入れる必要があります。このような背景を考慮し、適切な知識と理解を持って資産を管理することが重要です。
本記事を通じて、キャピタルゲインの理解が深まり、それを自社の経営やM&Aの現場で活用する一助となれば幸いです。M&Aに関するお悩みはM&Aの専門家へ相談する選択肢もあります。東証プライム上場の信頼と、豊富な実績を有するM&Aキャピタルパートナーズに、どうぞご相談ください。
















