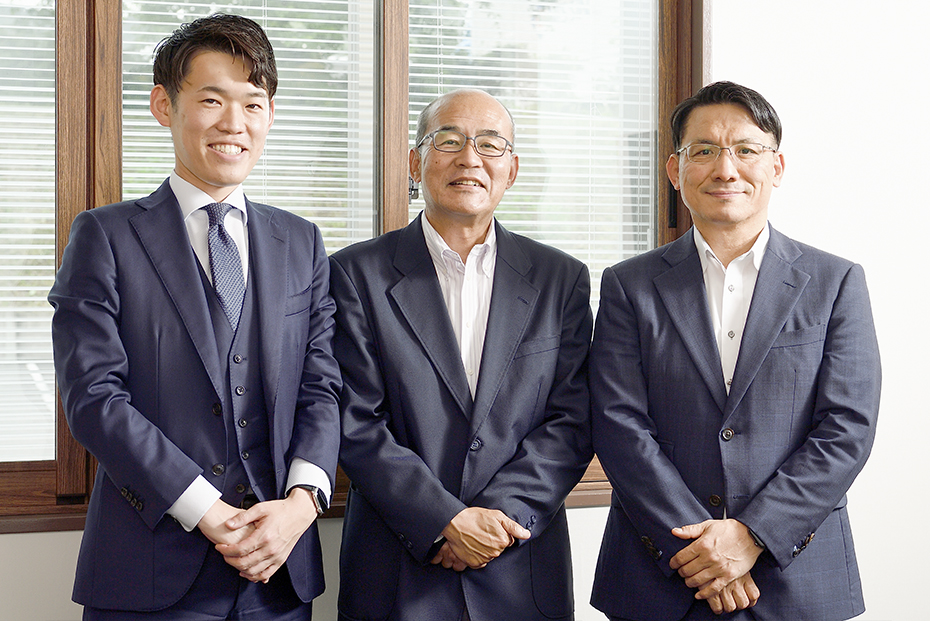更新日
M&Aの取引を行う際、法律の確認は欠かせません。
法律に抵触しているにも関わらず無視をしてしまうと、M&Aの取引が無効になってしまうだけではなく損害賠償の請求が発生する可能性もあります。
そうならないためにも、取引に関係している法律は必ずチェックしておく必要があります。
この記事では、M&Aに関する法務についてや法律上の問題点を事例付きで解説しています。
このページのポイント
~M&Aの法務とは?~
M&Aの法務とは、企業の合併や買収に関連する法的手続きを指します。主要な法律には会社法、金融商品取引法、独占禁止法などがあり、これらの法律に基づいて取引の適法性を確認します。法務デューデリジェンスは、M&Aの対象企業の法的リスクを評価するための重要な調査です。
関連タグ
- #M&A
- #M&A関連記事
- #M&Aの流れ
- #M&Aの法務とは?
~その他 M&Aについて~
M&Aではさまざまな法律を理解しないと話がまとまらない
M&Aを実施する際には、会社法のみならず、金融商品取引法や独禁法等、多くの法律に抵触しないか用心深く確認していく必要があります。
なぜならM&Aの一連の取引では必ず利害関係者が存在し、対立するからです。
M&Aを進める上で、毎回、必ず全てではありませんが、M&Aの法務に関する実務書では、以下の法律に関して記載があり、M&Aの一連の流れをおさえたうえで随所に法務や税務の知識を身につけておかないと、対立する関係者同士の利害を調整し、M&Aをまとめ上げることができません。
- 国税通則法
- 国税徴収法
- 国税徴収法施行令
- 国税徴収法基本通達
- 所得税法
- 所得税法施行令
- 所得税基本通達
- 法人税法
- 法人税法施行令
- 法人税法施行規則
- 法人税基本通達
- 連結納税基本通達
- 相続税法
- 登録免許税法
- 消費税法
- 消費税法施行令
- 消費税法施行規則
- 消費税法基本通達
- 地方税法
- 地方税法施行令
- 印紙税法
- 印紙税法基本通達
- 租税特別措置法
- 租税特別措置法施行令
- 租税特別措置法施行規則
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(租税条約実施特例法)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(租税条約実施特例省令)
- 会社法
- 会社法施行規則
- 会社計算規則
- 金融商品取引法
- 金融商品取引法施行令
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
- 外国為替及び外国貿易法
- 外国為替令
- 対内直接投資等に関する政令
- 対内直接投資等に関する命令
- 外国為替の取引等の報告に関する省令
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)
- 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(旧産活法)
- 産業競争力強化法
- 有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)
- など
このような法律上の手続きに則らずに実施されたM&Aは、会社とそれを取り巻く多数の利害関係者に影響を与え、最悪の場合にはディールそのものが無効となることや、取消されるおそれがあります。
例えば、M&Aの対象会社が特定の許認可事業を行っている場合には、その許認可がM&A後も有効に活用できるか検討する必要があります。
【事例】において、「建設業」が許認可事業建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する「経営管理責任者」をはじめとする4つの「許可要件」を備えていて、同法8条に規定する「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者」をはじめとする「欠格要件」に該当しないことが必要になります。
また、仮に当該許認可を承継することができたとしても、一定期間事業を停止しなければならないとすれば、対象会社の事業価値を損なうことは明白です。このように、M&Aには通常の商取引では注意を払わない法律にも留意する必要があります。
これらの法律を検討した結果、当初予定していたスキームでは法的に問題があると判明した場合、別のスキームを用いることなどを検討しなければなりません。
M&Aの障害となる法律上の問題点
M&Aでいう「株式を買う」ことは、「会社を丸ごと買う」ことです。株式譲渡の実行において、売主となる株主、売買の対象物である株式、そして株式譲渡により譲受ける会社について、どのようなこと問題点があるか【事例】をもとに検討しましょう。
事例
Aさんは30歳で独立し、会社員時代に培った経験と人脈をもとにA建設株式会社を設立、建設業を始めました。
当時株式会社の設立には、7名が集まりそれぞれ株式を引受けることが必要ということで、Aさんは親戚や友人に名前を借り、実際にはAさんの父親とAさんが株式の引受を行いました。A建設株式会社は、業容を拡大し、従業員が15人となりました。
Aさんの人柄に惹かれて集まってきた従業員達でしたので、A建設株式会社ではきちんとした勤怠管理は行われておらず、頑張った従業員には、Aさんの判断でボーナス支給時に残業代を上乗せして支給していました。そして、退職金支給規定はないものの、勤続10年以上の従業員が退職する際には、退職金を出すことが慣習となっていました。
昨年Aさんの父親が死去し、自身ももうすぐ60歳になるということがきっかけで、株式譲渡によるM&Aを選択肢の1つとして検討することになりました。
事例での注意点の例として、以下の項目が挙げられます。
- 名義株がそのままになっていないか
- 父親名義の株式の相続人は誰か
- 未払残業代が発生していないか
- 退職金支払債務がないか
- 建設業の許可は、M&A後も維持できるか
- Aさんが経営から離れても事業を継続できるか
など
M&Aを実施する際は、多くの法的問題点が存在します。
しかし、最終契約における取引対象は、ヒト・モノ・カネの集合体という会社であり、単なるモノの売買と比べて、取引対象を把握しにくいという問題点が存在します。また、M&Aの対価にのれんが上乗せされ、時価純資産よりも高額であることが一般的です。
にもかかわらず、M&A後に予想通りに事業が進捗しないことや、予想外の損失計上などの事態が生じることも頻繁にあります。つまり、M&Aの契約は将来的にトラブルとなるおそれが高い契約と言えます。
トラブルになった際に重要な役割を果たすのは、最終契約書の記載内容となります。そのため、将来的にトラブルになる可能性が少しでも想定される場合には、弁護士をはじめとする専門家の支援を受けて法務デューデリジェンスを実施し、可能な限リのリスクヘッジを行った契約内容にまとめる必要があります。
- 関連記事
- 株式譲渡とは?~事業承継の手続きと中小企業でよくある論点~
- M&Aと契約書~アドバイザリー契約書などの必要書類や記載項目~
- デューデリジェンス(dd)とは?~M&Aにおける意味や費用、種類を解説~
よくある質問
- M&Aにおける法務デューデリジェンスとは何ですか?
- 法務デューデリジェンスとは、M&Aの対象企業の法的側面を評価し、潜在的なリスクや問題点を特定するための調査です。これにより、取引後のトラブルを未然に防ぐことができます。
- M&Aで確認すべき主要な法律は何ですか?
- M&Aでは、会社法、金融商品取引法、独占禁止法など多くの法律を確認する必要があります。これらの法律に抵触しないようにすることで、取引の有効性を確保します。
- M&Aの法務上の問題点にはどのようなものがありますか?
- M&Aの法務上の問題点には、株式の帰属確認、労務管理、不動産の適法性、知的財産権の確認などがあります。これらの問題点を事前に把握し、適切に対処することが重要です。