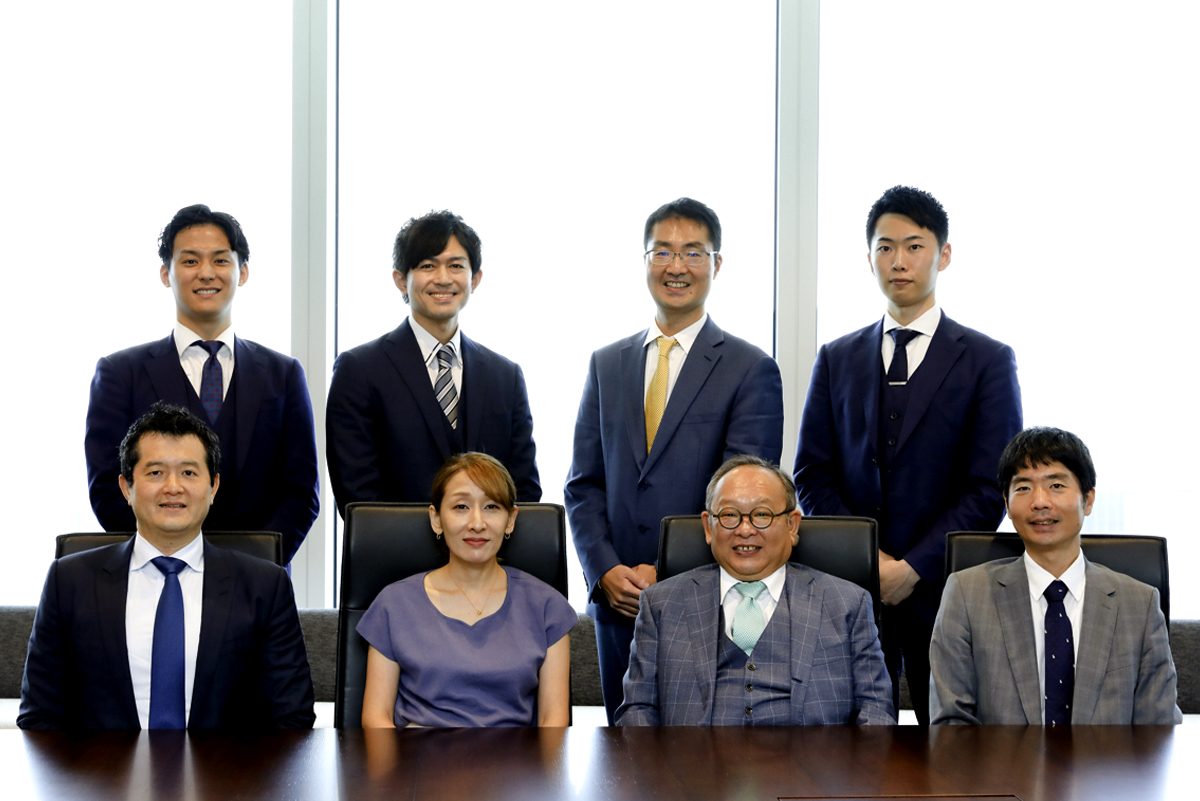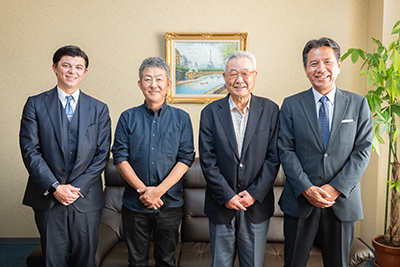更新日
日本の企業間におけるM&A(Mergers and Acquisitions、合併・買収)や事業承継の動きは、近年増加しています。特に事業承継において、経営権の分散を防ぐことは経営者にとって重要な課題であり、株式の売渡請求は経営権の集中につながるため、この課題に対して有効な解決策となり得ます。
今回は、株式の売渡請求の概要、前提条件、売渡請求の具体的な流れおよび留意点について、詳しく説明します。
このページのポイント
~売渡請求とは?~
株式における売渡請求とは、少数株主に対して、当該株式を売り渡すことを請求できる制度。少数株主の同意を得ずとも強制的に取得できる点が、株式の売渡請求の特徴とされている。株式の売渡請求の使用場面としては、相続や完全子会社化、少数株主の排除などの場面で活用され、特に相続の手段として、有効性が高いと一般的に認識されている。
目次
1. 売渡請求とは?
株式の売渡請求とは、少数株主に対して、当該株式を売り渡すことを請求できる制度です。少数株主の同意を得ずとも強制的に取得できる点が、株式の売渡請求の特徴とされています。
株式の売渡請求の使用場面としては、相続や完全子会社化、少数株主の排除などの場面で活用されます。特に相続の手段として、株式の売渡請求は有効性が高いと一般的に認識されていることから、今回は相続人等に対する売渡請求について、説明していきます。
相続人等に対する株式の売渡請求とは、株主が死亡した際に、その相続人などに対して株式を会社に売り渡すよう請求することができる手続きです。
相続人等は会社から売渡請求をされた場合、金額の交渉をすることはできるものの、売り渡し自体を拒否することはできません。
株主が亡くなって相続が発生したとしても、株式を承継した相続人などに対して会社が売り渡しを請求することで、会社や他の株主の予期せぬ人が会社の株主であり続ける事態を避けることが可能となります。
2. 相続人等に対する売渡請求をするための前提条件
相続人等に対する株式の売渡請求をするためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
2-1. 譲渡制限株式であること
株式に譲渡制限が付いていない場合は、相続人等に対する売渡請求の対象にできません(会社法174条)。
2-2. 定款に売渡請求ができる旨の規定があること
売渡請求は定款の定めがある場合にのみ行うことができるものであり、定款に定めがない場合は行うことができません(会社法174条)。
2-3. 会社に株式を買い取るだけの資金があること
相続人等に対する株式の売渡請求は、自己株式の取得にあたります。
そのため、財源規制の対象となり、買い取りの対価として一定の分配可能額を超える金銭等を交付することはできません(会社461条1項5号)。
財源規制に違反して欠損が生じた場合、株主総会議案を提案した取締役などが連帯して欠損填補をする責任を負う可能性があります。
3. 相続人等に対する売渡請求の具体的な流れ
次に相続人等に対する売渡請求の具体的な流れの事例を紹介します。
3-1. 会社が株主の死亡(相続発生)を知る
相続人等に対する売渡請求は、株主が存命中には実施できません。
その株主が亡くなり、会社が相続の発生を知った時点から検討を開始することとなります。
3-2. 株主総会で売渡しの請求決定をする
相続人等に対する売渡請求をするには、株主総会の特別決議で次の事項を定めなければなりません(会社法175条1項、309条2項3号)。
3-3. 売渡しの請求をする
株主総会において相続人等に対する売渡請求をする旨などが決まったら、株式を承継した相続人等に対して売り渡しの請求をします(会社法176条)。
3-4. 売買価格の協議をする
相続人等に対する売渡請求は、あくまでも買取請求であり、株式を無償で会社に交付することを求めるものではありません。
相続人等から会社が株式を取得するには、正当な対価を支払うことが必要です。
そのため、株式の売買価格は、まず会社と請求対象である相続人等の協議による決定を目指すことになります(会社177条1項)。
3-5. 協議がまとまらない場合は売買価格決定の申立てをする
売買価格の協議がまとまらず、相続人等に対する売渡請求から20日が経過してしまうと、売渡請求の効果が失われてしまいます(会社法177条5項)。
売渡請求の効果を維持するためには、会社または請求対象である相続人等のいずれかがこの期間内(売渡請求から20日以内)に、裁判所に対して売買価格決定の申立てをする必要があります(会社法177条2項)。
3-6. 株主名簿の記載をする
株式の売買価格が決まり会社が株式を買い取ったら、会社はその事項を株主名簿に記載又は記録する必要があります(会社法132条1項2号)。
4. 相続人等に対する売渡請求の留意点
相続人等に対する売渡請求をする際や定款に定める時の主な留意点は、以下のとおりです。
4-1. 主要株主の相続発生時に会社乗っ取りに利用されるリスクがある
例えば、ある会社の代表取締役が90%の株式を有するAと、7%の株式を持つB、3%の株式を持つCがいたとします。
この場合、会社の定款を作成するにあたって、相続人等に対する売渡請求ができる旨を定める際は、少数株主であるBやCの死亡への備えを念頭に置くことが多いです。
しかし、相続人等に対する売渡請求は少数株主が死亡した場合のみに発動されるものではなく、主要株主であるAが死亡したときに発動される可能性もあります。
つまり、Aが亡くなり、取締役であった長男のZがAの有していた株式を相続したところ、Bが株主総会で相続人等に対する売渡請求を決議し、Zが強制的に株式を買い取られてしまう可能性があることには留意が必要です。
4-2. 相続人等に対する売渡請求には期限がある
相続人等に対する売渡請求は、会社が相続の発生を知ってから1年以内に行わなければならないことには留意が必要です。
4-3. 遺産分割協議の結果が不明な場合は相続人全員に対して請求する
株主に相続が発生し、相続人のうち誰がその株式を取得したのか会社に対して速やかに申し出があった場合は、原則としてその株式を取得した相続人にピンポイントで売渡請求をすることが可能です。
しかし、相続人の間ですぐに遺産分割協議がまとまるとは限りません。
そのため、会社としては株主に相続が発生した時点で、法定相続人全員に対して売渡請求を行っておくことも考えられます。
5. まとめ
今回は、株式の売渡請求の概要、前提条件、売渡請求の具体的な流れおよび留意点について、説明しました。
経営者であれば、事前に売渡請求について理解し、実施する場合には、会計、税務および法律の専門家に相談・依頼して進めることが望ましいです。