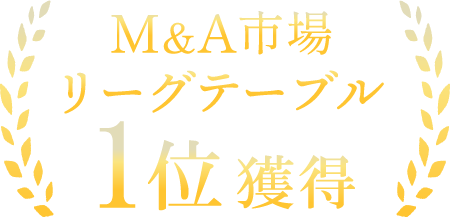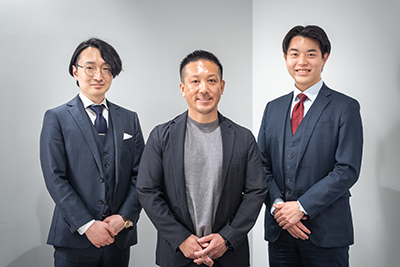基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aキャピタルパートナーズとは
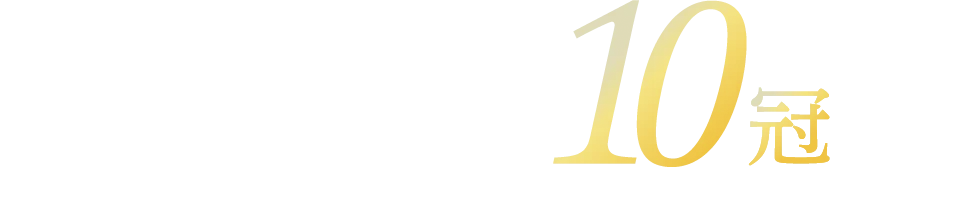
- リーグテーブル国内案件数
- 成約案件の譲渡株価総額
- 譲渡企業の売上高総額
- 社名認知度
- CM認知度
- 支払手数料率の低さ
- 成約案件の平均譲渡価格
- コンサルタントの士業資格保有者率
- コンサルタントの1人あたり売上高
- コンサルタントの1人あたり経常利益

リーグテーブル 国内M&A件数No.1※2
M&Aキャピタルパートナーズは、LSEG※1が発表したM&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー 2024年 フィナンシャル・アドバイザー」において、M&A 仲介専業企業で唯一ランクインし、3部門※2で1位を獲得いたしました。
※1 LSEG(ロンドン証券取引所グループ) ※2 1位獲得「国内案件 アドバイザー上位 5 位 案件数ベース」,1 位獲得「日本企業関連 完了案件(AF23a) 案件数ベース/不動産案件を除く」,1 位獲得「日本企業関連 公表案件 (AD19a) 案件数ベース/不動産案件を除く」豊富な支援実績
弊社では、創業以来、累計1,000組以上のお客さまをお手伝いしてまいりました。国内トップクラスの調剤薬局業界のM&A実績の他、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。
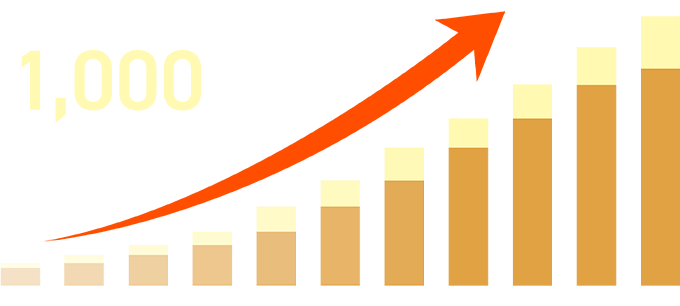

CM放映中
人気の報道番組で絶賛放映中!
テレビ朝日・テレビ東京系列
ライオン社長は、会社の将来を考える孤高のオーナー社長を表現しています。
社員を率いて重責に挑む社長の姿は、群れを率いて孤独に戦う百獣の王=ライオンと重なり、
事業承継に思い悩む様々なオーナー社長の姿を、CMで描いています。
明瞭かつ納得の手数料体系
「着手金無料、売り手・買い手同一の
株価レーマン方式」
売り手・買い手に対する
手数料(報酬)体系の違いによる影響
【弊社】
売り手・買い手同一の手数料
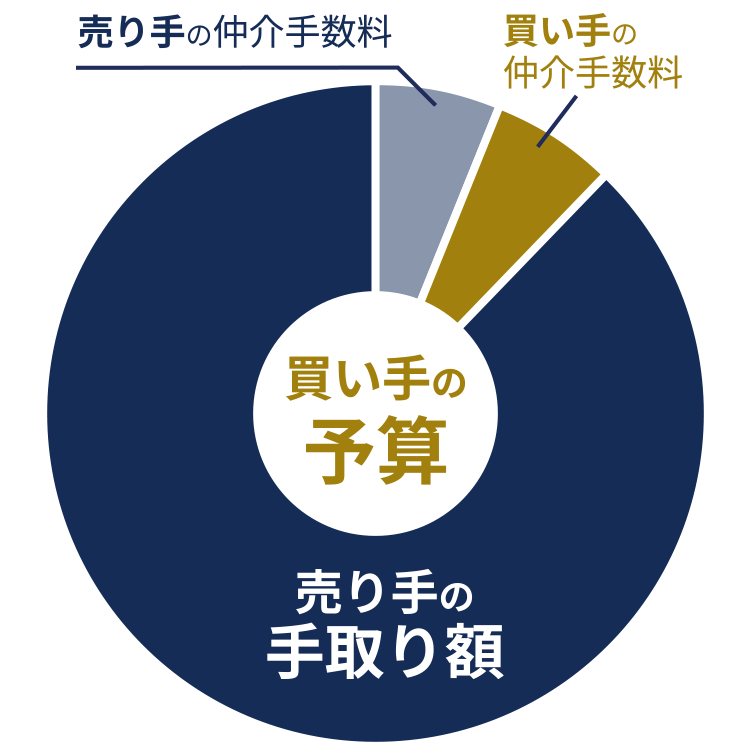
【他社】
買い手企業の手数料が
売り手企業よりも高い設定
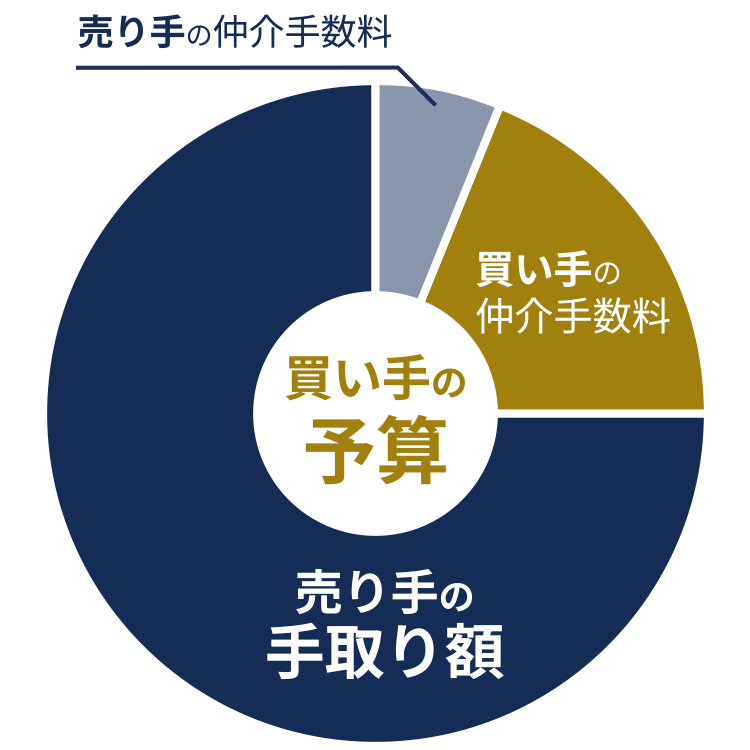
※出所:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」、「Ⅴ 仲介者・FAの手数料についての考え方の整理」より当社作成
M&A仲介会社の売り手・買い手のお客様への手数料体系が異なる場合、「売り手の手取額が減額」してしまうというリスクを孕んでいます。
弊社では、創業以来、着手金無料で売り手企業と買い手企業の双方から同一の手数料(報酬)体系を採用。
公正かつ相談しやすい手数料体系を続けています。
お客様に寄り添う
アドバイザリー
すべての中小企業オーナー経営者様を支えるM&Aのプロフェッショナルとして、私たちは的確な事業承継スキームのご提案、実行支援などのサービスをご提供いたします。

成約事例インタビュー
それぞれの選択
「様々な思いと葛藤の末に、最終的になぜM&Aを決断したのか?」
弊社でM&Aを実施し、事業の承継や発展を選択した経営者の方々のインタビューを、
「M&Aご成約事例インタビュー“それぞれの選択”」としてご紹介しております。
M&A案件情報
弊社にてご紹介できる譲渡(売却)案件の一部を掲載しております。
TOPICS
IR情報
M&A関連記事
- 後継者不足の実態
- 廃業
- 従業員への事業承継
- 中小企業のM&Aの現状
- 中小企業のM&A実績
- 医療法人の事業承継
- 事業承継時の消費税の取扱い
- ハッピーリタイア
- 親族外承継
- 倒産
- 経営不振
- 会社売却
- 後継者のいない会社を買う
- 非上場株式の譲渡
- 株式譲渡にかかる税金
- アーリーリタイア
- 事業承継計画書の記載項目
- 事業承継ガイドライン
- 事業承継とは
- 事業承継とM&Aの違い
- 事業承継における課題
- 事業承継対策の必要性
- 事業承継を実施するタイミング
- 事業承継で活用できる融資
- 事業承継M&A
- 事業承継問題
- 事業譲渡の相場
- 事業承継における生命保険
- 事業承継コンサルティング
- 事業承継の専門家
- 持株会社を活用した事業承継
- 事業承継と資産移転
- 事業承継の税務対策
- 事業承継計画
- 相続時精算課税制度
- 事業承継税制
- M&Aとは?
- 企業価値
- 事業譲渡
- 株式譲渡
- スモールM&A
- M&Aのメリット
- 経営戦略とM&A
- 売手側、買手側の課題
- M&Aとシナジー効果
- 会社売却の相場
- M&Aの情報漏洩対策
- M&A取引における金融商品取引法
- M&Aと節税
- 会社法
- M&A仲介
- 日本のM&Aの歴史
- 代表取締役と社長の違い
- 事業提携
- ファイナンシャルアドバイザー
- 決算(M&Aにおける決算の重要性)
- 損切り
- M&Aの手数料
- 敵対的買収
- 事業売却
- 休眠会社
- M&Aのスキーム(手法)
- 会社の解散
- COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)
- M&Aの条件交渉
- 買収防衛策
- M&Aの市場規模
- 投資と融資の違い
- M&Aにおける必要書類
- M&Aの注意点
- 吸収合併における存続会社
- 株式分割
- 事業譲渡における消費税
- 総合課税と分離課税の違い
- M&Aにおける独占禁止法
- 中小M&Aガイドライン
- M&Aの事例
- 第二会社方式
- 株価の決まり方
- ポストM&A
- テール条項
- 税理士が担う役割
- M&A実施時の実務
- M&Aにおける失敗
- 親族間株式譲渡の方法
- M&Aにおける借地権譲渡
- M&Aでの債権者保護手続き
- 事業譲渡の「のれん」
- 合併と買収の違い
- 会社分割における債権者保護手続き
- 吸収合併における仕訳・会計処理
- 会社分割の登記方法
- 吸収合併での契約承継
- スタートアップにおけるM&A
- 買収にかかる費用
- 廃業する会社を買う
- 休眠会社を買う
- 有限会社の株式譲渡
- TOBの規制
- TOBの不成立
- 無償の株式譲渡
- 株式譲渡と消費税
- 家族への株式譲渡
- M&Aの会計処理方法
- 株式譲渡の仕訳方法
- M&Aにおける意向表明書
- M&Aにおける退職金
- M&Aと株価
- 合併における債権者保護手続き
- 事業譲渡の株主総会
- 事業譲渡でかかる費用
- 個人事業主の事業譲渡
- 株式移転の仕訳
- 株式交換の適格要件
- TOBの手続きの流れ
- 株式交換の仕訳
- 業務提携と業務委託の違い
- 会社分割の税金
- 会社分割の不動産取得税
- 事業譲渡と株式譲渡の違い
- M&Aマッチングサイト
- M&Aのリスク
- M&Aにおける弁護士法人
- M&Aにおける税理士法人
- 株式価値
- M&Aにおける営業権
- M&Aにおける表明保証保険
- 範囲の経済
- M&Aにおけるディール
- M&Aにおけるアドバイザリー契約
- マッチングを成功させる方法
- M&A仲介とFAの違い
- M&Aアドバイザリー
- M&Aと税金
- M&Aの着手金
- M&Aのリテイナーフィー
- M&Aの中間報酬
- レーマン方式
- 企業価値評価(バリュエーション)
- M&Aの企業価値算定費用
- 収益拡大
- 中小企業の課題
- 会社買収
- M&Aの相談先
- 選択と集中
- 個人M&A
- 事業承継補助金
- 財務分析の指標
- M&A支援機関登録制度
- 会社買収後の影響・変化
- 赤字会社の売却
- M&Aの目的
- 親族内承継
- M&Aにおける資格
- M&Aのティーザー
- M&Aにおける銀行の役割
- 株式取得でかかる費用
- 個人で会社を買う方法
- 新設分割の手続き
- M&Aによる多角化戦略
- 経営資源集約化税制
- M&Aにおける監査法人
- SWOT分析
- アンゾフの成長マトリクス
- 商法と会社法の違い
- 買収
- 資本業務提携
- 業務提携
- 企業の合併
- 会社分割
- 第三者割当増資
- 株式移転
- 株式交換
- 提携仲介契約
- 経営統合
- 資本参加
- 株式持ち合い
- LBO(レバレッジド・バイアウト)
- MBO(マネジメント・バイアウト)
- 株式取得
- 吸収合併
- 新設合併
- 異業種参入
- 子会社売却
- EBO(エンプロイーバイアウト)
- バイアウト
- エスクロー
- 組織再編
- TOB(株式公開買付)
- MBI(マネジメント・バイ・イン)
- 株式交付
- マルチプル法
- イグジット(EXIT)
- カーブアウト
- クロスボーダーM&A
- 不動産M&A
- ベンチャー企業にとってのM&A
- 逆さ合併
- 分社型分割
- 三角合併
- M&Aによる投資
- M&Aを活用した起業
- 新規事業のM&A
- 適格株式移転
- M&Aの手法
- M&Aの手続きの流れ
- 株式譲渡の留意事項
- M&Aとノンネームシート
- M&Aと契約書
- M&Aの基本合意契約書
- 法務のポイント
- デューデリジェンス
- M&Aの表明保証
- M&Aのクロージング
- M&AにおけるPMI
- 最終契約
- マネジメントインタビュー
- 合弁会社
- M&Aの資金調達
- IM(企業概要書)
- ロングリスト
- ショートリスト
- M&Aのソーシング
- 資金調達
- トップ面談
- 株式譲渡の議事録
- 個人事業におけるM&A
- 株式上場
- マーケットアプローチ
- 医療法人の出資持分
- 会社の廃業手続き
- M&Aグロース
- EBITDAマルチプル
- VDR(バーチャルデータルーム)
- ディスクロージャー
- ビジネスデューデリジェンス
- ITデューデリジェンス
- ベンダーデューデリジェンス
- 人権デューデリジェンス
- 累進課税
- キャピタルゲイン
- 退職所得
- 新株予約権
- EPS(一株当たり純利益)
- IRR(内部収益率)
- EVA(経済的付加価値)
- 環境デューデリジェンス
- 超過収益力
- 期待収益率
- 法務デューデリジェンス
- オーガニックグロース
- インカムアプローチ
- コストアプローチ
- のれん
- EBITDA
- 正常収益
- 時価純資産法
- DCF法(割引現在価値法)
- SPC(特別目的会社)
- ストックオプション
- 株主間契約
- ROA(総資産利益率)
- BS(貸借対照表)
- PL(損益計算書)
- 連結決算
- PBR(株価純資産倍率)
- ROE(自己資本利益率)
- 自社株買い
- 株式消却
- 持分法適用会社
- ステークホルダー
- コンプライアンス
- スピンオフ
- 完全子会社
- 非連結会社
- リーグテーブル
- 株式併合
- 買戻条項
- ポイズン・ピル
- スクイーズアウト
- フリーキャッシュフロー
- NDA(機密保持契約)
- ホワイトナイト
- インサイダー取引
- 事業拡大
- 事業再生
- 経営者保証
- 業務移管
- 債券
- 適時開示
- MOU(基本合意書)
- SPA(株式譲渡契約書)
- テンダー・オファー
- ペーパーカンパニー
- 黄金株
- リストラクチャリング
- スコーチドアースディフェンス
- 包括利益
- 偶発債務
- DDS
- NPV(正味現在価値)
- 黒字倒産
- プライベートエクイティ(未公開株式)
- TSA
- プロラタ方式
- 割引現在価値
- サクセッションプラン
- 事業再生ADR
- 負ののれん
- フィナンシャルバイヤー
- XBRL
- 匿名組合
- 特別決議
- ノンリコースローン
- オーバーアロットメント
- シニアローン
- スーパー・マジョリティ条項
- スタンドスティル条項
- ブリッジローン
- DIPファイナンス
- 労働契約承継法
- 純有利子負債(ネット デット)
- 財務シナジー
- コストシナジー
- 連結子会社
- ホールディングス
- 投資銀行
- サイトM&A
- カバレッジ部門
- 適格合併
- コングロマリット
- 債務超過
- インカムゲイン
- 零細企業
- 持株会
- アライアンス
- 非適格組織再編
- 適格組織再編
- 配当所得
- 株式譲渡所得
- 組織再編税制
- 投資ファンド
- 事業戦略
- 技術提携
- 企業再生
- ベンチャーキャピタル(VC)
- 関連会社
- ノンコア事業
- コア事業
- 規模の経済
- 企業生存率
- 子会社化
- オーナー企業
- キラー・ビー
- クラウン・ジュエル
- グリーン・メール
- ゴールデンパラシュート
- ジューイッシュ・デンティスト
- スタッガード・ボード
- 財務デューデリジェンス
- 分社化
- スケールメリット
- ストラクチャー
- DES(債務の株式化)
- PER(株価収益率)
- 利益相反
- IPO
- エグゼキューション
- 個人保証
- 資本性劣後ローン
- 株式の贈与
- 株式相続
- 民事再生
- 創業者利益
- M&Aシニアエキスパート認定制度
- PPA(取得原価の配分)
- 100日プラン
- 従業員リテンション
- 事業承継ファンド
- 事業承継信託
- 垂直型M&A
- M&Aファイナンス
- M&Aブティック
- サルベージ・レシオ
- アーニング・マルチプル・レシオ
- 譲渡承認取締役会
- 産業再生法
- 源泉徴収
- みなし配当
- 地位承継
- コーポレートガバナンス
- 合併比率
- 事業承継士
- 事業譲渡契約書
- 株式譲渡承認請求書
- 合併契約書
- 簡易合併
- 逆三角合併
- 競業避止義務
- プロキシー・ファイト
- パールハーバー・ファイル
- Qレシオ
- MSCB
- IFRS
- 株式譲渡制限会社
- 大量保有報告
- 自己株式
- 現物出資
- チャイニーズ・ウォール
- コントロールプレミアム
- キャッシュ・テンダー・オファー
- 買収プレミアム
- 海外M&A
- 友好的買収
- 事業買収
- M&Aコンサルティング
- EV(事業価値)
- MEBO
- アセットパーチェス
- ゴーイング・プライベート(Going Private)
- シェルカンパニー
- バックエンド・ピル
- パックマン・ディフェンス
- 事業譲渡類似株式
- 株式移転計画書
- 簿外債務
- 売渡請求
- 財務アドバイザー
- レバレッジ効果
- 減損価格
- 合併公告
- LBOファイナンス
- アーンアウト
- オリジネーション
- シナジーバイヤー
- シャーク・リペラント
- スーイサイド・ピル
- ティン・パラシュート
- 事業再生ファンド
- PEファンド
- バイアウトファンド
- MBOファンド
- 低廉譲渡
- 独占交渉権
- 基本合意
- 企業再生支援機構
- 監査法人
- ネームクリア
- M&Aアドバイザー
- IN-IN・OUT-IN・IN-OUT
- 吸収分割契約書
- 人事デューデリジェンス
- 再生ファンド
- サーチファンド
- 税務デューデリジェンス
- 第三者承継
- 総数引受契約
- TMK(特定目的会社)
- SPAC(特別買収目的会社)
- 相対取引
- LOI(レターオブインテント)
- アナジー効果
- エクイティファイナンス
M&Aへの疑問

M&Aに関する疑問に市場統計や弊社実績情報から、分かりやすくお答えします。
業種別M&A動向

日本国内におけるM&Aの件数は近年増加傾向にあります。その背景には、企業を取り巻く環境の変化があります。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。